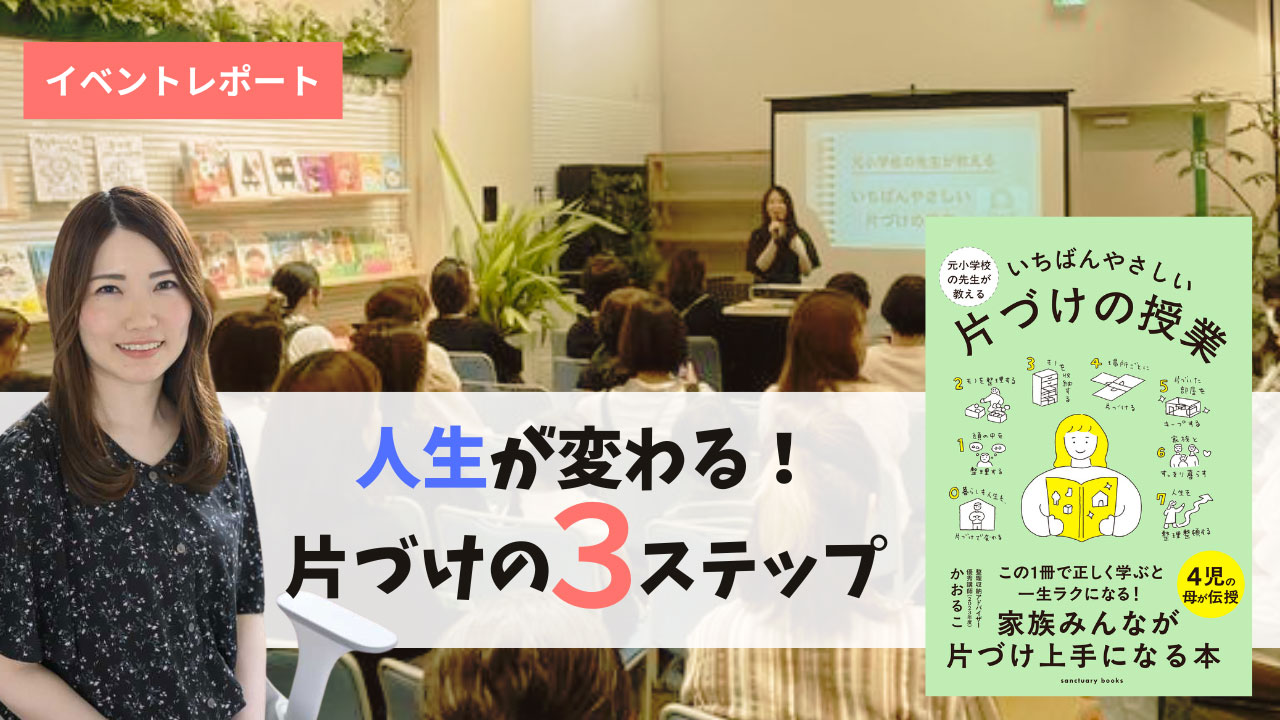SNSのフォロワー21万人の人気整理収納アドバイザー、かおるこさんが『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業』を出版。4児(三つ子+1児)の母という圧倒的な説得力、そして、元小学校の先生ならではのわかりやすい解説で、片づけの全体像をひもとき、「リバウンドなし」「だれでも再現できる」方法を伝授してくれる1冊です。
出版記念トークイベントでは、混同しがちな「整理」「収納」「片づけ」のステップについて、カギとなる要素をそれぞれ紹介。片づけられないことに悩む出席者たちに、多くの気づきをもたらしてくれる会となりました。
目次
片づけができないと多くのデメリットがある
「1日13分」……なんの数字か分かる方はいらっしゃいますか?
実はこれ、私たちが「探し物の平均時間」と言われる分数です。1年間で考えると、×365で4745分。79時間、つまり1年365日のうち約3日間は寝ずに探し物をしているという計算になります。けっこう長いですよね。この数字は平均なので、モノが多い人は、おそらくもっと時間を無駄にしてしまっているのではないでしょうか。
このように、片づけをしないといろんなデメリットがあります。
たとえば、家事や仕事の効率が悪くなります。仕事に必要なものが見つからず、提出期限が守れなかったりすると、同僚からは「仕事ができない人」と思われてしまいます。
また、必要なモノが把握できていないことで無駄買い、つまり無駄な出費が増えます。「ない」と思って同じモノを買ったのに、後から出てきたり。モノが多い人は「買う」ことへのハードルが低く、「セールだから買っておこう」といった行動もとりがちです。
家が片づいていないと落ち着かないし、気軽に人を家に呼ぶこともできません。また、災害の際にはモノは凶器と化します。高いところからモノが落ちてきて命を落とす、といったことも起こり得るのです。
そして、長期で入院するなど、自分に万が一のことがあったとき、モノが多いことは残された家族に大きな負担をかけてしまいます。自分のモノでも整理するのは大変なのだから、他人のモノなら時間と労力がさらにかかるのは当然ですよね。
片づけをすると、これらのデメリットが解消されるだけでなく、「家の中がすっきりする、家が広くなる」「時間、心、お金にゆとりが生まれる」など、たくさんのプラスの変化が起きてきます。
「整理」→「収納」→「片づけ」の順で取り組もう
「片づけをしよう」と思ったとき、収納用品を買いに行くという人は多いと思います。SNSやテレビの情報番組で見た「カンタン収納術」とまったく同じ用品を買えば、同じように片づくんじゃないかと……実は、それでは片づきません。
まずは、「モノの整理」をする必要があります。片づけというと「モノを捨てる」ことだと思われがちですが、まずやるべきは「いるモノといらないモノを判断し、必要なモノを選ぶ」こと。一見、同じように思えますが、「必要なモノを残していく」というイメージですね。
必要なモノだけになったら初めて、それらを使いやすく収める「収納」に進むことができます。その次が、日々使ったものを元の場所に戻す「片づけ」のステップです。ここまでの流れをひっくるめて「片づけ」と呼ぶことも多いですが、本来の意味はこちらです。
なんのために片づけて、どんな暮らしをしたいのか
「片づけができない」という人は、はじめの「整理」の段階でつまずいていることが圧倒的に多いです。整理するだけで、もう8割ぐらい片づけは終わっているようなもの。まずは、「頭の中の整理」から始めましょう。
多くの人は「モノを減らせばいいんでしょ? どんどん捨てよう」と思って手を動かしがちですか、「自分がそもそもなんのために片づけをするのか、どんな暮らしをしていきたいのか」という軸を持ち、何を残して、何を手放すべきなのかを決めましょう。
具体的なやり方としては、まず全部のモノを出すこと。片づけが苦手な人は、引き出しから必要のなさそうなものを引っ張り出してきて悩む、ということをやりがちですが、持っているものを全部出すところから始めてほしいです。
クローゼットの中の服を全部出すのは大変なので、「今日はこのクローゼットの中のこの引き出し1段分」「今日はTシャツ全部」などのように、狭い範囲に絞ってやるのがいいでしょう。とにかく大事なのは全部出すこと。全部出すからこそ「私、こんなに持ってたんだ」、「こんなにいらないよね」ということに気づけるのです。
全部出したら、それを使っているかどうかで分けていきます。「使っている」の基準は、1年の間に1回でも使っているかどうか。分ける作業が済んだら、そこから自分にとって必要なモノを選んでいきます。
「今の自分にとって必要なモノ」を残す
ここで、選ぶときの基準を3つ紹介しましょう。まずは、先ほども話した「使っているモノかどうか」。この基準はいちばん大切です。今は使っていないけど、「今後使う」と確実に言い切れるモノも残してもらってかまいません。また、使っていなかったとしても、「持っていると気分が上がるモノ」、自分にとって「持つ意味があるモノ」も選んでOKです。
つまり、大切なのは「今の自分はどうしたいか、今の自分にとって必要なのか」ということ。「いつか使うかも」と言ってモノを捨てられない人は多いですが、大事なのは今。「いつか」を優先しすぎた結果、モノが増えすぎて今の生活が苦しくなるのはおかしいですよね。
そして、「今」と同じように「自分」も大事です。捨てない理由として「まだ使えるから」言う人がいますが、たとえば洋服なら9割方「着ようと思えば着られる」わけで、手放せるモノなどなくなってしまいます。「使えるモノかどうか」ではなく、「自分が使っているか、使いたいか」を大事にしてほしいと思います。
家族と片づけを進めるポイント
整理が済んだら収納、つまり片づけの仕組みをつくるステップになります。本書にも「家族はチーム」と書きましたが、家族みんなで同じ目的に向かって行動できると、片づけはスムーズに進みます。「来月に○◯ファミリーが来てバーベキューをするから、それまでにみんなで片づけをがんばろう」「年末の大掃除は▲日までに終わらせよう」など、目的を共有するのがいいですね。
広い家をお母さんひとりで片づけるのは難しいので、役割を分担しましょう。「自分のモノは自分で片づける、自分で管理する」を基本に、お子さんにも役割を与えながら進めていきます。お子さんが小さいと難しいかもしれませんが、保育園・幼稚園にもなれば簡単なことならできるはず。
片づけのルールを決めるのも大切です。たとえば我が家の場合、「自分の洗濯物は自分で畳む」「みんなで使うタオルは1週間ごとの当番制」「学校から帰ってきたらこのカゴにプリントを入れる」などのルールがあります。
ハードルが高いと守れなくなってしまうので、ルールはシンプルでわかりやすいものにしておくのがいいですね。また、お母さんひとりで決めるのではなく、「どういうルールだったらできそう?」などと家族の意見も聞いておくのがおすすめです。ルール決めに参加していると、子どもも守らないわけにはいかなくなります。
片づけが苦手な家族への声かけ
「片づけが苦手な家族をどうしたらいいんでしょうか」「夫がモノを捨ててくれないから、私が勝手に捨ててます」といった声を聞くことがありますが、相手を変えようとするのはやめたほうがいいです。
「子どもに片づけさせたい」「夫に捨てさせたい」と思ったところで、人は、人から言われたところで変われるものではありません。自分で変わろうと思って初めて変われるわけであり、人から言われるとかえって逆効果になることも。
他人と過去は変えられません。変えられるのは未来と自分だけ。だから、「まずは自分のモノから片づけてみようかな」「声かけの仕方を変えてみようかな」など、自分で変えられるところを変えた方が、ストレスも少ないですし、それによって家族が変化するというケースも多いです。
そして、つい家族という身近な相手だと「こんなモノいらないでしょ」「捨てちゃいなよ」のような声かけをしてしまいがちですが、それよりも、相手を理解しようとする気持ちを持つようにしましょう。
たとえば、夫が片づけられないのは、「仕事が忙しくて片づける時間がないのかな」「片づけ方が分かっていないのかな」となどと想像すること。家族と進める片づけは、ある意味、家族との関係がいちばん重要になってきます。
最後に、片づけを始める前の、家族への声かけの例をご紹介します。
×「片づけなさい」「なんで片づけしないの」
◯「どこを片づける?」「いつ片づける?」=相手に選んでもらう
◯「一緒にやろう」「手伝うよ」=寄り添う
◯「お母さん大変だから手伝ってくれない?」=お願い
◯「片づけてもらえるとうれしいな」=相談
◯「片づけると友達を呼べるようになるね」「家でホームパーティーができるね」=メリットを伝える
これらはあくまでも一例です。どんな言葉が響くかは人それぞれなので、いろんな言葉をかけみて「うちの子、うちの夫にはこれが響く」という言葉を見つけてみてください。
そして、ちょっとでも動いてくれたら、「すごーい」「ありがとう」「すっきりしたね」などとほめてあげましょう。ポジティブな声かけをすると、それだけでもうれしい気持ちになって、「もうちょっとがんばろうかな」と思えてくるようになるはずです。