「家の中が物であふれかえって、どこから片付ければいいのかわからない」
「物を捨てるのは罪悪感があるけれど、今の状況はもう限界」
物が積み重なって収拾がつかなくなった家での暮らしは、毎日がストレスの連続です。探し物に時間を取られ、急な来客には慌てふためき、家族からも文句を言われる日々は嫌ですよね。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- 物が多い家で暮らすことの具体的な問題点
- 物が多い家を効率的に片付ける5つのステップ
- リバウンドしない片付けテクニック5選
物が多い家でも、正しい手順とコツさえ知れば必ず片付きます。無理に完璧を目指さず、家族みんなが快適に過ごせる住空間を手に入れましょう。
目次
物が多い家で暮らす問題点
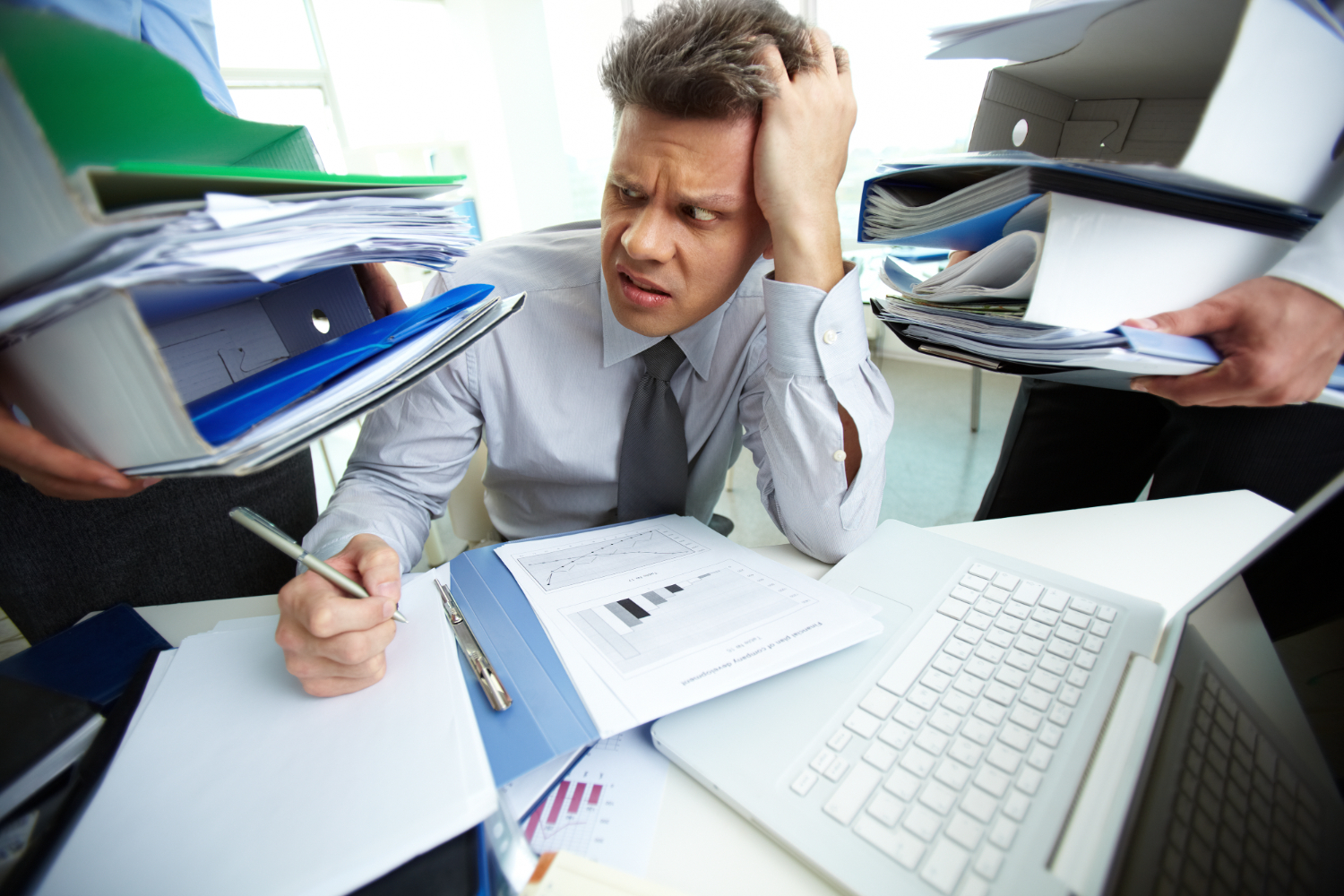
物が多い家での生活は、想像以上に大きな負担となります。単に見た目が悪いだけでなく、日常生活のあらゆる場面で支障をきたすのです。
物があふれた環境が引き起こす主な問題を3つの観点から詳しく見ていきます。
探し物のせいで時間を失う
探し物のせいで時間を失うことは、物が多い家の最も深刻な問題です。必要な物が見つからず、毎日20〜30分を探し物に費やしている家庭も珍しくありません。
物が多い環境では、以下のような状況が日常的に発生します。
- 同じ場所を何度も探してしまう
- 物の下に隠れて見つからない
- 収納場所を忘れてしまう
- 家族が勝手に移動させている
1日10分の探し物は、1年間で約60時間にもなります。この時間があれば、もっと家族との会話や自分の時間を大切にできるはずです。
精神的なストレスが溜まる
精神的なストレスが溜まるのも、物が多い家の深刻な問題点です。視界に入る物の多さは、脳に常に刺激を与え続け、無意識のうちにストレスを蓄積させます。
物があふれた空間にいると、以下のような心理状態に陥りがちです。
- どこから手をつけていいかわからない無力感
- 人を家に招くことへの恐怖心
- 「片付けられない人」というレッテルへの自己嫌悪
- 家族に申し訳ないという罪悪感
特に、急な来客への対応ができない不安は、多くの人が抱える深刻な悩みです。また、SNSで見る整理整頓された美しい部屋と自分の現実を比較し、自己肯定感が下がってしまうことも少なくありません。
家族関係が悪くなる
家族関係が悪くなることも、物が多い家の見過ごせない問題です。物があふれた環境は、家族間のコミュニケーションを阻害し、イライラや不満の原因となります。
具体的には、以下のような状況が家族関係に悪影響を与えます。
- 物の置き場所をめぐる家族間の口論
- 片付けない家族への不満の蓄積
- 友達を家に呼べない子どもの不満
- リラックスできない環境での家族時間の質の低下
特に成長期の子どもにとって、友達を家に招けない環境は深刻な問題です。「なぜうちだけ片付いていないの?」という子どもの質問に答えられず、親としての自信を失ってしまう方も多くいます。
また、家族が「家事を手伝いたいけれど、どこに何があるかわからない」と感じ、結果として家事負担がひとりに集中してしまう悪循環も生まれます。
物が多い家の具体的片付け手順5ステップ

物が多い家を効率的に片付けるためには、正しい手順に沿って進めることが重要です。やみくもに始めるのではなく、段階的にアプローチすることで、確実に成果を上げられます。
以下の5ステップを順番に実践すれば、物があふれた家でも必ず片付けることができます。ぜひ確認してみてください。
ステップ1:エリアを決めて物を全部出す
まずは、エリアを決めて物を全部出すことから始めましょう。一度にすべてを片付けようとせず、リビングテーブル、クローゼット、キッチンの引き出しなど、限定されたエリアから取り組みます。
最初は以下のような小さなエリアから始めることをおすすめします。
- ダイニングテーブルの上
- 玄関の靴箱
- 洗面台の引き出し一段
- 本棚一段分
選んだエリアの物をすべて取り出し、一箇所に集めて全体量を把握します。この作業により、自分がどれだけの物を持っているかが明確になり、片付けへの意識が変わります。
ステップ2:出しっぱなしの物を仕分けする
次に、出しっぱなしの物も仕分けしましょう。明らかにその場所にないべき物から優先的に処理していきます。
仕分けは以下の4つのカテゴリーに分けて進めます。
- 本来の場所に戻すべき物
- 別の場所で保管すべき物
- 使わないけれど捨てられない物
- 明らかに不要な物
判断に迷う物は「保留ボックス」を用意して一時的に入れておきましょう。すべての仕分けが終わった後で、改めて検討すれば効率的です。
この段階では完璧を求めず、直感的な判断で構いません。迷いすぎると作業が止まってしまい、片付けが嫌になってしまいます。
ステップ3:捨てる物と残す物を見極める
出した物のうち、捨てる物と残す物を見極めることが、片付け成功の最も重要なポイントです。物を大切にする気持ちは素晴らしいことですが、現実的な判断基準を設けることも必要です。
以下の基準に沿って判断を進めてみてください。
- 1年以上使っていない物
- 壊れているor汚れが落ちない物
- 同じ用途の物が複数ある場合の余剰分
- サイズが合わなくなった衣類
- 賞味期限切れの食品や化粧品
物を捨てることに罪悪感を感じる場合は、「物に感謝の気持ちを込めてお別れする」という考え方を取り入れてみましょう。役目を終えた物に「ありがとう」と声をかけることで、気持ちの整理がつきます。
また、高価だった物や思い出の品については、写真に撮って記録に残すという方法もあります。物理的な物は手放しても、記憶は残せるのです。
ステップ4:グループ分けして収納を考える
グループ分けして収納を考えることで、使いやすく戻しやすい収納システムが完成します。同じ用途や同じ場所で使う物をまとめることが基本です。
効果的なグループ分けの例を以下に示します。
- 文房具:ペン類、のり・テープ類、はさみ・カッター類
- 薬品類:内服薬、外用薬、絆創膏・包帯類
- 掃除用品:洗剤類、道具類、使い捨て用品
- 書類:取扱説明書、保証書、重要書類
グループ分けができたら、使用頻度に応じて収納場所を決定します。毎日使う物は手の届きやすい場所に、たまにしか使わない物は高い場所や奥の方に配置しましょう。
収納を考えるときは、家族の動線も意識してください。子どもが使う物は子どもの手の届く高さに、夫婦で共用する物はどちらからもアクセスしやすい場所に置くことが大切です。
ステップ5:不要物を処分する
不要物を処分することで、片付け作業が完了します。処分方法を事前に調べておくことで、スムーズに作業を進められます。
処分するときのコツは、ゴミ収集日の前日に作業を完了させることです。不要な物が家の中に長期間残っていると、再び散らかる原因となります。
また、処分費用がかかる物については、事前に予算を確保しておきましょう。片付けを完了させるための必要経費と考えることが重要です。
物が多い家を片付けるテクニック5選

こちらでは、家を片付けるテクニックを紹介します。
目立つ場所や頻繁に使うスペースから片付ける
目立つ場所や頻繁に使うスペースから片付けることで、短期間で成果を実感できます。玄関、リビング、ダイニングテーブルなど、家族がよく使う場所を優先的に整理しましょう。
目に見える変化があると達成感が得られ、片付けのモチベーションが維持できます。家族からも「きれいになったね」という言葉をもらいやすく、自信回復にもつながります。
また、来客時に最も人の目に触れる場所から始めることで、急な訪問者があっても慌てずに済むようになります。
「収納する物」が決まってから収納アイテムを購入する
「収納する物」が決まってから収納アイテムを購入することは、無駄な出費を避けるための重要なポイントです。多くの人が先に収納用品を買ってしまい、結果的に使わない収納グッズが増えてしまいます。
収納アイテム購入の正しい手順は以下の通りです。
- 収納したい物の種類と量を正確に把握する
- 収納場所のサイズを測定する
- 使用頻度に応じた取り出しやすさを考慮する
- 家族の使いやすさを確認する
- 予算に合わせて商品を選択する
例えば、文房具を整理する場合、まず「ペン5本、はさみ1本、のり2個、クリップ1箱」など具体的な内容を把握します。その後、収納場所の幅・奥行き・高さを測ってから、最適なサイズの仕切りケースを購入しましょう。
この方法により、ぴったりサイズの収納グッズが手に入り、見た目も美しく機能的な収納が完成します。
アイテムをグループでまとめて管理する
アイテムをグループでまとめて管理することで、探し物の時間を大幅に短縮できます。同じ目的で使う物、同じ場所で使う物を一箇所にまとめる習慣をつけましょう。
「○○をするときに必要な物」という視点でグループ化すると、実用的なまとめ方ができます。使う場面をイメージしながら、関連する物を集めてみてください。
また、グループごとにラベルをつけると、家族にもわかりやすく、元の場所に戻してもらいやすくなります。
使用頻度で物の置き場所を決める
使用頻度で物の置き場所を決めることは、日常生活の効率を格段に向上させるテクニックです。よく使う物ほど手の届きやすい場所に、めったに使わない物は奥や高い場所に配置しましょう。
例えば、キッチンでは毎日使う調味料は手の届く場所に、お正月にしか使わない重箱は高い棚に収納します。この配置により、料理の効率が大幅に向上します。
また、家族それぞれの使用頻度も考慮することが大切です。子どもがよく使う物は子どもの手の届く高さに、夫婦で共用する物は両方からアクセスしやすい場所に置きましょう。
片付けが楽しくなる工夫をする
片付けが楽しくなる工夫をすることで、継続的に整理整頓ができるようになります。単調で面倒な作業という意識を変え、ゲーム感覚で取り組める環境を作りましょう。
片付けを楽しくする具体的な工夫をご紹介します。
- 音楽をかけながら片付ける
- タイマーを使って制限時間内に完了させる
- 家族でチーム戦にして競争する
- 完了後に小さなご褒美を用意する
「15分間でリビングをきれいにできたら、お菓子をあげる」というようにゲーム要素を取り入れると、子どもも積極的に参加してくれます。家族全員で取り組むことで、責任感も生まれ、維持しやすくなります。
また、片付けた後の美しい空間で家族団らんの時間を過ごすことで、「片付けると良いことがある」という実感を得られます。
まとめ
物が多い家の片付けは、正しい手順とテクニックを知ることで必ず成功できます。完璧を目指さず、家族が快適に過ごせる環境を作ることを目標にして取り組んでください。
今回ご紹介した5つの手順を実践し、5つのテクニックを活用すれば、物に支配される生活から抜け出せます。小さなエリアから始めて、徐々に範囲を広げていくことが成功の秘訣です。
片付けは一度で完了する作業ではありません。日々の習慣として継続することで、理想の住環境を維持できるようになります。
もし、より本格的な片付けのコツが知りたいという場合は、『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業』という書籍をご確認ください。
フォロワー21万人の人気整理収納アドバイザーが、誰でも簡単に実践できる片付けのノウハウを、余すこと無く解説しています。きれいな部屋を手に入れて、身も心もリラックスしたいと考えている方は、ぜひ書籍を手に取ってみてください。




