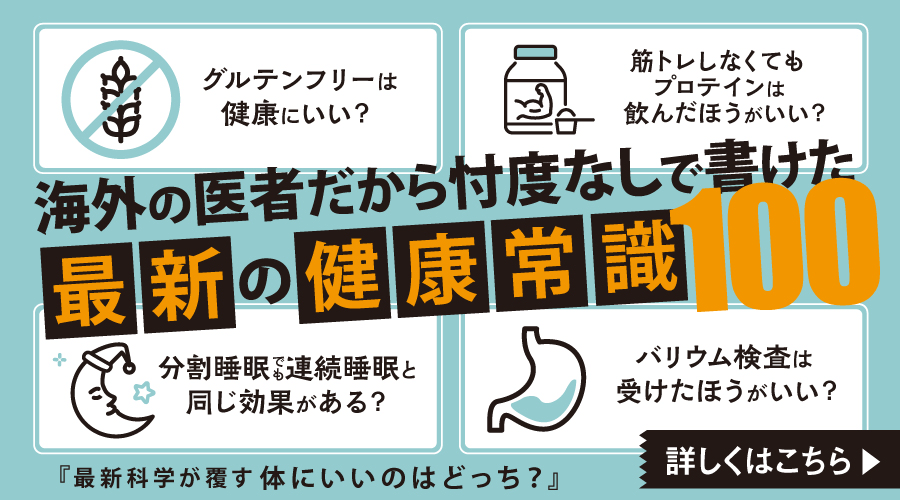鹿児島の田舎で育ち、気づけば20歳。学歴なし、語学力ゼロ、格闘技未経験――そんな私が、貯金600万円を握りしめて飛び込んだハワイの格闘技留学。
異国の地での不安や孤独、そして数え切れないほどの挫折。しかし、それらすべての経験が私の内側に眠る強さを引き出してくれました。
失敗と迷いを繰り返した先で出会ったのは、新しい世界と、本当の自分でした。
目次
はじめに:ご挨拶と自己紹介
この記事をご覧いただき、ありがとうございます。吉田実代と申します。
現在36歳、9歳の娘と共に2年前からニューヨークに移住しました。世間では“闘うシングルマザー”と呼ばれることが多いですが、私はただ、自分の人生に正直に向き合い続けてきただけです。女子ボクシングで世界2階級制覇というタイトルを手にしましたが、そこに至るまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。
この文章を通じて、私がどのようにして「何者でもない自分」から「世界チャンピオン」へと成長していったのか、少しでも伝えられたらと思います。
鹿児島で育った少女時代




私は鹿児島の小さな町で生まれ育ちました。3歳のときに両親が離婚し、兄はしばらくして父と暮らすことに。母と二人三脚の生活が始まりました。裕福ではないけれど、母は懸命に働き、私を育ててくれました。
自然に囲まれた美しい故郷で、のびのびと過ごした幼少期。しかし、海外や広い世界とは無縁の生活で、狭いコミュニティの中でのびることが当たり前だと思っていました。私にとって「世界」は、テレビや本の中の遠い存在だったのです。
ソフトボールにかけた日々と挫折




小学生の頃、私はソフトボールに夢中になりました。キャプテンとしてチームをまとめ、4番バッター、ピッチャーとしても活躍。中学では新人戦で優勝し、オリンピック出場を夢見るほど本気で取り組んでいました。
しかし、家庭の事情や母が忙しくサポートできない現実、さらにチーム内での不和が重なり、次第に心が折れていきました。遠征試合に母が来られないことが、子どもながらに寂しくて悔しくて…。結果、私はソフトボールを辞めてしまいました。この挫折は私にとって人生初の大きな壁でした。
反骨心と新しい挑戦/ダンスとの出会いと挫折
「このままでは終わらない、絶対に見返してやる!」と、ソフトボールでの挫折をバネにHIPHOPダンスを始めました。親のサポートがほとんど不要な環境だったため、自分の力でやり遂げようと思ったのです。しかし、最初の情熱は次第に薄れ、気づけば夜遊びに逃げる日々。レッスンもサボりがちになり、最終的にはダンスも辞めてしまいました。
「また逃げてしまった…」と自分自身を責め、情けなさで胸がいっぱいになったのを覚えています。それでも心のどこかで、「まだ終わりたくない」という気持ちが燻っていました。