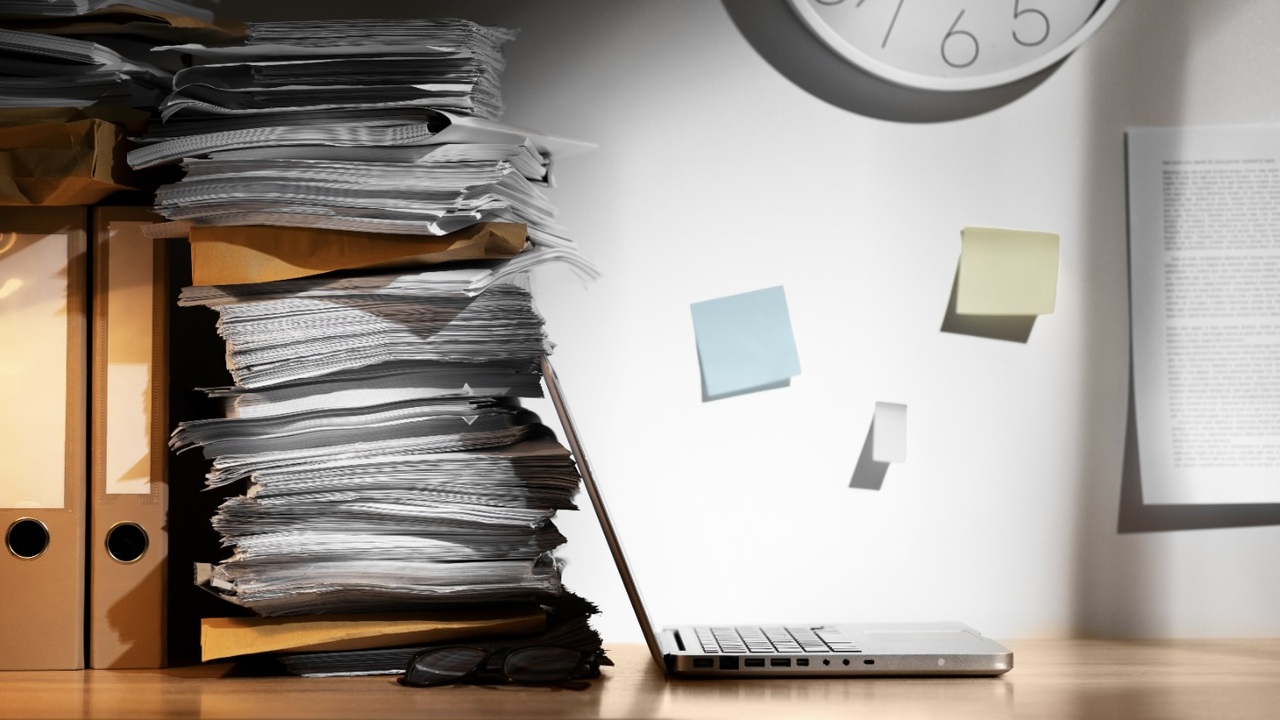「片付けられないのって、何かの障害があるからなの?」
「もしかして私、病気なのかな…」
部屋が散らかっていて片付けられない状態が続くと、自分に何か問題があるのではないかと不安になりますよね。実際に、片付けられない背景には病気や発達障害が隠れている場合もあります。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- 片付けられない人に考えられる病気の種類
- 病気以外で片付けられない主な要因
- 片付けられる人になるための具体的な5ステップ
この記事を読むことで、自分の状況を客観的に把握でき、適切な対処法が見つかります。ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
部屋を片付けられない人に考えられる病気

部屋を片付けられない状態が続く場合、以下のような病気や発達障害が関係している可能性があります。ただし、自己判断は禁物です。気になる症状がある場合は、専門医への相談をおすすめします。
ADHD
ADHDは注意欠如・多動性障害の略称で、集中力の維持や物事の整理整頓に困難を抱える発達障害です。
ADHDの人に見られる片付けに関する特徴は以下の通りです。
- 物事に集中できず、途中で別のことを始めてしまう
- 整理整頓の手順を覚えられない
- 物の定位置を決められない
- 衝動的に物を購入してしまう
- 先延ばし癖がある
例えば、「部屋を片付けよう」と思っても、どこから手をつけていいか分からず、途中で他のことに気を取られてしまうパターンが典型的です。
ASD
ASD(自閉スペクトラム症)の人は、変化への適応が苦手で、決まったルーティンを好む傾向があります。
ASDと片付けの関係には、以下のような特徴があります。
- 物への強いこだわりがあり、捨てられない
- 収納方法を変えることに抵抗感がある
- 感覚過敏により、特定の素材や音を避ける
- 完璧主義で、中途半端な状態を嫌う
- 他人の片付けルールを理解しにくい
物に対する独特のこだわりがあるため、一般的な「いらない物は捨てる」という考え方が当てはまらない場合があります。
例えば、同じ種類のペンを大量に集めていたり、使わない物でも「いつか必要になる」という理由で保管し続けたりします。ASDの特性を理解した上で、個人に合わせた片付け方法を見つけることが大切です。
強迫性障害
強迫性障害は、不安や恐怖を和らげるために特定の行為を繰り返してしまう精神疾患です。
片付けに関連する強迫性障害の症状には、以下があります。
- 物を捨てることへの強い不安
- 完璧に整理しないと気が済まない
- 特定の順序や方法でないと片付けられない
- 汚染への恐怖から物に触れない
- 片付け作業を何度も繰り返してしまう
特にためこみ症候群(ホーディング)と呼ばれる症状では、価値のない物でも「捨てると何か悪いことが起きる」という不安から手放せなくなります。
例えば、古い新聞や雑誌、壊れた電化製品なども「いつか必要になるかもしれない」と考え、部屋に溜め込み続けてしまいます。認知行動療法や薬物療法により改善が期待できるため、専門医への相談が必要です。
うつ病
うつ病では、意欲の低下や疲労感により、日常的な活動への取り組みが困難になります。
- やる気が起きず、片付けに着手できない
- 集中力が続かない
- 疲れやすく、途中で断念してしまう
- 自分を責めてしまい、さらに動けなくなる
- 部屋の散らかりが症状を悪化させる悪循環
うつ病の場合、片付けられないのは病気の症状の一つであり、本人の怠けや性格の問題ではありません。
症状が改善されれば、自然と片付けへの意欲も回復します。無理をせず、まずは精神的な治療に専念することが先決です。家族や周囲の理解とサポートも欠かせません。
認知症
認知症では、記憶力や判断力の低下により、片付けや整理整頓が困難になります。
- 物をしまった場所を忘れてしまう
- 同じ物を何度も購入してしまう
- いらない物と必要な物の判断ができない
- 片付けの手順が分からなくなる
- 危険な物を適切に管理できない
特に軽度認知障害の段階では、本人も家族も「年のせい」と見過ごしがちです。しかし、早期発見・早期対応により、進行を遅らせることが可能な場合もあります。
例えば、冷蔵庫の中に同じ食材が大量にあったり、重要な書類を紛失したりする頻度が増えた場合は、医療機関での検査をおすすめします。
部屋を片付けられないのは病気ではないことも多い!主な要因を解説
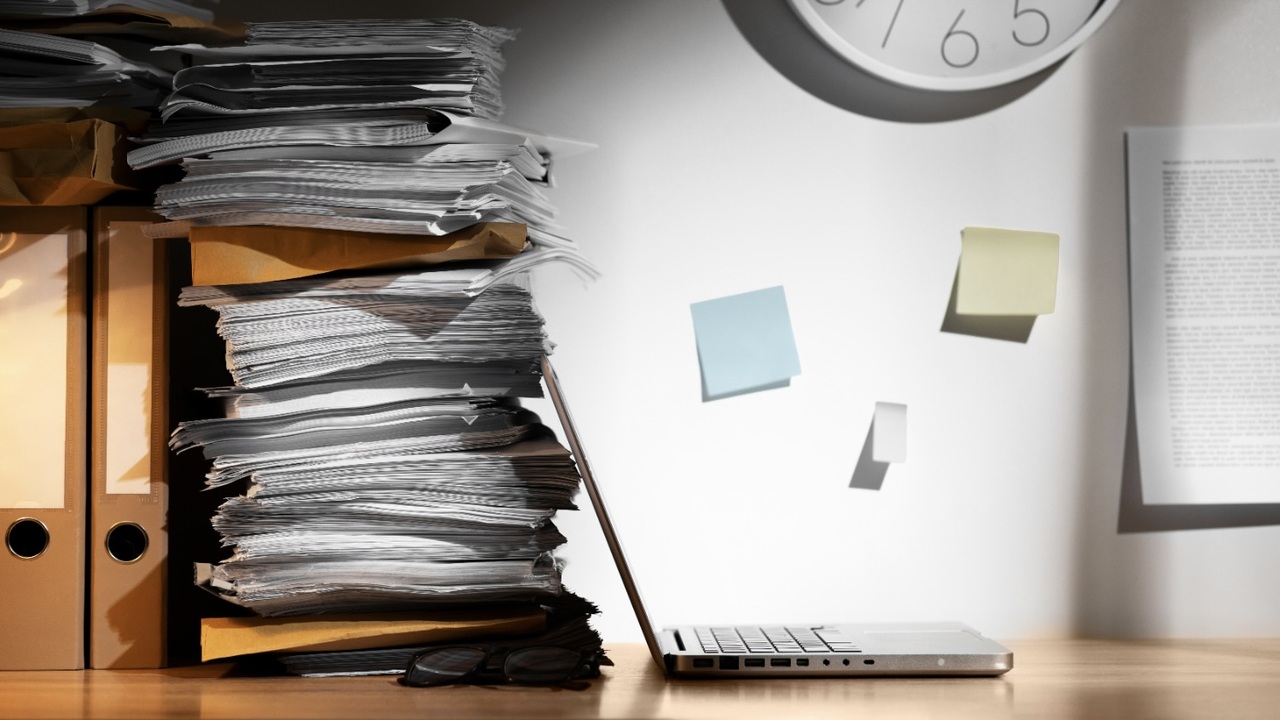
片付けられないからといって、必ずしも病気や障害があるわけではありません。適切な方法を知り、環境を整えることで改善できる場合が多いのです。
病気が疑われる場合は専門家への相談が必要ですが、そうでなければ自分でも片付け上手になれる可能性は十分あります。以下では、病気以外の主な要因について解説します。
片付け方を知らない
実は、多くの人が体系的な片付け方法を学ぶ機会がないまま大人になっています。そのため、片付け方を知らないという方は非常に多いです。
- とりあえず目に見える場所だけ片付ける
- 収納用品を買えば解決すると思っている
- 一度に全部片付けようとして挫折する
- 物の定位置を決めずに適当にしまう
- 片付けと掃除の区別がついていない
片付けには正しい手順とコツがあります。まずは物を減らし、残った物の定位置を決め、使ったら元に戻すという基本的なサイクルを身につけましょう。
例えば、「出したら戻す」「1つ買ったら1つ手放す」といったシンプルなルールから始めると効果的です。片付けは技術なので、練習すれば誰でも上達できます。
モノに執着しすぎている
物への過度な執着は、片付けの大きな障害となります。現代社会では物があふれており、「もったいない」という気持ちが強すぎると部屋が物で溢れかえってしまいます。
物の価値は、使ってこそ発揮されるものです。使わずに保管しているだけでは、物も部屋も活かされません。
例えば、「1年間使わなかった物は手放す」「同じような物は1つだけ残す」といった明確な基準を設けることで、執着心を和らげることができます。物よりも快適な空間を優先する考え方に切り替えましょう。
時間に余裕がない
忙しい日常生活の中では、片付けの時間を確保することが困難な場合があります。しかし、時間がないからこそ、効率的な片付けシステムが必要です。
実は、片付いた部屋の方が時短効果が高いのです。物の定位置が決まっていれば、探し物の時間が大幅に短縮されます。
例えば、「帰宅後5分だけ片付けタイム」「朝の身支度前に昨日使った物を元に戻す」など、短時間でも継続できるルーティンを作ることが効果的です。
人を招く機会がない
一人暮らしや在宅勤務が多い人は、他人に部屋を見られる機会がないため、片付けの動機が弱くなりがちです。
定期的に人を招く習慣を作ることで、自然と片付けの動機が生まれます。友人や家族を招く予定を入れることで、良い緊張感と目標ができるでしょう。
例えば、月に1回は友人を招いてお茶を飲む、家族に部屋を見てもらうなど、小さな約束から始めてみてください。他者の視点が入ることで、部屋の問題点にも気づきやすくなります。
部屋を片付けられる人になるための具体的な5ステップ

部屋を片付けられる人になるためには、正しい手順を踏んで段階的に取り組むことが大切です。一度にすべてを変えようとせず、以下の5つのステップを順番に実践してみてください。
継続できるシステムを作ることで、リバウンドしない片付けスキルが身につきます。
片付けの順番を紙に書き出す
片付けの順番を紙に書き出すことは、作業を可視化して迷いを減らす効果があります。頭の中だけで考えていると、どこから手をつけていいか分からなくなってしまいます。
- 部屋を見回して散らかっている場所をリストアップ
- 使用頻度の高い場所から優先順位をつける
- 1日でできる範囲に作業を分割
- 完了したらチェックマークをつける
- 次回の予定も合わせて記入
例えば、「玄関→リビングテーブル→キッチンのシンク→クローゼット」という順番で、使用頻度の高い場所から着手します。
作業を紙に書くことで達成感も得られ、モチベーションの維持にもつながります。スマートフォンのメモ機能でも構いませんが、手書きの方が記憶に残りやすくおすすめです。
捨てるモノのルールを明確にする
捨てるモノのルールを明確にすることで、判断に迷う時間を短縮できます。感情的な判断ではなく、客観的な基準を設けることが成功の鍵です。
- 1年以上使っていない物
- 壊れていて修理する予定のない物
- 同じ用途の物が複数ある場合の劣化品
- サイズが合わない衣類
- 期限切れの食品や化粧品
「迷ったら保留ボックス」を作ることも有効です。すぐに判断できない物は一時的に保留し、3ヶ月後に再度見直します。その間に使わなければ手放すというルールを設けましょう。
例えば、「もらいものだから捨てにくい」「高かったから捨てられない」という感情的な理由は一旦横に置いて、純粋に「今の生活に必要かどうか」で判断することが大切です。
ジャンルごとに片付ける場所を決める
ジャンルごとに片付ける場所を決めることで、物の居場所が明確になり、散らからない仕組みができあがります。使う場所の近くに配置するという基本原則を守ることが重要です。
- 化粧品は洗面台の近く
- 調理器具はキッチンの手の届く範囲
- 仕事道具は作業デスクの周辺
- 掃除用具は各部屋の近く
- 薬は洗面所やキッチンなど水回りの近く
使用頻度に応じた配置も考慮しましょう。毎日使う物は手の届きやすい場所に、たまにしか使わない物は高い場所や奥に収納します。
例えば、文房具なら「毎日使うペンは机の上のペン立て」「たまに使うホッチキスは引き出しの中」「年に数回使う封筒は棚の奥」というように、使用頻度で住み分けを明確にしてください。
場所を区切る
場所を区切ることで、物の混在を防ぎ、整理整頓を維持しやすくなります。引き出しや棚の中を仕切ることで、各アイテムの定位置が明確になります。
- 引き出し用の仕切りケースを活用
- 小さな箱や缶を仕切りとして使用
- ラベルを貼って何を入れるか明示
- 色別やサイズ別で区分
- 使用頻度別にエリア分け
「ワンアクションで取り出せる」配置を心がけてください。何かをどかさないと取り出せない状態では、片付けが続きません。
10分だけ始める
10分だけ始めることで、心理的なハードルを下げて行動に移しやすくします。「完璧に片付けよう」と思うと負担に感じますが、短時間なら気軽に取り組めるでしょう。
- タイマーをセットして時間を区切る
- 1つのエリアに集中する
- 捨てる・しまう・移動するの3つに分ける
- BGMをかけて楽しみながら行う
- 終わったら自分を褒める
毎日10分の積み重ねが、大きな変化を生み出します。1週間続けると70分、1ヶ月で約5時間の片付け時間になり、部屋の状態は確実に改善されます。
例えば、「朝起きてから10分」「夜寝る前に10分」など、生活リズムに組み込むことで習慣化しやすくなります。短時間でも継続することで、自然と片付けスキルが向上し、効率も上がっていくでしょう。
まとめ
片付けられない状態が続く場合、ADHDやASD、強迫性障害、うつ病、認知症などの病気が関係している可能性もありますが、多くの場合は適切な方法を学ぶことで改善できます。
今回紹介した、片付けられる人になるための5つのステップを実践することで、持続可能な片付けスキルが身につきます。無理をせず、10分という短時間から始めて、段階的に習慣化していくことが成功の秘訣です。
ただし、もし気になる症状がある場合は、自己判断せずに専門医に相談してください。適切なサポートを受けることで、より効果的な改善が期待できます。一人で悩まず、今日から小さな一歩を踏み出してみましょう。
もし、より本格的な片付けのコツが知りたいという場合は、『元小学校の先生が教える いちばんやさしい 片づけの授業』という書籍をご確認ください。
フォロワー21万人の人気整理収納アドバイザーが、誰でも簡単に実践できる片付けのノウハウを、余すこと無く解説しています。きれいな部屋を手に入れて、身も心もリラックスしたいと考えている方は、ぜひ書籍を手に取ってみてください。