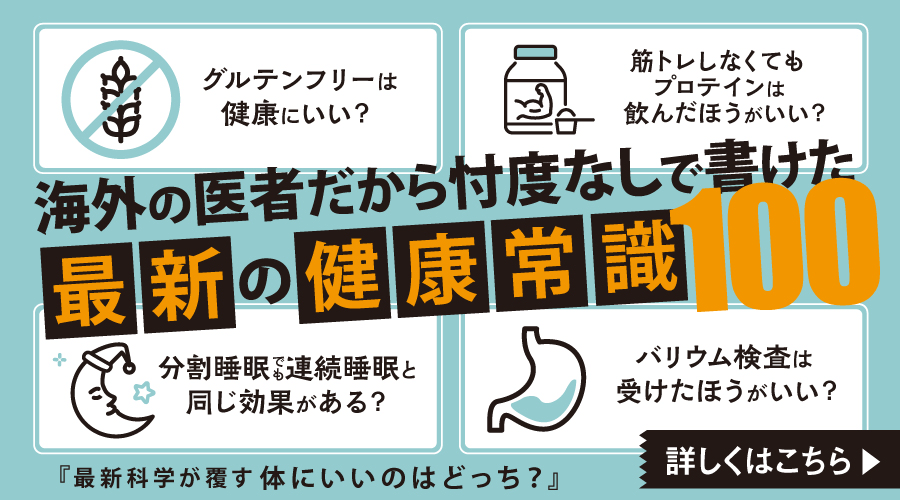連載エッセイ「あの本とカフェへ。」
「唐揚げにレモン、かけますか?」 これは、かの有名なドラマ「カルテット」の名ゼリフだ。 満島ひかり演じるすずめちゃんと、松田龍平演じる別府さんが、テーブルに並んだ揚げたての唐揚げに添えられたレモンを手に取り、同席したルームシェアメイトに断りもなく、「おいしそう~!」と、唐揚げにじゅわーっとレモンを絞る。 その行為について小競り合いが繰り広げられる光景は、「カルテット」のファンなら忘れられないシーンのひとつだ。 高橋一生演じる家森が「いま君たち、なんで唐揚げにレモンしたの?」と問いただすと、「え、なんで?唐揚げはレモン。」と返すすずめちゃんに、食い気味に「人それぞれ」と語気を強めて返す家森。 すずめちゃんが「レモンぐらいで怒らなくていいじゃないか」と返すと、松たか子演じる巻真紀が「レモンくらいってことはないと思うんですが」とボソッとつぶやき、意見は真っ二つに分かれる。 この一連のシーンはコミカルで、観る側はただ笑っていられるシーンにも関わらず、のちのち重要な場面で例えに引き出されることで、視聴者がより忘れられなくなる作用があるのだけど、その話はまた別の機会にしておこう。 なにが言いたいのかというと、食のこだわりは人それぞれ、千差万別だ。それに関しては、いいわるいも存在しない。好きなように食べればいいのだ、と思う。 余談だが、わたしはスパイスカレーにハマっていた時期があり、レシピを頭に叩き込むために毎日1週間カレーを作り続けたことがある。 単純に美味しいから毎日食べたいと思っての行動だったが、いつも料理には一言も文句を言うことのない夫から「さすがにカレー続きすぎじゃない?」と言われ、われに返った。 食のこだわりに関しては寛容になれる自分だけれども、食卓に並ぶまでの過程には、しばらく変なこだわりがあった。 それは、「レシピ通りにちゃんと作らねば」という呪いのようなもの。 恥ずかしい話、29歳で結婚するまでは実家暮らしでほとんど料理しなかった。アパレルの店長をやっていて、毎日長時間の重労働に加え、休みの日もなにかあれば対応に追われる始末。 追われている中で、なにかを生み出す気力はゼロに近かった。 当時付き合っていた彼(現在の夫)が、よくある20代の一人暮らしの男性らしい、不健康な食生活を送っていたのを目の当たりにし、見るに見かねて手料理をふるまうようになった。 彼が食べたわたしの初の手料理はゴーヤチャンプルだったそう。 自分ですら忘れていた記憶をなぜ覚えているのかと聞くと、ふだん全く料理をしないわたしを知っている妹にその話をしたところ、「え、あいつが料理を…⁈」とひどく驚かれたからだという。なんと失礼な。 まずい料理だったら愛想をつかされてしまう、という恐怖が大きくて、自炊からできるだけ遠い位置にいたかった。 それに、どうも家庭料理はレシピ至上主義というか、レシピ通りに作らねば料理とは呼べないという謎のこだわり……誤解を恐れずに言えば、わたし個人が持つ偏見のようなものがあった。 「料理、つらい。」 そうこぼしたところで誰も助けてはくれない。 なぜかと言えば、恥ずかしくて誰にも助けを求められなかったから。 料理教えて、なんて言えない。ましてや料理教室に通うなんてハードルが高すぎる。「そんな包丁の持ち方じゃダメ!」とか、怒られまくるんだろうな、と。自分の苦手な領域と向き合うドM根性は、その当時の自分にはなかった。(いまも無いかも) 「作るなら、ちゃんと作らねば」という妙な思い込みで、ずいぶん苦しめられた。 それを少しずつ解放してくれたのが、当時人気ブロガーだった野菜料理家の庄司いずみさん。庄司さんの料理は野菜をメインに使ったシンプル料理。 トマトを丸ごと使った滋味深いトマトスープは何度も作った。作る工程も調味料もシンプルで、野菜から出る水分がごちそうになると知ったわたしは、無水料理に夢中になった。 「頑張らなくても、なんとかなるかも」 味噌汁を作るなら、昆布と鰹節できちんと出汁をとるところから料理本のレシピが始まるものがほとんどだった頃。そんな気力がない人でも作りたくなるきっかけを与えてくれた庄司さんには今でも感謝している。 レシピ至上主義に思えた家庭料理の概念をぶち壊してくれたのは、あの土井先生だった。 料理研究家の土井善晴先生は、「料理と利他」(中島岳志さんとの共著・ミシマ社)の中でこう言う。 日本がレシピ至上主義になった背景は?との質問への回答から一部を紹介すると、 “日本人ってそれまでレシピないんですよ。ないところにあとから入ってきたものなのですが、ところが、今は日本人のほうがレシピに執着しているんですね。ヨーロッパの人は誰もそんなことしてないんです。” 引用:「料理と利他 / 土井善晴・中島岳志」ミシマ社 より 土井先生によれば、レシピ至上主義のはじまりは、栄養管理のために「正確に計量する科学」が発端かもしれないと説く。 確かに栄養は大事。でも、プロでない自分が果たして毎日の家庭料理でレシピ通りに作る必要があるのだろうか。 「家庭料理の味噌汁は出汁を取らなくてもよい、入れる具材から旨みが取れるもの。時間がなければお湯に味噌といただけでもええ。」と、土井先生は事あるごとに教えてくれる。 思わず「ええんですか、それで」と聞き返してしまいたくなるけれど、ええんです。実際に作ってみれば分かる。 毎日食べる家庭料理に、ハレの日のごちそうを作るレシピはそぐわない。わたしたちが無意識に求めている家庭料理は、実は「ごちそう」なのだ。ほんとうはもっとシンプルでいい。むしろ、それこそが心と体に染み渡るごちそうなのかもしれないと、初めて思った。 過去のわたしのように、理論詰めのようなレシピ本ばかりを読んで、自炊のハードルが上がり、にっちもさっちもいかなくなっている人におすすめしたいのが「カレンの台所」(滝沢カレン著・サンクチュアリ出版)。 一読し、素直な感想を言えば「よく、この本出したな…」と。 冒険が過ぎる。 人気タレントの滝沢カレンさんが、Instagramで発信する文体をそのままレシピにした作品。 通常のレシピの主役は、言うまでもなく作る人なわけで、文章の中で主語が省略されていたって、作る人が主語なのが当たり前なのであって。例えば、「野菜の下ごしらえをします」という文章に省略されているのは、「わたし」という存在。 だけど、カレンさんのレシピでは、説明もなく主語が切り替わる。その主語は、作り手のわたしたちではなくて、材料たちになることもしばしば。 例えば、肉じゃがはこうだ。 “ 茶色い模様がつき始めたら、牛肉を失礼しますと隙間に入れて炒めます。 足元は少し浸かっていただき、飽きさせないように景色を変えます。 もうこれ以上休憩されちゃ困ります、と思う度合いでアルミホイルをめくります。 引用:「カレンの台所 / 滝沢カレン」サンクチュアリ出版” 料理する人だけではなく、材料の目線になるところが最大の特徴であり、10万部(2020年12月時点)も売れる理由のひとつであることは間違いない。 調理される材料たちを主語にするからこそ生まれるファンタジーの世界。この本が、超感覚派のレシピと言われる所以がここに。 だって、煮詰まるピーマンを見て、「気持ち良さそうだな」なんて思わないじゃないですか。「色、変わってきたな」くらいで。 この観点は新しい。 それに、なんといっても食材に対する愛が感じられるのが良い。 スーパーに行けば、旬という概念を忘れるくらい、なんでも揃っている現代。ワンコインで一通りのメニューを選べちゃうような時代で、食材への感謝はいつだって忘れ去られる。 わたしたちの体を作ってくれる食材に対する、ありあまるほどの敬意が、このレシピには隠れているように思えてならない。 「カレンの台所」には、通常のレシピ本には必ず書いてある分量が明確に書かれていない。 あくまでも物語の中で、いくつかの材料が主人公となって登場し、たまに作り手が主役を奪いながら、いつのまにか料理が完成されている。 頭の中で想像してごはんを作る疑似体験をさせてくれる作品。「ごはん、作らなきゃなぁ…」という消極的な気持ちから自炊するよりも、「作ってみたい!」と思って作る方がきっと好みの味に近づける。食材だって喜ぶはずだ。 この本を読むのなら、浅草橋の〈Ome Farm Kitchen〉がいいかもしれない。連載タイトル「あの本とカフェへ。」第2回目にしてカフェではなくキッチンを紹介してしまうけれど、それだけ感激した店なので多目に見てほしい。 遅めのランチタイムに訪れて、無農薬の野菜をふんだんに使ったメニューを待ちながら、ひとつのレシピで繰り広げられる食材の物語にふれる。 神田川にかかる浅草橋(ほんとうに「浅草橋」という橋があるんですよ)を眺めながら、カウンターに座る。 小さなキッチンでテキパキと無駄なくオーダーをこなし、下ごしらえまで進めるシェフの様子をひそかに盗み見て、手際の良さにうっとりとする。 〈Ome Farm Kitchen〉の気さくなシェフが話す、青梅市にある自分たちの農園で採れた無農薬を中心とした野菜のことや、目黒川沿いで作られた非加熱のはちみつのストーリーを聞いて、食材への愛を慮る。 メインメニューと一緒にオーダーしてほしいスープ。今日は「品川かぶのポタージュ」だ。 かぶのほっくりとした優しい甘みで、緊張してた体がするすると解放される。とろとろのポタージュが心をほどいてくれるよう。 ポタージュをしみじみと味わっていると、目の前には畑が広がっていた。 〈Ome Farm Kitchen〉のブッダボウルはとにかくカラフル。それぞれの野菜がぴかぴかと光っていて、うっとりとしばらく眺めてしまう。 「今日のお野菜は沖縄の島人参のグリル、ケールと菜の花のオイル蒸しにバルサミコと生ハチミツの人参マリネ、コリアンダーの根っこの素揚げ…」とひとつひとつ説明してくれるシェフ。 その時々で野菜は変わるから、〈Ome Farm Kitchen〉のブッダボウルは一期一会のメニューだ。コリアンダー(パクチー)の根っこがこんなに甘くて美味しいなんて。 「根っこは栄養素が高くて、旨みもつまっているんですよ。だからびっくりするくらい甘くて。」と話すシェフ。 たっぷりの野菜の下にはジェノバソースのまぜごはんが。こちらは品川かぶの葉っぱとチャービルというハーブを使ったソース。調理で余ってしまうかぶの葉っぱを使っているのだとか。 スプーンでひとくち掬えば、食べ終わるのが惜しくなること間違いなし。 心のこもった料理に触れると、なんだか自分でも作りたくなってくるはずだ。 いつもなら面倒くさくて作りたくないけれど、今日は唐揚げでも作ってみようかな。 レモンをかけるかどうかは、応相談で。 ■Ome Farm Kitchen 著者:チヒロ(かもめと街) この記事は、「カレンの台所」の新刊コラムです。
大人気Webマガジン「かもめと街」を運営する、街歩きエッセイストのチヒロがサンクチュアリ出版の本を持ってお気に入りのカフェを巡ります。


 唐揚げの物語もすごい。
唐揚げの物語もすごい。


 ポタージュにはビオラの花を添えて。
ポタージュにはビオラの花を添えて。
住所:東京都台東区浅草橋1-1-10-2F
公式サイト:
https://www.omefarm.jp
公式Instagram:
https://www.instagram.com/omefarmkitchen/
かもめと街
https://kamometomachi.com
Twitter:
@kamometomachi

カレンの台所
滝沢カレン(著)
1400円+税
![]()
言葉の魔術師・滝沢カレンが綴る、人類未体験の新感覚レシピ文学!