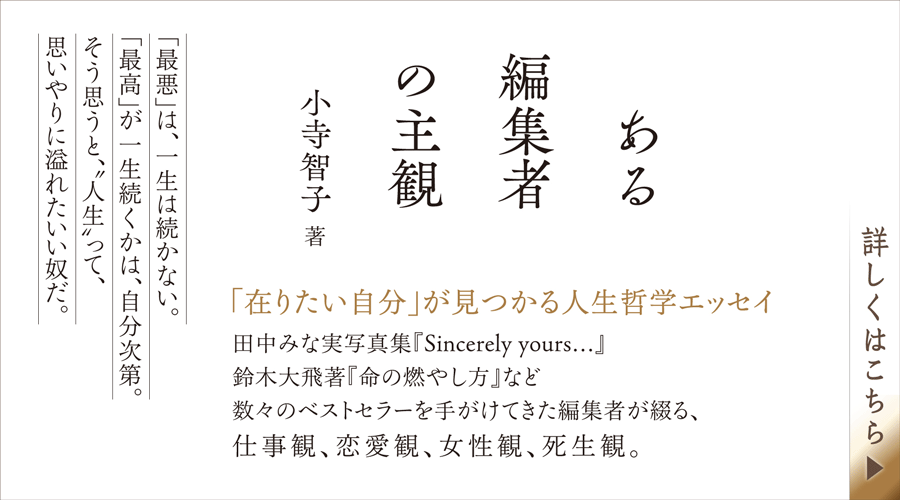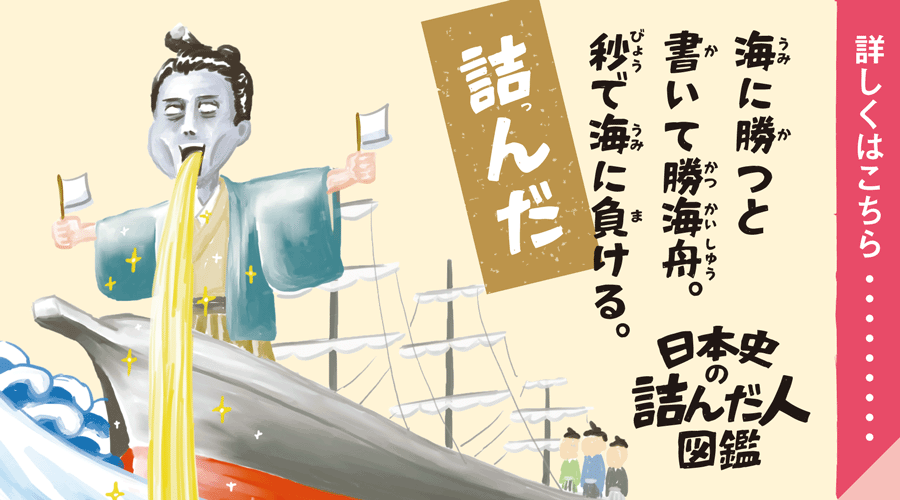メルマガ、Facebook、YouTubeなどで精力的にアウトプットを行い、多くの著作も持つ精神科医の樺沢紫苑さん。映画『ドグラ・マグラ』を見たことが今の道に進む決定打となったという。ビジネス書の大家が溢れんばかりのノウハウをいかに獲得したか、そのルーツに迫る。
目次 1965年、北海道札幌市生まれ。少年時代は「アメリカに憧れる」映画少年だった。テレビの映画番組はすべて視聴。ビデオデッキのない時代に、年間200本以上の映画を見ていたという。 「映画ばっかり見ていましたね。高校生になると映画館にも通うようになりました。特に好きだったのはウディ・アレン。彼はユダヤ人なので、映画の中にユダヤネタが入るんですよね。そこで、『ユダヤ人って何だろう?』と疑問を持ち、中学時代からアメリカの文化や歴史、差別、宗教などについて調べたりもしていました」 大学では医学部に入学。当初は「医師としての一般的なコース」として内科医を目指していた。しかし、研修医として経験を積む中で、そのコースに疑問を抱くようになる。 「大学病院にはカンファレンス、症例検討会というものがあります。この患者さんはこんな症状で、検査の結果はこうで、レントゲンはこうで、治療方針はこうで……と主治医がプレゼンし、質問を受けたりしながら話を進めていくのですが、私には検査データしか見ていないように思えたんです。患者さん自身の考えや、どんな人なのかはまったく関係なく話が進んでいる。人間不在というか」 治療の現場も同様のように思えた。「人間」よりも「病気」と向き合い、その人がどんなふうに苦しんでいるかは見ようとしない。「これが自分のやりたいことなのだろうか」と自問すると、否という答えを出さざるを得なかった。そんなとき、研修で精神科をまわる番がきました。 「精神科は予診といって、診察の前に1時間以上かけて患者さんの話を聞くんです。子どもの頃のエピソードから、家族構成、出身学校など、生い立ちを詳しく聞いていく。人間のバックグラウンドを見ないと、症状は理解できないということですね」 この研修の経験で精神医学のおもしろさに気づくも、当時はまだ「精神科=変わっている」というイメージが根強く、簡単に進路を変える決断はできなかった。内科と精神科、どちらのコースを選ぶか迷っていたが、ちょうどそのときに上映されていた夢野久作原作の映画『ドグラ・マグラ』を見たことが人生の決定打となった。 「ざっくりいうと、記憶喪失の青年がいて、隔離室に入っているんだけど、なんでそこにいるのかわからない。それを精神科医が問診することで、次第に過去を思い出し、少しずつ彼のしたことがわかってくる、というストーリーです。精神医学というものが、イメージとしてとてもわかりやすく描かれていました。思い起こしてみれば、自分が少年時代から親しんできた映画も、精神世界を描いているものがけっこう多いんですよね。これは『一生かけてやっていくのにふさわしい世界だ』と確信し、精神科医になることを決めました」 勤務医として医師のキャリアをスタートし、道内各所の病院を転々とした。最初の3年間は、「道北地区で最も忙しい」と言われる旭川の病院に勤務。「ありえないぐらい患者さんが来る」日々を過ごす中で、自身の体に異変を感じる。1993年の冬のことだった。 「ある日突然、耳鳴りがしたんです。マイナス10度と寒い日だったので、『寒さのせいかな?』と放っておいたのですが、2〜3日したら悪化。最終的には音が耳の中で反響するようになってしまい、仕事に支障が出始めました。あわてて耳鼻科で診てもらったら、蝸牛リンパ水腫と診断されました。いわゆる突発性難聴と似た病気で、先生に聞いたら『ストレスです』と」 この経験をきっかけに、働き方を見直すことに。それまでは、どちらかというと寝食を忘れて仕事に没頭する「熱血医師」だったのだが、その姿勢を改めた。「自分がもっとやりたいことをやろう」と決め、緩急をつけて仕事に取り組み、空いた時間は「自分のために」使うようになった。また、自身が病を得たこの機会は、「健康」について初めて意識したタイミングでもあったという。 「若いと平気で徹夜もできますし、健康というのは、失わないとそのありがたみに気づくことはできません。この早いタイミングで意識できたのは、ある意味でよかったと思います」 その後、医学博士を取得するべく、大学に戻って研究にも従事。勤務医としての仕事を終え、夕方の5時から深夜0時まで研究に没頭する日々が続いた。そして、無事に博士号を取得し、次なる道としてアメリカ留学を志す。 「子どもの頃からアメリカへの憧れがあったので、一度は住んでみたいと思っていました。本当はすぐにでも留学したかったのですが、病院の人手が足りず、3〜4年待ち続けて。ようやく行けたのが2004年、39歳のときです」 なお、「待たされた」アメリカ留学までに、気づけば10以上の病院に勤務。大学病院、公立病院、個人病院など、あらゆる医院で研鑽を積んだ。 「認知症、アルコール依存症、うつ病、統合失調症など、あらゆる疾患を相当な数見てきましたが、そういう経験をしている医者はなかなかいません。今、YouTubeで何を聞かれても答えられるのは、このときに一生懸命勉強したのが生きているんだと思います」 留学が決定したエピソードも劇的だ。留学の前年、アメリカで行われる世界最大の脳科学の学会に、樺沢さんは教授に同行。教授が知り合いだというインド人とたまたますれ違った際、「こいつの留学先探してるんだけど、空いてない?」と聞いたところ、彼は「空いてるよ」と即答。なんと、彼はうつ病研究では屈指の存在であるイリノイ大学の教授であった。 アメリカの大学は完全な「ノルマ主義」。決められた期間中に結果を出せないと、「このままだと帰ってもらうことになるぞ」と脅しがかかる。人の入れ替わりもとても激しく、しばらくすると「自分が空きに入れてもらえたのも、入れ替わりが激しかったから」だと気づいたという。 なお、3年間の留学生活では、最先端の脳科学だけではなく、「アメリカのワークスタイル」を目の当たりにした。 「アメリカは多くが9時から5時で、ほとんどの人が6時には帰る。7時過ぎまでいるのは10人いたら3人ぐらい。とにかくみんな、集中して仕事をする。もちろん、実験がうまくいかなければ早く来たり、遅くまで残ったりするけど、うまくいっていれば早く帰っても何もいわれません。ノルマ主義のよさですね」 空いた時間を利用して、「映画は月15本ぐらい見ていた」。アメリカ文化に憧れていただけあって、公開したての映画をすぐに、しかも浴びるように見ることができるというのは、夢のような環境だ。そして、いつしか「ただ映画を“見る”だけではもったいない」と感じるようになっていく。 アメリカ流のメリハリの効いたワークスタイルのおかげで、時間はふんだんにあった。そこで、見た映画の感想をまとめて、発信していくことにした。当時はブログもなく、発信をするなら自作のホームページで、という時代。ホームページ制作のノウハウは持っていたものの、ネットの状況は「記事をアップしてから、検索エンジンに載るまで1〜3カ月かかる」というもの。これでは、せっかく封切り直後の映画について書いても、タイムラグが生じてしまう。 そのとき、流行の兆しを見せていたのが「メルマガ」だった。 「『まぐまぐ』とかが盛り上がって、第1次メルマガブームですよね。当時、私は日本から雑誌などを送ってもらっていたのですがそれでは足りず、日本語渇望症になっていた。そのときに、日本語で情報が得られるものとして、メルマガというものを知りました。渡米してすぐに10から20ぐらいのメルマガを登録したのですが、読んでいるうちに、『あ、これなら俺にも書けるな』と(笑)」 2004年7月、メルマガ「シカゴ発 映画の精神医学」を発刊。週2回発行で、アメリカで公開されたばかりの映画を次々に紹介した。メルマガのいいところは「今日配信したら、今日読んでもらえる」点。他にはない、現地の最新映画情報が得られるコンテンツは多くの読者を惹きつけ、最終的に、5万人の読者を抱える優良メルマガへと成長した。 プライベートも充実させつつ、厳しい環境の中で3年間学んだ樺沢さんは、教授から慰留されつつも帰国を決意。帰国後の身の振り方を考え、自身の精神科医としてのあり方を突き詰めていく。 「アメリカで勤めていた研究所は、自殺した方の脳のサンプルをたくさん持っていました。その脳にどういうタンパク質が存在して、どういう遺伝子変異が起こったのか、といったことを一つひとつ調べていく。ひとつのタンパク質を調べ上げるのに数カ月かかるような、気が遠くなるような作業です。これが治療に生かされるようになるには極めてうまくいっても15年はかかるわけで、私には『こんなことやっていても、患者さんのためにはならないのではないか』と思えてなりませんでした。無駄とはいわないし、誰かがやらなくてはならないのだけれど」 15年後の人ではなく、今苦しんでいる人、自殺しそうになっている人を救いたい……そこで樺沢さんが着目したのが「予防」だった。 「『こういうことをするとうつになりやすい、自殺に至りやすい』といった情報や知識をみなさんに知ってもらうことで、だいぶ変わっていくのではないかと。当時は、そういった情報はまったく世に出てなかったし、むしろタブー視されていた。インターネットで検索する人もまだ少なかったように思います」 アメリカ留学時代から、その布石は打っていた。実はメルマガ「シカゴ発 映画の精神医学」も、最新映画を題材にしながら、そこに描かれている心理世界、精神世界をわかりやすく論じることで、メンタル疾患に悩む人を少しでも減らそうという狙いがあったのだ。 「『予防しよう』とストレートに書いても誰も読みません。健康法の本もそうで、健康に関心のある人、つまり、もともと健康に詳しい人しか読まない。本当に必要な人は問題意識もないから、そもそも健康法の本を買ったりしません。でも、映画好きに向けたメルマガなら、映画にかこつけて読ませることができる。いわば、変化球ですね」 この「変化球」の手法は、作家となった今も踏襲している。それぞれの著作のあとがきを読めばわかるが、ビジネス書であっても、根底にあるのは「健康に役立ててほしい」という想いだ。 「基本的に私が書いているのは、『この通りやっていけば健康になれる』という内容。読んでいる人は気づきにくいかもしれませんが、働き方やビジネススキルのノウハウを身につけることで、メンタル疾患になる人が減ってほしいと思って書いています」 アメリカで執筆し、大成功を収めたメルマガ「シカゴ発 映画の精神医学」。しかし、実はこれ以前にも彼はずっと情報発信を繰り返してきた。いってみれば、彼の半生は「アウトプット人生」そのものだ。 「アウトプットというものを初めて意識したのは、『月曜ロードショー』の解説をしていた荻昌弘さんです。特徴的なことはないけれど、優しい口調で、正論をわかりやすくいってくれる。彼の解説をカセットに録音し、文字に書き起こしたこともあります。小学6年生のときです。どういう論点で解説が構築されているのか、分析するんです。思えば、私のアウトプット人生はここから始まりました」 映画評論家への憧れは強く、大学時代は『キネマ旬報』に投稿して常連のように掲載され、映画の同人誌にも参加していたという。 一方、インターネットのホームページとの出会いは1998年。富良野の病院に着任した初日、院長の部屋へあいさつに行くと、パソコンの画面を見せられた。 「『君、これを見なさい。うちの病院のホームページだけど、私がつくったんだよ。君もなんかつくってみれば?』と。帰ってから、北海道でホームページを持っている病院を調べてみたら、20ぐらいしかない。精神科だと2つぐらいでした。最先端ですよね」 次の週末、当時、Windows98に標準搭載されていた「FrontPage98」というソフトを使い、さっそくホームページ制作に没頭。それまで書きためていた「スター・ウォーズ」に関する記事を活用し、1日かけて10ページ程度の自作ホームページが完成。「ホームページっておもしろいな」と実感する。 その数年後、デジカメが安価で出回るように。樺沢さんもさっそく入手し、好きで食べ歩いていたカレーを撮りためていく。そのうち、「自分だけで見ていてもつまらないからシェアしよう」と、日記のような意味合いも込めてカレーのホームページを立ち上げる。そして、これが2004年に、札幌に一大スープカレーブームを巻き起こすことになる。 「『誰も読まなくてもいいから』という気持ちでいたのですが、案の定、誰も読んでくれない(笑)。それなら毒舌で書いてやろうと、何も気にせずガンガン書いていたら、『それがおもしろい』と人気になったんです。多いときで、1日に3000PVはありました。3000というとあまり多くないように思われるかもしれませんが、ほぼ札幌限定ですからね。1%の人がお店に行ったとしても30人ですから、私が紹介した次の日には行列ができているということもありました」 きっかけはひとつの個人ホームページに過ぎない。しかし、そこから本の出版、テレビ局からの取材と、あれよあれよという間につながっていく。「インターネットってすごいな」と思った瞬間だった。 「医者はたいてい、論文作成などのためにパソコンを持っているので、スキルはありました。普通だったら、ホームページをつくろうと思っても技術的な壁があるものですが、その点はラッキーだったと思います。さらにさかのぼると、高校時代は無線部だったです。なので機械には強い。もともと好きなこと、適性があったんでしょうね」 帰国後は、作家を本業とすることに。現在は、月に数回程度、医師として病院にも勤務しながら、「日本一、情報発信する精神科医」として精力的に活動。メルマガ、Facebook、YouTubeでの発信を定期的に続け、年3冊のペースで書籍を発行している。その一方で、月10本以上の映画鑑賞、月20冊以上の読書も欠かさない。 1冊の本が出版されるまでの流れは、当初は自分で企画書を書き、それを出版社に提案していたが、今はそのスタイルを改めたという。 「どうも、私は早過ぎるようで(笑)。2016年に出した『脳を最適化すると能力は2倍になる』(文響社)という本は5万部売れたのですが、実はこれ、2010年に出した『脳内物質仕事術』(マガジンハウス)とほとんど同じ内容なんです。『脳内物質』という言葉を初めてタイトルに使った本でしたが、あまり売れませんでした。いまでこそ脳科学ブームですが、当時は先取りし過ぎていたんでしょう。私としては、ようやく時代が追いついてきたという感じです」 同様のケースをいくつか経験し、「自分からは企画を出さず、編集者から提案されたものをやろう」というスタンスに。 「出さないだけで、文章化した企画は何十個もストックしています。その中にあるアイデアを編集者さんが持ってきたら、時代としても求められているということ。『では一緒にやりましょう』という流れになります。『よく気づいたね』と(笑)」 2018年8月には28冊目の著作となる『学びを結果に変える アウトプット大全』(サンクチュアリ出版)を出版。 「これも編集者さんのご提案に乗った形です。アウトプットのことを書きたいという構想はありました。2015年に出して15万部売れた『読んだら忘れない読書術』(サンマーク出版)も、考えてみたらアウトプットの本ですが、もしタイトルを『アウトプット読書術』にしたら売れなかったと思います。今は、小学校でアクティブラーニングが導入されたり、学校の授業にディベートを取り入れたり、アウトプットという言葉こそ使わなくても、世の中全体がそういった方向へ向かっていますよね。自分は、一貫してアウトプットの重要性を伝えてきましたが、ようやく時代がマッチしてきたなというのが実感です」 『アウトプット大全』は図解も豊富で、樺沢さんも「今までの私の本の中でいちばんわかりやすい」と胸を張る。出版に際して行われた500人が集まったセミナーも大盛況だった。 「私の集大成となる本。ビジネス書50冊以上の内容が入っているといっても過言ではないでしょう。ビジネスマンが抱えている悩みの90%くらいをフォローできると思います」 さて、作家としての今後を問うと、「精神科医らしい本を世に問おうと思っている」という回答。 「集大成となる本も出しましたし、時間術や仕事術に関しては一通り書いたので、当面、ビジネス書はもういいかなと。これからは予防医学をベースにしつつ、もっと、心の問題や生き方に沿った本を書いていきたいですね。それも、20代、できれば10代といった若い世代に伝えていきたい。若い頃からそういった知識があれば、人生は相当変わります」 YouTubeはもちろん、4コマ漫画も駆使するなど、若い人にリーチする取り組みも積極的に行っている。 「将来を悲観する若者は多いですが、これからは技術が飛躍的に進歩していくので、既成の価値観は通用しなくなる。有史以来、チャンスが最も多い時代なのに、みんな気づいていません。だからこそ、自分が何をすればいいのかを探るために、自分磨きをしていくことが重要なのです。インプットとアウトプットをし続けることで、自分の方向性に気づけるはずです」 (取材・文/中田千秋、写真/サンクチュアリ出版 大川美帆)年間200本以上の映画を鑑賞、特に好きだったのはウディ・アレン
精神科医の道を選ぶきっかけとなった『ドグラ・マグラ』
アメリカ式のワークスタイルを目の当たりにした留学生活
5万人の読者を獲得したメルマガ「シカゴ発 映画の精神医学」
スープカレーブームの火付け役となり、インターネットのすごさを実感
「アウトプット人生」に、ようやく時代が追いついてきた
チャンスの多い時代だからこそ、インプットとアウトプットが重要




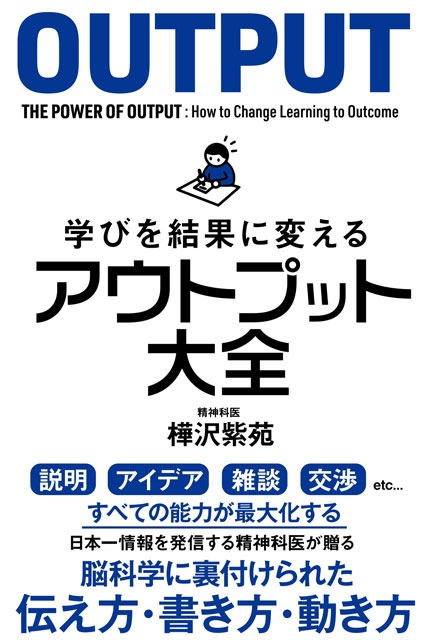
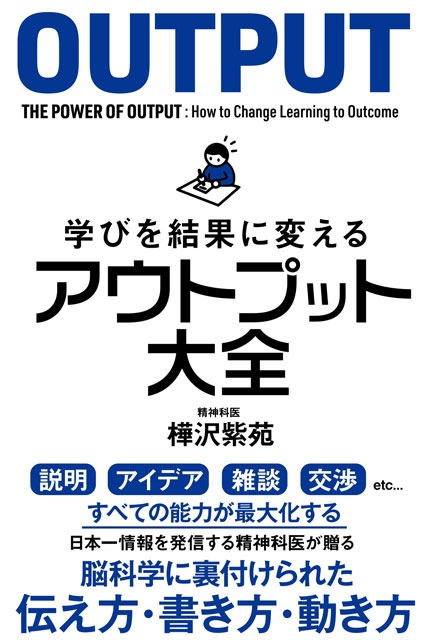
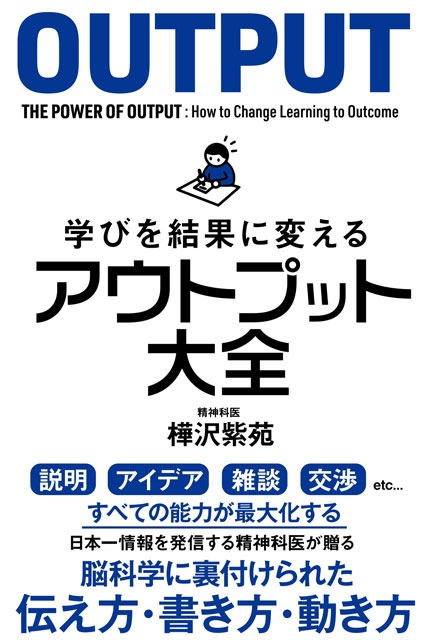
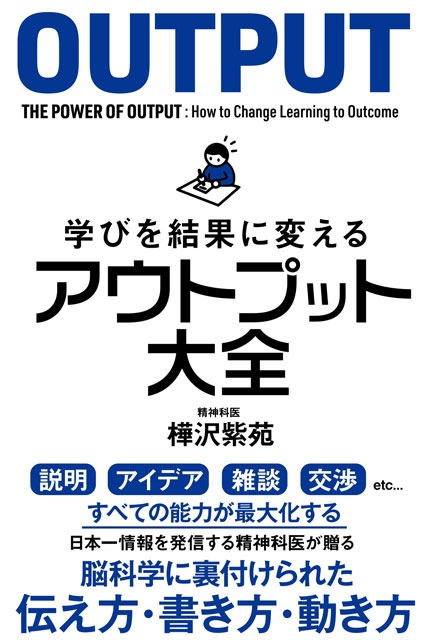
学びを結果に変えるアウトプット大全
樺沢紫苑(著)
定価:1,600円(税込1,760円)
![]()
![]()
![]()
![]()
説明・アイデア・雑談・交渉など……すべての能力が最大化する。