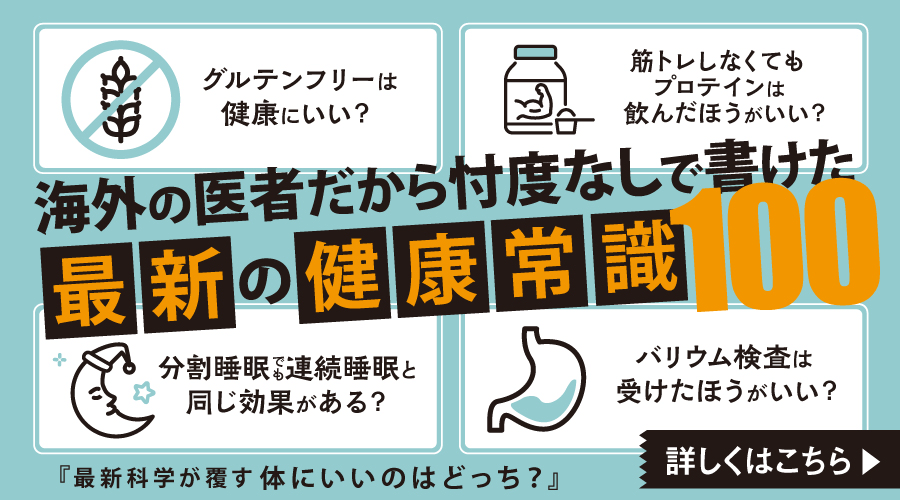「食べたら運が良くなる」と話題の、大阪府枚方市楠葉の「御食事ゆにわ」。連日、開運を求めるお客が後を絶たないが、その中心にいるのが、店長の“開運料理人”ちこさん。彼女がいま、笑顔を絶やさずにいられるのは、まさに“食”の力のおかげだ。
目次 大阪府枚方市に生まれ育ったちこさん。幼少時代は、とても“インドア”な子どもだったという。 「家では、寝るか、着せかえ人形で遊んでいるか、テレビを見ているか。あまりにも静かすぎて、いることに親が気づかないぐらい(笑)」 外に遊びに行くよりも、家で静かに過ごすのが好き——そんな少女にとって、料理はとても身近なものだった。料理をする母親の姿を見るのは、生活の一部。「今日のごはん何?」と母親に聞く瞬間が、1日の中でいちばんの楽しみだったという。 ごはんを待ち遠しく思うのには、ある理由があった。ちこさんの家には、「おやつを食べる」という習慣がなかったのだ。既製品のお菓子は、親戚の家に行った時などに食べることができる“特別”なもの。小学校に入学して、友達の家に遊びに行くと大量のおやつが出てくる光景に、とても驚いたという。 「家でおやつを食べる時は、ホットケーキなど、イチから作るものばかりでした。ある時、チョコレートがどうしても食べたくなって。『ココアってチョコレートと似てるなぁ』と思って、ココアと牛乳をひたすら混ぜ合わせたことがありましたが、全然チョコじゃない、よくわからないものができました(笑)」 おやつ問題(?)で培われた“ないなら作る”という姿勢は、食に限らず発揮された。小学校高学年の頃から、「既製品を買うより、生地を買って作った方が安い」という母親のアドバイスを受け、洋服を自作。オシャレしたい少女が抱く「キリがない物欲」に対処していた。 「雑誌で見て気に入った洋服と、似たような生地を買ってくるんです。そして、自分のスカートの寸法を測って、それを型紙にして縫う。みんなから『オシャレだね』って言われてうれしかったけど、自分で作っていたことは言いませんでした。みんなは買ってもらえていたから、恥ずかしくて」 実は小学生の頃、“インドア”から“アウトドア”へと気質が転換する出来事があった。きっかけは、小1の頃に引っ越したこと。転校先の学校ではなかなか友達ができず、「静かに待っていても、誰も何もしてくれないんだ」ということに気づく。 そんな時、クラスメイトが「あの子、暗いよね」と自分について話しているのが聞こえてきた。 「その一言が、自分の中にすごく入ってきて。『私って暗いんだ?』と、初めて人からどう見られているのかを知ったんです」 この一件で危機感を抱いた“暗い”少女は、現状を打破するべく、まずはクラスの人気者と仲良くなった。彼女と過ごすうちに、かわいいだけではなく、元気になるし、楽しいし、面白いということに気がつく。そして、自分に足りないものを意識するようになった。 そこからは一変。友達にも恵まれ、4年生の頃になると、クラスでいちばん目立つグループに入って、いつでも「話の中心」にいるようになった。また、小学校高学年の頃にはSPEEDが、中学生の頃はモーニング娘。が流行。自分と1〜2歳しか違わない子が歌ったり、踊ったりしているのを見て、「“自分を表現する”というのは、大人になるまで待ってからやることではない」という気づきを得る。 中学校に入っても、勢いはそのまま。変わらずに「クラスの中心」にいた。でも、ちこさんにはひとつ弱点があった。それは「運動が苦手」だということ。 そこで、ちこさんはバスケットボール部に入部。小学生の頃、人気者の振る舞いを観察して良いところを取り入れたように、「運動が上手い人のセンスや感覚」を、厳しい環境にあえて身を置くことで習得しようとしたのだ。当然、「人よりも劣っているから、努力をしなくてはならない」。朝早く起きて走り、練習や体力作りに打ち込む日々を送った。 早々とコツをつかみ、みるみる上達したちこさん。がんばっている姿を見た先輩には目をかけられ、違う部活の人とも仲良くなれた。 「一度誰かに認められれば、さらに多くの人に認められることにつながると知りました。この頃は完全に“がんばることは素晴らしい、結果が全て”という考えでしたね」 この経験はちこさんに大きな自信を与えてくれたが、同時に、危うさもはらんでいた。“多くの人に認められてうれしい”が、いつしか“認められなければならない”に変わり、少しずつ窮屈になっていくのだが、このことに気づくのはまだ先のことだ。 高校受験では、バスケでの指定校推薦の話もあったが、「もっと違う世界が見たい」ために断った。学力的にはもっと上の学校を勧められるも、最終的に選択したのは「いちばん自由な」高校。バスケ漬けの中学時代を経て、「遊びたい」という気持ちが強くなっていたのだ。 入学してみると、中学とは全く違った雰囲気に圧倒された。クラスメイトには読モもいた。「私が力を入れて努力で得ているものを、力を抜いた状態で得ている人がいる」——これまで成功体験をしてきたちこさんに、少しずつ心境の変化が現れ始める。 「努力しても、叶わないものがあるのではないか」——うすうすそう感じているものの、これまでの経験から身に染みついた習性が「もっと努力しなくちゃ!」と自身を駆り立てる。勉強、遊び、恋愛、バイト、全ての物事を、全力でがんばる日々が続く。 「自由」を手にするべく入ったその学校では、「遊ぶ」ことこそがカッコ良いとされているように感じた。かといって、けっして落ちこぼれが集まっているわけでもない。ある程度勉強ができる人が集まり、専門学校へ行く人もいれば、良い大学へ入学する人も。自由と引き換えに、ストッパーがないので、落ち始めたら簡単に落ちた。 「自分がどの立ち位置にいれば良いのか、迷う幅が広かった。友達関係も広く浅くなり、『疲れた』と思うことが増えました」 高校では、茶道部に入り、プライベートではダンスにも取り組んでいた。しかし、なぜだか満たされない。バスケに熱中していた中学時代とは違い、一つのことに集中できない。徐々に歯車が狂いだす。 一方、大手の予備校にも通い勉学にも励む。塾に通い始めた当初は「閉鎖寸前で」、大手にも関わらず、生徒は高2のちこさんだけ。マンツーマンで教えてもらうと学力は飛躍的に伸び、勉強が楽しくなった。 講師にお願いされて塾に友達を誘うと、幸か不幸か、あっという間に生徒数が増加。個別指導がなくなっただけでなく、自分の知り合いばかりの教室は、成績順で席が決まった。「競わせる」雰囲気に胸が詰まり、せっかく楽しさを覚えた勉強も、手つかずの状態になっていく。 「だんだん、いままで『これが自分だ』と思ってやってきたことに違和感を感じ、ストレスになってきました。いつも、人の顔色をうかがって“自分じゃない自分”を演じているような。いろんなことにエネルギーを割きすぎて、何が大事かわからなくなってしまったんです」 ストレスに対して、体はいたって正直だ。顔じゅうに吹き出物が出て、薬をいくら塗っても治らない。それを隠すために、化粧もどんどん厚くなっていく。そして、ついには「学校行くのが嫌だ」と思うようになった。しかし、親に「休みたい」ということもできず、登校するふりをして、公園で時間をつぶす日もあった。そこにいたのは、すっかり忘れていたはずの内気な少女の“本来の”自分だった。 「学校も予備校も、何が正しいのかわからなくて、とにかく苦しかった。誰かとしゃべるのもしんどい状態。毎日、浮遊霊のようにフラフラして、何か変われるきっかけを探し求めていたような気がします」 八方塞がりな状況が続いていたある日、兄と話をしていたら、急に涙がとめどなくあふれて止まらなくなってしまった。兄は見かねて「俺が行っている塾に行け」といった。 3年前、壮絶な反抗期を送っていた兄だったが、母親に連れられてその塾に通い始めるとガラっと人が変わった。妹のちこさんも、当時は他人事だったのにも関わらず、その変貌ぶりをよく覚えていた。 「どんな塾なの?」という問いに、「塾長は料理が上手やねん」という、塾とは思えないような回答。疑問もあったが、唯一本音が話せる存在だった兄をとにかく信じてみることにした。 塾に行ってみると、先生とカフェで仲良くなったという〝大人の人〟がお茶をしに来ていたり、先生がご近所の人の人生相談に乗っていたり…塾としては「ありえない光景」が広がっていた。 自習室でテキストを開いてぼんやり過ごしていると、休み時間に、何やら生徒たちが重箱の周りにしぜんと集まりだして、みんなで何かを食べている。ちこさんも「何事か」と輪の中に入り、おむすびを食べてみた。 「……おいしい!」 それは何の変哲もない、具もない、塩むすびだったが、見るからにおいしそうなオーラを放ち、光り輝いていた。そして、ひと口食べた瞬間に涙がこぼれた。自分は心からの幸せを忘れていた、その事実に気付かされた出来事だった。 翌日から、塾の食事の時間が“生きる楽しみ”になった。しかし、先生や奥さんの手が空いた時に作っているため、毎日出てくるわけではないし、時間帯も不規則。なんとか食事にありつこうと、自然と毎日塾へと通うようになっていった。 特別な食材を使っているわけではない。出されるものはおにぎり、ハンバーグ、パスタといったごく普通の家庭料理が、とんでもなくおいしかった。当時嫌いだったお米も、先生との出会い以降、大好物になった。 「いま食べているものの中で、もっともおいしいと思いました。外食でもこんなにおいしいものは食べられないし、お母さんが作る味とも違う」 それは、「家庭料理を極めたらこうなるだろう」という、究極の味。お米を炊くこと、おにぎりを結ぶこと、お茶を淹れること、それらの一つひとつを、「その人の幸せを祈って作った」味。生まれて初めて知るおいしさだった。 塾のみんなは、学校や以前通っていた大手予備校の生徒とは違い、とても穏やかだった。先生の存在や、先生が作ってくれる食べ物を通して、お互いに通じ合っている感覚もあった。彼らと過ごす中で、ちこさんには大きな心境の変化が訪れる。 「どんな私でも、みんな気にしていないとわかったんです。気にしなくていい、そう思えてきました。そこからもう化粧もやめて、まず肌や体を治すことに専念しようと思えました」 そして、これまで陥っていた悪循環を断ち切るべく、学校の友達との接点は全てシャットアウト。休み時間は机に臥せり、“しゃべりかけないでオーラ”を出す。教室移動も一人で動き、下校のチャイムが鳴ると誰よりも先に飛び出して塾へ通う日々。自分が腫れ物扱いされていることも感じていたが、走り出してしまった気持ちを抑えることもできない。 追い詰められていた彼女にとって、他の選択肢は見当たらなかったのだろう。他人に合わせて生きるより、“自分に正直に生きる”方に舵を切ったのだ。 「友人は惑わせたし、悲しい気持ちにさせたかもしれない。扱いにくさから陰口も言われていただろうけど、自分の人生に対する決意ですよね。ここで折れてしまったら、自分の人生を譲ってしまうような気がして」 こんなふうに高3の1年間を過ごし、受験シーズンが到来。自分が何をしたいのかを突き詰めて考え、「おいしいごはんを食べる人生が送りたい」という結論にたどりつく。 「学校でどんなに嫌なことがあっても、塾に行って先生のおいしいごはんが食べられたら、『今日は良い1日だった』と思えた。いままでは与えられる側だったけど、この先の人生で私も作れる側になりたいと思うようになったんです」 進学先は、栄養士科のある短大へ。大学でも、周りの人の顔色を伺うのではなく、高校時代に決めた“正直に生きる”ことを大切にした。しかし、独特な雰囲気が人を寄せ付けるのか、なぜかクラスメイトから興味を持たれることが多かったという。 高校の頃に比べて余裕が生まれていたので、“拒絶する”スタイルは脱し、その頃には“聞かれたら答える”という姿勢に。履いていた5本指ソックスを更衣室で見られ、問われるがままにその効果を答えたところ、すぐにクラスメイトの間ではやったこともあった。 「自分は独自の道を進んでいる感覚があったので、それを他人に押し付けないように心がけていました。入り込みすぎず、求められたら伝えるというスタンス。人に『変わって欲しい』と思って狙って言うと、響かない。あくまでも、その人が求めるタイミングで何かを伝えられる人になれたら、というのは漠然と思っていましたね」 大学入学後も、塾でアルバイトをさせてもらいながら、先生との接点は保ち続けていたちこさん。そして、2年生の時、大きな転機が訪れる。塾があるビルの1階の店舗に、空きが出きたのだ。アルバイトとして塾に残っていた卒業生のメンバーは、ちょうど就活シーズンを迎え、それぞれが将来のことを考えていた頃だった。こんなタイミングで、この場所が空くなんて。先生を慕う仲間同士で、いつまでも一緒にいたい——そんな、夢でしかなかったことが、もしかしたら、叶うかもしれない。 想いは止められなかった。外食の時に食べられるものがなくて困っていた自分たちが、納得の行くお店を作りたい。塾で食べたごはんに与えてもらった力を、今度は誰かに届けたい——そんな想いを胸に飲食店をはじめることを決意。 周囲の反対も乗り越え、06年、枚方市楠葉に「御食事ゆにわ」がオープン。塾で先生が出していた家庭料理をベースに、素材の良さを活かしたシンプルなものを提供し、そこに、作り手のありったけの想いを込める。 「水と塩と米があれば、それだけで人は幸せになれるんです。あとは、厚切りのトマトにオリーブオイルをかけて、一夜干しのアジとお味噌汁があったら最高。そんなシンプルな料理が出てくるお店って、意外とないですよね。お客様を満足させようと、どんどん飾り立てて素材の味を覆い隠してしまう。そんな必要ないのに」 いたってシンプルな、“当たり前”を提供すること。でも、“当たり前”だからこそ、ごまかしがきかないし、難しい。しかも、熱い想いとは裏腹に、店を切り盛りするのは、大学を卒業したばかりの“ど素人”たち。右も左も分からず、寝る暇もおしむ日々が続いた。 「先生は毎日味のチェックに来てくれました。おいしければ開店、何かがおかしければその日の営業はなし。営業しないと、利益も当然ゼロですから、普通はしないことだと思います。でも、先生から教わった高い基準を守るためには、必要なことでした。」 客足も伸びず、利益は出ない。それでも、味が悪ければ開店はしない。お金はないが、食材の質は落としたくない——実にシビアな状況だ。 「いま思えば、先生から『それでもやるのか?』と毎日問われていたんでしょうね。それは先生からの愛でもありました。だけど、1か月も経たないうちに『体力も、気力も、もう限界』と思っていました。でも、そんな気持ちで料理をすると、ネガティブな気持ちが入ってしまうので、食材はさわらせてもらえず、ひたすら洗い物をしている時もありました」 そして、ある日ちこさんは、みんなの前から姿を消してしまう。本当はここにいたい。でも、ついていけない自分がふがいなくて、情けなくて。先生に恩返しする気持ちで始めたはずの店なのに、未熟さゆえに、むしろ迷惑をかけてばかりで…壊れそうだった。しかし、暗い気持ちの中で自身の行く末を案じていると、脳裏に蘇るのは先生が作ってくれた料理の数々とみんなで過ごした幸せな日々。 「私は、あの世界を知ってしまった。この道を諦めたら、きっともう二度と味わえなくなる。他で満足するには、自分の中の基準を下げるしかない。そうして、ずっとやりきれない気持ちを抱えたまま残りの人生を送るんだろう」 「帰ろう」——そう決意して一歩、一歩、歩いていた。店に戻ると、メンバーには怒られ、先生には初めて叩かれた。その瞬間、赤ん坊のように大きな声をあげて泣きじゃくった。 「そこで、『私はここで生きていきたい』とハッキリ気づきました」 その日、先生から店長に任命された。一度は逃げ出したのに、ありえない抜擢だが、「先生は、私の気持ちをぜんぶわかってくれている。この人を絶対に裏切っちゃいけない」と覚悟が生まれた。 もう失うものは何もない。一緒に働く仲間の、そして、お客からの信用を得るべく、いよいよ本腰が入った瞬間だった。ちこさんと「御食事ゆにわ」は、ここから生まれ変わっていく。 ホールで接客をしていると、「なんでこんなに若い子たちばかりでお店をやってるの?」など、店に関する質問が多く寄せられた。 「ハタチそこらの子たちが切り盛りしていて、しかも出てくる料理はめっちゃ渋い。そりゃ疑問に思いますよね」 聞かれるままに、塾や先生のこと、食へのこだわり、提供する料理に込められた想いなどを話すが、時間が足りない。エピソードは溢れるほどあるのに、短い滞在時間の中で伝えられることには限りがある。 なかなか知ってもらえない店の状況にもどかしさを感じ、「もっと伝えたい」という気持ちがあふれ、思い至ったのが、本の出版だった。 「私が高校時代に苦しんでいたのと同じように、日本のどこかに同じような想いで苦しんでいる人がいるんじゃないだろうか。でも、楠葉の街でいくら叫んでいても、遠くの人には届かない」 開店から1年半。当時、お客様だったコンサルタントの知人に毎日の気づきをブログにアップしていたものをみせたところ、「これなら本になるよ」とのお墨付きを得る。そこでちこさんは、自らカメラマンを探して撮影を行い、記事を切り貼りしてサンプル本を作成。出版社に企画書を持ち込んだ。 「客観的に考えて、22歳の、大阪府枚方市楠葉の、飲食業の1年目の人の本なんて誰も読まないし、出版会議にも通らないだろうと(笑)。かといって、『お店は毎日満員です』なんて嘘をつくのもイヤ。だから、先生から学んだ“伝えるべきこと”を、まずは視覚的に訴えようと思ったんです」 こうした行動が功を奏し、09年に初の書籍『いのちのごはん』(青春出版社)を出版。「本を読んで共感した」というお客様が全国からやってくるようになった。 「食べ方を変えると、生き方が変わる」。先生に教わってきたことを、本という形で広く世に知られたことで、店のあり方が、ゆるやかに変わってきた。北は北海道から南は沖縄まで、実にさまざまなところからお客がやってくる。しかも、それぞれのストーリーや想いを抱き、ちこさんの話を「もっと深く聞きたい」という人たちだ。 そして、15年には『運を呼び込む 神様ごはん』(サンクチュアリ出版)を出版。この時、編集担当者が、著者名として「開運料理人ちこ」と命名。いまも名刺に肩書きとして刷られている。 「食事を変えれば、人生はうまく行く」というメッセージが響き、同著は7万部を突破。冷え込んでいた夫婦仲が復活した人など、同著を読んで“人生が変わった”多くの人たちが店に駆けつけ、涙し、ちこさんに対して想いを溢れさせた。作るごとに悩みが消え、食べるごとに運が開ける——ちこさんのメッセージは、まさに「開運料理人」と呼ぶにふさわしいものだった。 古神道の言葉で「お祭りのときに、神様をお迎えする場所」という意味を持つ“ゆにわ”。現在は、枚方市楠葉の「御食事ゆにわ」を筆頭に、大阪5店舗、東京1店舗の計6店と、京都・綾部の宿泊施設が、自然食という枠を超え、それぞれが違ったコンセプトを持って運営されている。さらに、塾、飲食、セミナーなどの事業が有機的なつながりを見せながら、 会社組織として“よりよい生き方”––そのベースにあるのは、毎日のおいしいごはんとみそ汁である––をトータルに伝えている。 がんばって、がんばって、成功を追い求めなくても、日々の中のシンプルな幸せを見失わなければ、迷うことがなくなる。 17年10月には、『暮らしとごはんを整える。』(主婦と生活社)を出版。さらに、18年春に公開予定の映画『美味しいごはん』の撮影も進行中だ。先日は、米の収穫シーンを撮影してきたという。 「セミナーでごはんの炊き方をレクチャーすることがあるのですが、ごはんを炊くところを見ていただくと、感覚がインストールされるのか、受講者は家でとてもおいしく炊けるようになるんだそうです。遠方でセミナーには来られない人もいるから、映像でお見せできれば良いな、というところから製作が始まりました」 少女時代、「見本となるような人を探して」伝記が好きだったというちこさん。「伝記に出てくる人って、みんなだいたい“運命の人”と出会っているんですよね。『私も出会いたいな』と思いながら読んでいました」。 ちこさんにとっての“運命の人”は、塾の先生だったのだろう。そしていま、お店や本、映像などを通して、彼女が誰かにとっての“運命の人”になっているのかもしれない。 (取材/文 中田千秋) 取材場所 東京ゆにわ Teas Üniwa 白金 & 斎庭 Salon de thé 「今日のごはん何?」が、いちばんの楽しみだった幼少期
成功体験が育んだ、「がんばれば認められる」という価値観
“自分じゃない自分”を演じていた高校時代
心からの幸せを教えてくれた、何の変哲もない塩むすび

たったひとつの“心の込もった塩むすび”がちこさんの人生を180度変えた。夢の「御食事ゆにわ」オープンと、立ちはだかる現実
伝えきれない想いを全国に伝えるために、本を出版
大切なのは「おいしいごはんと味噌汁があったら幸せだ」ということ

開運料理人ちこさんと『神様ごはん』を担当した橋本編集長プロフィール
 ちこ tico
開運料理人。
不幸のどん底だった17歳のときに風水師・北極老人と出会い“食を変えると人生が変わる"ことを悟得。声なき声を聞き、香りなき香りを利く料理“ゆにわ流"を伝授される。
大阪府枚方市(ひらかたし)楠葉(くずは)に、自然食という枠を超えた「御食事ゆにわ」をオープン。
飲食店としては異例の「食べたら運が良くなりました」という声が、全国から多数寄せられるようになった。
現在は「御食事ゆにわ」「べじらーめんゆにわ」「茶肆(ちゃし)ゆにわ」を営みながら、「いのごはスクール」にてゆにわ流ライフスタイルを伝授している
ちこ tico
開運料理人。
不幸のどん底だった17歳のときに風水師・北極老人と出会い“食を変えると人生が変わる"ことを悟得。声なき声を聞き、香りなき香りを利く料理“ゆにわ流"を伝授される。
大阪府枚方市(ひらかたし)楠葉(くずは)に、自然食という枠を超えた「御食事ゆにわ」をオープン。
飲食店としては異例の「食べたら運が良くなりました」という声が、全国から多数寄せられるようになった。
現在は「御食事ゆにわ」「べじらーめんゆにわ」「茶肆(ちゃし)ゆにわ」を営みながら、「いのごはスクール」にてゆにわ流ライフスタイルを伝授している

運を呼び込む 神様ごはん
開運料理人 ちこ(著)
1,200円+税
![]()
全国から予約殺到の開運料理人が教える 奇跡を起こす食の作法
作るごとに悩みが消えて、食べるごとに運が開ける。
人生が変わった! 全国から感動の声続々!