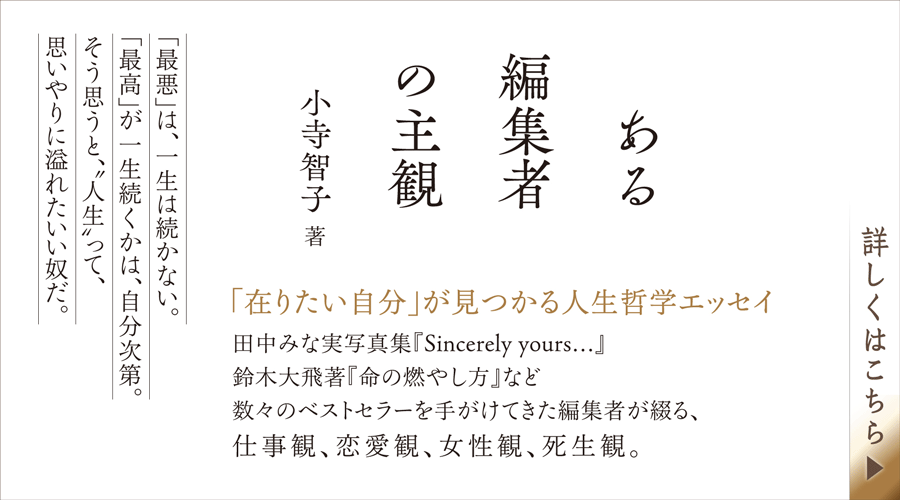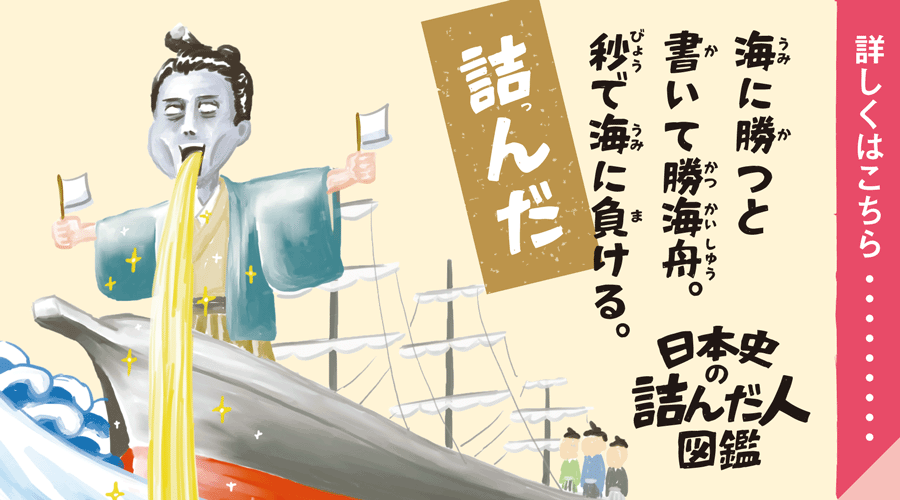『ゼクシィ』『HOT PEPPER Beauty』などに携わった後、「女子未来大学」や女性支援事業を自ら立ち上げた猪熊真理子さん。
その華やかな容姿と、にじみ出る凛とした雰囲気は、まさに“若くして活躍する女性起業家”像そのものだ。
だが、彼女は決して“特別な人間”ではない。むしろ、自分の存在価値を見出せずに長い間思い悩んでいた、“自信のない女の子”だった。著書である「『私らしさ』のつくりかた」の執筆を決意したのも、自分と同じような悩みを持つ女性の役に立ちたい、という思いが根底にあったからだという。
“自信のない女の子”から、“若くして活躍する女性起業家”へ。その平坦とはいえない道のりを、猪熊さんはどのように歩んできたのだろうか。
目次
がんばることをやめたら、存在価値がなくなる
そう思い込んでいた幼少期
さまざまな分野で活躍する女性を講師に迎え、自分らしい生きかたやキャリアについての授業を行う「女子未来大学」。その主宰者である猪熊さんは、あるとき、参加者の女性たちが講師の話を真剣に聴いている姿を見て、不意に涙ぐんでしまったという。
「女子未来大学に参加するために、わざわざ時間をつくって、お金を払って、足を運んでくれる。自分と向き合うことは苦しいことなのに、それでも必死にもがきなら、自分の手で未来を切り拓いていこうとする。そんな女性たちの姿って、本当に美しいと思うんです」
自分の人生をかけて世の中の女性を応援し、ときには涙するくらい心を揺さぶられる。猪熊さんのその情熱は、いったいどこからくるものなのか。答えを知るカギは、彼女の幼少期のある体験に隠されていた。
香川県の小さな街で、両親と兄弟、近所に住む祖父母に囲まれて暮らしていたという猪熊さん。愛情豊かな家族と、日差しが降り注ぐ穏やかな瀬戸内海に見守られながら、バレエ・ピアノ・習字などの習いごとに大忙しの毎日。恵まれた環境で何不自由なく育ったかのように思えるが、幼い胸の奥には、暗いものが常に渦巻いていた。
「本に書くかどうか最後まで迷ったのですが、女性支援に対する私の情熱の原点はここにあるので、家族の了承ももらって思いきって書くことにしました。私には、生まれることの叶わなかった妹がいました。彼女のことを思うたび、“もしかしたら私が妹の立場だったかもしれない”“妹は生きたくても生きられなかったのに、私なんかが生きていていいんだろうか”と、幼心に感じていたんです」
そう話してくれた猪熊さんの表情は、吹っ切れたように明るかったが、彼女が抱えてきたものの重さは計り知れない。
「だから、私は常に自信がなかった。どれだけ勉強や習いごとをがんばっても、がんばることを少しでも休んだ瞬間に、私の生きている価値なんか消えてなくなるんじゃないかって、不安でたまりませんでした」
惜しみなく愛情を注いでくれていた家族に、その本心を打ち明けることはできず、ひとりでずっと悶々としていたという猪熊さん。少女から大人の女性へ成長していくにつれ、漠然とした不安は“生きていること”そのものへの疑問に変わっていった。どうして世の中には、生きられる人と生きられない人がいるんだろう。私はなんのために生かされているんだろう——。
「この前、実家に帰ったら、廊下に見覚えのある焼き板が飾ってあったんです。よく見ると、中学2年の立志式(かつての成人である15歳になったときに、将来の目標などを掲げて大人になる自覚を深める儀式)で、私がつくった焼き板でした。そこに書いてあったのは、
『自分の力を最大限にだした、精一杯な生きかたをする』
という言葉。生きることへの疑問や理不尽さを抱えていた当時の私が、自分なりに導き出した解決策だったんでしょう。この私のスタンスは、今もほとんど変わっていないので、なんだか16年前の自分に勇気をもらったような気がしました」
悩みながらも一生懸命生きようとしていた我が子の葛藤を、両親もちゃんと知っていた。
「立志式では、生徒一人ひとりに親からの手紙が渡されるというサプライズもあったんですが、『真理ちゃんはいつも全力投球』という母からのメッセージに泣いてしまった記憶があります。私の本心は理解してもらえていないと思っていたけれど、そうじゃなかったのかもって」
この世に生かされているからには、精一杯、全力投球で生きる。自分なりの心の落としどころをようやく見つけて、猪熊さんの青春時代はより一層せわしく過ぎていこうとしていた。
病気になってはじめて気づいた、
心の悲鳴
ところが、高校2年のある日。いつも通り授業を受けていた猪熊さんの身に、異変が起こった。突然、動悸がして、手の震えや吐き気が止まらなくなったのだ。病院で出された診断は“自律神経失調症”。あまりのショックに、思わず言葉を失った。
「勉強も部活も習いごともフルパワーでがんばって、自分なりに楽しく充実した毎日を送っていると思っていました。まさか心の病気にかかるなんて……」
だが、そこではじめて、無理をしていた自分に気がついた。自分のためにがんばっていたのではなく、親や先生、部活の先輩、まわりの友達が期待する“いつも全力でがんばる完璧な私”を演じようとしていたのだと。そして、本当はだれもそんな自分を期待していないということにも、限界を超えて悲鳴をあげた心身を通して、ようやく気がついたのだ。
そのとき、猪熊さんは思ったという。
「“心”って、なんなんだろう」
自信を持てないのも、妹のことを思って苦しくなるのも、まわりの期待に応えようと必死になるのも、体が突然言うことをきかなくなったのも、すべては“心”のしわざ。目に見えないのに、こんなにも自身に影響を及ぼす“心”の正体は、いったいなんなのだろう。
「心理学を勉強したいと思いはじめたのは、この頃です。今の私の仕事に心理学の造詣が欠かせないことを考えると、病気でダウンしたことも必然だったのかもしれませんね」
こうして猪熊さんは、生まれ育った香川県を離れ、東京女子大学の心理学科で人生の新たなスタートを切ることになった。
“ありのままの私”で生きられていないのは、
自分だけじゃなかった
大学に進学し、興味の対象は“自分自身の心”から“女性の心”へと少しずつ広がっていった。自分と同じように自信を持てずにいる女性が、思いのほか多いことを知ったのだ。
「女子大という環境だったこともあり、女性たちの本音や悩みに触れる瞬間がたくさんありましたね。当時は、私も含めてみんなとにかくトレンドを追っていて、流行りのブランドのワンピを着て高価なバッグを持つことが一種のステータスでした。“みんなから外れている”と思われるのがいちばん怖いので、自分がかわいいと思うものではなく、みんながかわいいと言っているものを持つ。それって結局、自信のなさのあらわれなんですよね」
自分が窮屈にならない生きかたとはどういうものか、どんなことになら情熱を傾けられるか、自分自身のことをより深く知るために、さまざまなことに挑戦した。バレエサークルに入ったり、他校との合同サークルに参加したり、ボランティア活動の手伝いをしたり……。もともと美容やファッションが好きだったことから、思いきって読者モデルをはじめてみたりもした。そこでもリアルな“女性の心”に触れることになる。
「その頃は、まわりの読者モデルのみんなに劣等感を感じてつらかったこともありました。“みんな自分よりきれい”“かわいがられてる”“いいバッグ持ってる”……表面的なことばかり気にして、そんな自分もすごくイヤでした。でも、だんだんわかってきたんです。どんなにきれいで、みんなから憧れられている子でも、心のどこかでまわりの目を気にして“ありのままの自分”を出せていないということが。自分のことが好きで、自分の生きたいようにのびのびと生きている人は、ほとんどいないように見えました」
心理学の調査や研究結果などを自分なりに調べていくうちに、猪熊さんはある社会的な問題に行き当たる。女の子は愛されて生きるべき、という昔ながらの価値観。自己主張よりまわりとの調和を大切にするべき、という暗黙の美徳。女性は従順であるべき、という、時代錯誤のように思えて実は根強く残っている思想。これらが複雑に絡み合い、女性特有の“自信のなさ”をつくり出しているのではないか。そう考えるようになった。
「自信を持てないことが個人の問題だけではなく、世の中の女性に共通する悩みだとしたら、どうにかしなくちゃいけない。そんな使命感を感じるようになりました」
猪熊さんがまずはじめたのは、当時流行っていたブログ。自信を持てない女性が多いのはなぜか、自分らしく生きるにはなにが必要か、日頃から考えていたことを文章にまとめ、コツコツ発信するところからスタートした。
「そのときはまだ、“自分の考えを世の中に広く伝えたい”とか“いずれ自分で事業を……”と強く意識していたわけではありませんでした。まずは考えていることを整理して、忘れないように文章に残しておこう、程度の気持ちだったといいます。でも、発信をつづけていくうちに、読んでくれた人から反応が返ってくるようになりました。そのうち、私と同世代の就活生や、キャリアに悩む女性に向けた、講演会のオファーをいただくようになったんです」
今でこそ、「女子未来大学」や企業向けセミナー、政府・自治体の会議などで登壇する機会の多い猪熊さんだが、当時はもちろん未知の領域。自分に務まるか不安だったが、3歳からバレエで人前に出ていたこともあり、大勢の人の前で話すことは苦でなかったという。
「バレリーナになりたいけれど、いくらがんばってもNo.1になれない。つづけている意味はあるのかな……。そんなふうに悩んでいた時期もありましたが、地道につづけてきた経験がこんな形で役に立つとは思いませんでした。人生に無意味なことなんてないんですね(笑)」
講演を重ねるうちに、自分の考えが整理されたり、自分に共感してくれる人があらわれるようになった。“私はこのままこの道を進んでいいんだ”という自信が、少しずつ湧いてきた。
「すべての女性が自分らしく輝けるように、私にできることを全力でやりたい」
これまで漠然としていた思いが明確な言葉に変わったのは、ちょうどこの頃だった。
近い将来、本気で女性支援に取り組むために、
リクルートに就職
まわりを見れば就職活動の真っ最中。そんななかで猪熊さんは、卒業後すぐに起業するか、一度企業に就職をするべきなのか、進路に悩んでいた。
最終的に“就職”の道を選んだのは、世の中の女性の役に立ちたいという思いがそれほどまでに本気だったからだ。
「本気で女性支援に取り組むとなれば、それを継続させるための資金も戦略も必要になってきます。すぐに起業したとしてもノウハウがないし、ボランティアだと自分が食べていけません。そう考えて、今の自分に必要なことを学べる会社に就職しようと決めたんです」
ビジネスを学ぶための修業先に選んだのは、就職・結婚・住まい・美容・グルメなどの幅広い事業を手がける株式会社リクルート(当時)。単なる商品やサービスの提供ではなく、人の人生に影響を与えたり、街全体を活性化させたり、新たなマーケットを開拓したり……という視野の広さには、猪熊さんの目指すビジョンと重なる部分が多くあった。
「面接では、“将来、女性向けの事業を立ち上げるための勉強がしたいので、『ゼクシィ』か『HOT PEPPER Beauty』か『L25』に配属してください”なんて生意気なことを言いました(笑)。その甲斐あってか、入社後は晴れて『ゼクシィ』に配属。今思い返しても、本当に感謝しています」
「ゼクシィ」では編集者として、結婚情報誌の編集に従事。花嫁のリアルな声を、クライアントである式場やドレスショップにもっと知ってもらいたいという思いから、「ゼクシィ編集部通信」なるものの配信も自発的にはじめた。その取り組みが評価され、入社2年目からは企画の仕事に携わるように。
3年目には、自ら手を挙げて部署異動できる制度を使い、「HOT PEPPER Beauty」の事業部へ異動した。ブライダルよりもさらに日常に近いマーケットで、女性のニーズを知りたいと思ったからだ。事業の中長期戦略を考える仕事から、テレビCMの企画まで、若くしてさまざまな経験を積んだ。
「世の中を動かしていくことのおもしろさを実感したのもこの頃。当時はまだ美容室に電話で予約を入れる時代でしたが、企画したCMを通じて、ネット予約という新しい文化がじわじわと浸透していきました。マーケットを読む力や、ターゲットの設定のしかた、ターゲットに響くアプローチの考えかた、事業を手がけるうえで必要ないろんなことを学んだ貴重な経験でした」
会社員時代は、自分らしい自由なファッションで通勤していたという猪熊さん。自分のやりたいことが定まってからは、まわりの目もあまり気にならなくなったそう。
「“猪熊は自由な人なんだ”というイメージを一緒に働いている周りの皆さんも受け入れてくれていたおかげで、上司にも先輩にもとくになにも言われませんでした(笑)。その代わり、信頼されるような仕事のしかたをしていくことは常に心がけていました。“いつまでにやっておいて”と言われたら、期限よりも早く提出する。どんなに小さな仕事でも、相手の期待以上のものに仕上げる。自分の“信頼残高”を増やすような気持ちで仕事をしていましたね」
リクルートでのダブルワークから、
株式会社OMOYA設立へ
いよいよ自分で事業をはじめようと思ったとき、猪熊さんが最初に選んだのは“ダブルワーク(副業)”という形だった。
「リクルートは副業を認めてくれる会社だったので、まずはリスクの少ない方法でスタートすることにしました。会社に勤めながら自分の会社を立ち上げ、女性向け商品・サービスの企画や、大学時代からつづけていた講演などを、事業として行っていました」
ダブルワークをやめて起業の道を選択したのには、いくつか理由がある。
「会社で責任あるポジションを任されるうちに、“経営者”がどんな仕事なのか、より興味が湧いていきました。自分の判断で事業が動いていくぶん、責任をともないますが、それだけ自分の考えや人間性を事業に反映させることができる。私にとって“自分100%”で生きられる仕事だと思ったんです」
政府が「女性の活躍推進」を成長戦略として掲げたことも、起業を後押しした出来事のひとつ。ダブルワークでは時代の波に置いていかれるという危機感を感じたという。
また、経営者になることで、人としてより豊かに成長したいという思いもあった。
「意外に思われることもあるんですが、私の人生でいちばん優先順位が高いのは“母親になること”。お母さんが子どもにやってあげることって、実は経営者の役割に近いんですよ。子どもがのびのびと自分の力を最大限発揮できるように、環境を整えてあげるという。経営者として事業やスタッフを成長させることで、私自身も人間的に成長することができれば、より愛情豊かな母親になれるのではないかと思いました」
そうして、7年間勤めたリクルートを退社し、2014年に株式会社OMOYAを設立した猪熊さん。女性の心を豊かにするような商品やサービスのプロデュース、企業内の女性活躍を推進させるためのコンサルティングをはじめ、講演事業の進化版としてファウンダー3人で「女子未来大学」を立ち上げた。
さらに、起業家・料理研究家・翻訳家・YouTuberといった女性のプロフェッショナルたちとチームを組んで、商品やサービス、ブランド、街づくりなどを行う、猪熊さんらしい独自性のあるビジネス「女性プロデューサー事業」も新たにはじめた。
大学時代に学んだ心理学の専門知識、会社員時代に学んだ事業戦略やマーケティングのノウハウ、そして最大の強みである“女性への共感力”をいかし、満を持して自分の事業をスタートさせたのだ。

「女子未来大学」の様子。この日は、「ママが輝ける社会」をテーマに、ママ&いつかママになりたい女性たちが参加した。キャリアや子どものスペシャリスト4人を招いてトークセッションをした。

ここぞ、という日に身につける大切な仕事の相棒。プロデュースした100carats of beautiful lifeの「NEO Classic 七宝模様ネックレス」。日本の伝統模様を現代のファッションとして昇華させたところがこだわり。
“私でよかった”と心から言えることが、
“私らしく生きている”証
猪熊さんがこれまでに講演やイベントを通じて出会った女性は、のべ3000人以上にのぼるという。高校生から70代まで、年齢も立場もさまざまな女性と真正面から向き合い、自分らしく生きるためのサポートを行ってきた。
「すべての人に、その人だけの“役割”があります。どの役割にも唯一無二の価値があり、優劣はありません。その役割に気づくことが、自分らしい人生を送るための最初の一歩。すでに与えられている恵みに気づかず、ないものねだりをして苦しんでいる人は、多いと思うんです」
その考えかたを教えてくれたのは、愛情深く育ててくれた両親だったと、猪熊さんは振り返る。
「父は、大人も子どももどんな職業の人も平等だという信念を持つ、公明正大な人。母は、どんなときでも私のことを応援し、尊敬してくれる、私のいちばんのファンのような人。自分の存在意義に悩んでいた幼少期にはなかなか気づけなかったけれど、私の“私らしさ”をいちばん理解し、尊重してくれたのは、いつでも両親でした」
生きることの意味を、自分の命に代えて教えてくれた妹も、猪熊さんにとってかけがえのない存在だ。
「大学3年のとき、1つ年下の親友ができました。彼女とは本当の姉妹のように親しくしていて、お互いの人生の転機やつらい時期には、必ずそばにいるような関係。私が姉として妹にしてあげたかったことを、彼女はたくさん経験させてくれました。そんな“心の家族”の存在もまた、自分らしく生きる勇気や希望を与えてくれます」
自分らしさを貫きつづけていると、ときには壁にぶつかることもある。そんなときに心を救ってくれるのは、自分らしさを無条件に受け止めてくれる人の存在だ。家族でも、親友でも、恋人でも、ビジネスパートナーでもいい。たったひとりでもいいから、自分を100%さらけ出せる相手を見つけることが、実はとても大切だという。
「“私らしさ”は、自分ひとりでつくろうとしなくていいんです。だれにも理解されなくて苦しいと感じたら、信頼する限られた人にだけでも心を開いて、本当の自分を少しずつ取り戻していけばいい。私もよく親友たちに“今の私ってどう見えてる?”と尋ねて、自分が思う“私らしさ”とまわりが思う“私らしさ”のすり合わせをしています」
2016年12月、「『私らしさ』のつくりかた」の発売直後に32歳の誕生日を迎えた猪熊さん。本を書くという行為は、これまでの32年間の棚卸しのような作業だったと語る。
「楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、悩んだこと。そのすべてが“自分が自分になるために必要なこと”だったのだと思えました。いろんなことがあったけれど、今は“私でよかった”と心から言える。それこそが、“私らしく生きている”という紛れもない証なのではないでしょうか」
かつての“自信のない女の子”は、いまはもういない。たくさん悩み、いろんなことに挑戦し、大勢の人と出会い、日ごとに“私らしい私”に近づいている自分を、いまは心から楽しんでいるようだ。
「最近では、好奇心旺盛で自由なありのままの私が出すぎて困っているくらい。親友たちには“まるで3歳児だね”ってよく言われます」
そう口にした猪熊さんの顔からは、子どものような笑みがこぼれていた。
(取材/文 三橋温子)