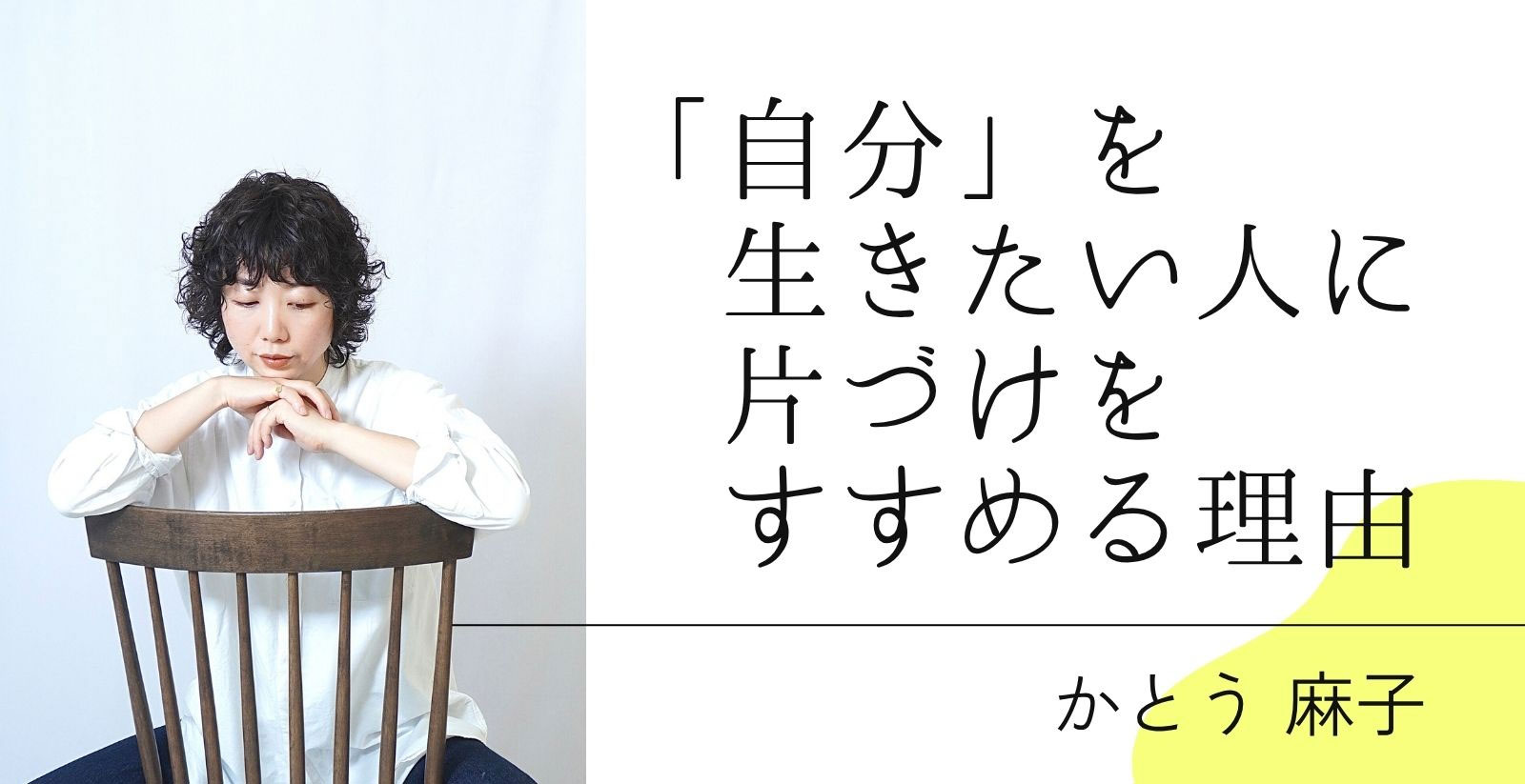「自分」を生きたい人に片づけをすすめる理由を連載しているけれど、「『自分』を生きる」って何だろうか?
私の中のひとつの答えは、選択と納得です。
他の誰でもなく「自分で」選ぶっていう行為と、そこへの納得感。その積み重ねで「『自分』を生きてるなぁ」って思うんじゃないですかね。
こんにちは、モチベーターのかとうです。
片づけって行為は選択の連続だから、この「選択と納得」を鍛えるすごく地に足のついた練習だと思う。自分の理想を軸にして選び、選び取ったもので暮らす。このプロセスはけっこう尊くて、片づけ以外にめちゃくちゃ生きる。
前回(連載四回目:https://sanctuarybooks.jp/webmag/20250313-17280.html)はモノをどう「整理」をするか?ってテーマで、四つの領域の「ただある」にメスを入れていく話をしました。自分にとっての「理想」を描いて、それを軸にモノを「整理」していく。どうでしょう?仕分けはけっこう進みましたか?進んでたら嬉しいです。

進んでるのを前提に、五回目の今日は「収納」の話をしますね。
「整理が終わった!さぁ収納だ!」と意気込む人ほど、インスタや雑誌の美収納に飛びついて収納グッズ爆買いとかしがちやけど、気をつけてほしい。それではうまくいかないからね。
まず大前提、収納の軸は「取り出しやすさ」と「しまいやすさ」です。
で、「取り出しやすい・しまいやすい収納」を作るために重要なのは「主語」です。どういうことか説明しますね。
手がつけられない状態まで散らかる理由は?
―モノを片づけないから。
モノを片づけられない理由は?
―モノの定位置(住所)を決めていない、もしくは住所があってもしまいにくいから。
モノがしまいにくい理由は?
―モノの住所や収納方法が自分の動きや体や性格に合ってないから。
収納が自分に合ってない理由は?
―自分を観察せずに収納方法を決めているから。
いかがでしょう。
あなたの家のモノを取り出すのは、しまうのは、一体「誰」か?スマホで見ているインスタグラマーか?雑誌に載ってる片づけ上手さんか?
否、あなたですよね。「主語」はあなたです。

雑誌やSNSに出てくる「美収納」は、その家にすんでいる人たちの使いやすさで作られているから、ただ真似してそのままあなたの家に作っても、合わないことがある。
「いや、私は参考にしてないし…」と思ってる方も、「こういうもんだろう」「実家はこうだったから」で自分無視で収納決めていたりしませんか?それもいっしょ。「主語」が自分になってない。
では、「自分無視」をやめて「自己観察」して収納を考えてみましょう。観察するのは三つです。
①モノの観察
②収納スペースと体の観察
③動きの観察
それぞれ説明しますね。
①モノの観察
まず、モノの「使用頻度」を観察してみてほしい。
(モノはもちろん「整理」が終わったあとのモノたちです。)
例えば「平日身に着けているスカート」と「喪服」だったら、喪服の方が使用頻度は低い。
毎日使うタオルと月一回出番が来る詰替用シャンプーなら?
毎日使う食器と年に一回使う重箱なら?
こんな感じで。
前回四領域の話で「スタメン」と「スタンバイ」に分けたけど、もう少し細かく観察してみる感じです。

②収納スペースと体の観察
次は体。体?って思うかもしれないけど、体が大事。
クローゼットがあるならその前に実際に立ってみてほしい。(押し入れでもいいし、キッチンの戸棚の前でもいい。)
あなたは扉をどっちの手であける?手はどこまで届く?
立った目線で見えるのはどこまでの範囲?って観察する。
扉をちょっと開ければモノが取り出せるエリアと、
全部開けないと取り出せないエリアがある。
しゃがまないといけないエリアと踏み台がいるエリアもある。
どのエリアが出し入れしやすくて、どのエリアは大変そう?

…みたいな感じで観察してみてほしい。
そうしたら「あなた特製あなた限定あなたの家の収納スペースあなたの使いやすさランキングマップ」(長い)が出来るはず。
これって、家によって違うのはもちろん、利き手や身長、体の状態によっても答えが違ってくるのわかりますよね。高所恐怖症の人は上のエリアは使いにくいかもしれないし、膝が痛い人はしゃがむエリアは使いづらいかもしれない。
正解はあなたにしかわからないし、あなたが決めていい。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
③動きの観察
最後は、動き。
例えば起床後、調理中、洗濯ものを取り出して干す時、子どもの書類を書く時、食材を買って帰ってきた時、どういう動きをしてる?
行ったり来たりしてるなら、本当はどういうルートならスムーズ?
そういう「動き」の観察。いわゆる「動線」ですね。

あとはね、仕切りを買ってきてがんばって靴下収納作ったけどぐちゃぐちゃになってるとか、素敵な収納ボックスを買ったはずなのにフタの上にモノが積まれてる…なんてあんまり見たくない現実も観察してほしい。
仕切りに合わせて入れることや、しまう時にわざわざフタを開ける→しまう→フタを閉めるってことが性に合ってないのかもしれないから。
ここけっこう大事なんですけど、こういう時、よく「私がだらしないから」「悪い癖だから直さなきゃ」みたいに思う人がいるけど、違うからね?
収納が自分に合ってないだけ。そこは「自分と相性のいい収納方法にしよう!」って思うべきところ。無理してるから続かない。リバウンドが起きるで。
「私、これが楽だな〜」「これなら出しやすいな〜」って思えるのはどんな状態ですか?それを観察して、許可する「心地よい甘さ」が収納には必要だと私は思う。

さて、こんな感じで色んな観察をしてみたら、きっと発見がたくさんあるはずです。何を発見しましたか?
「よく使う家電なのに、背伸びしないと届かない棚に置いたわ」
「調理中は菜箸もってるから、左側においてる方がスムーズじゃん!」
素晴らしい。ホント素晴らしい。(拍手)
ここまでやったら、あとはモノと収納スペースをマッチングさせるだけ。やってみて。
今回はモノの「収納」の話をしてきたけど、収納の力で身につくのは「自己観察」や「自分自身を大事にする」ってことです。
自分が一体どんな人で、どんな癖があって、どんな風になりたいと思っていて、どんなことに心地よさや心地悪さを感じているのか?
そして、そんな自分に優しくするにはどうする?こうかな?
そんな観察と検証の連続が「収納」だと思う。
これは片づけ以外でも常にやるべきこと。
でも、自分に問うことを後回しにして、外に正解を求めてしまうことや誰かの正解に乗っかってしまうことって、実はすごく多い。気づけば「世間的に正解っぽいこと」ばかりを気にして、そこに合わせて暮らしを組み立てていたりする。

それで苦しくなっていませんか?
それで退屈していませんか?
それで「自分」を生きてるって感じられますか?
「あ、これまでそうして生きてきたかも…」と思った人がもしもいるなら、よかったら「片づけ」からはじめてみてください。
次回はまとめ回です。
これ読んで「なんかいいな」と思った人は、「読んでほしいな」と思う人に伝えてくださいね。中学校や高校の頃、授業中に手紙を回したみたいに。ほなまた。
あ、そうだ、そうだ。ご家族も使うエリアを片づけるなら、みんなの身長や癖や動線なんかももちろん観察して「収納」作ってくださいね。相談しながら、トライ&エラー&リトライしながらね。ほなまた。
かとう麻子 1984年高知県生まれ、大阪府在住。 8年間の専業主婦生活を経て、2020年に整理収納アドバイザーとして起業。 現在は社会人学生として仏教を学びながら、落ち着いてるのに落ちない心と尽きない行動力を引き出すモチベーターとして活動中。 オンラインサロンやトークイベントなどを多数開催。一児の母。

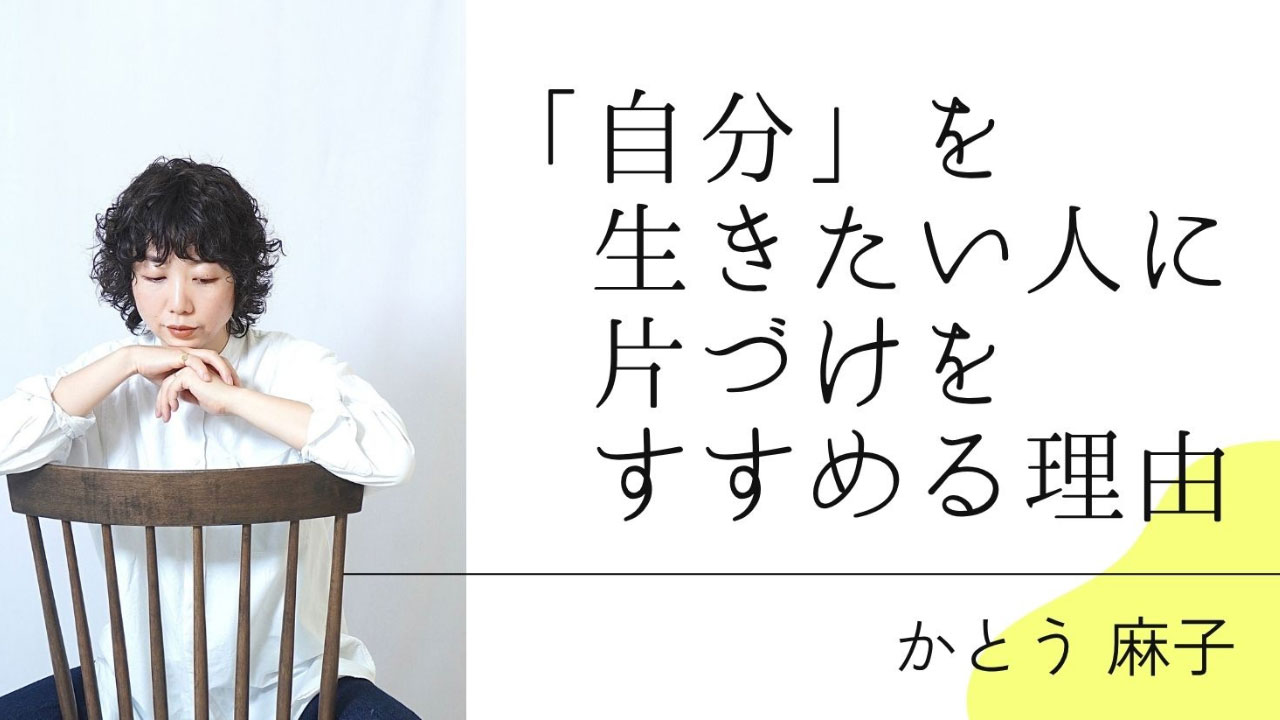

 かとう麻子
1984年高知県生まれ、大阪府在住。
8年間の専業主婦生活を経て、2020年に整理収納アドバイザーとして起業。
現在は社会人学生として仏教を学びながら、落ち着いてるのに落ちない心と尽きない行動力を引き出すモチベーターとして活動中。
オンラインサロンやトークイベントなどを多数開催。一児の母。
かとう麻子
1984年高知県生まれ、大阪府在住。
8年間の専業主婦生活を経て、2020年に整理収納アドバイザーとして起業。
現在は社会人学生として仏教を学びながら、落ち着いてるのに落ちない心と尽きない行動力を引き出すモチベーターとして活動中。
オンラインサロンやトークイベントなどを多数開催。一児の母。