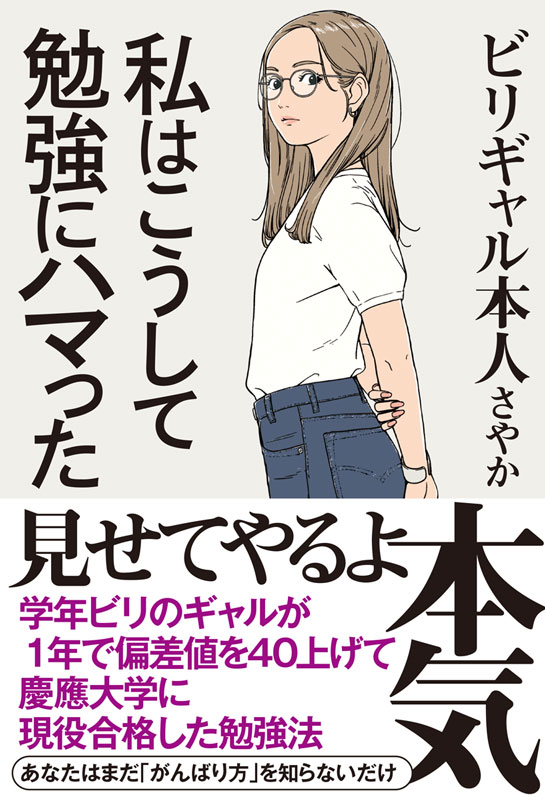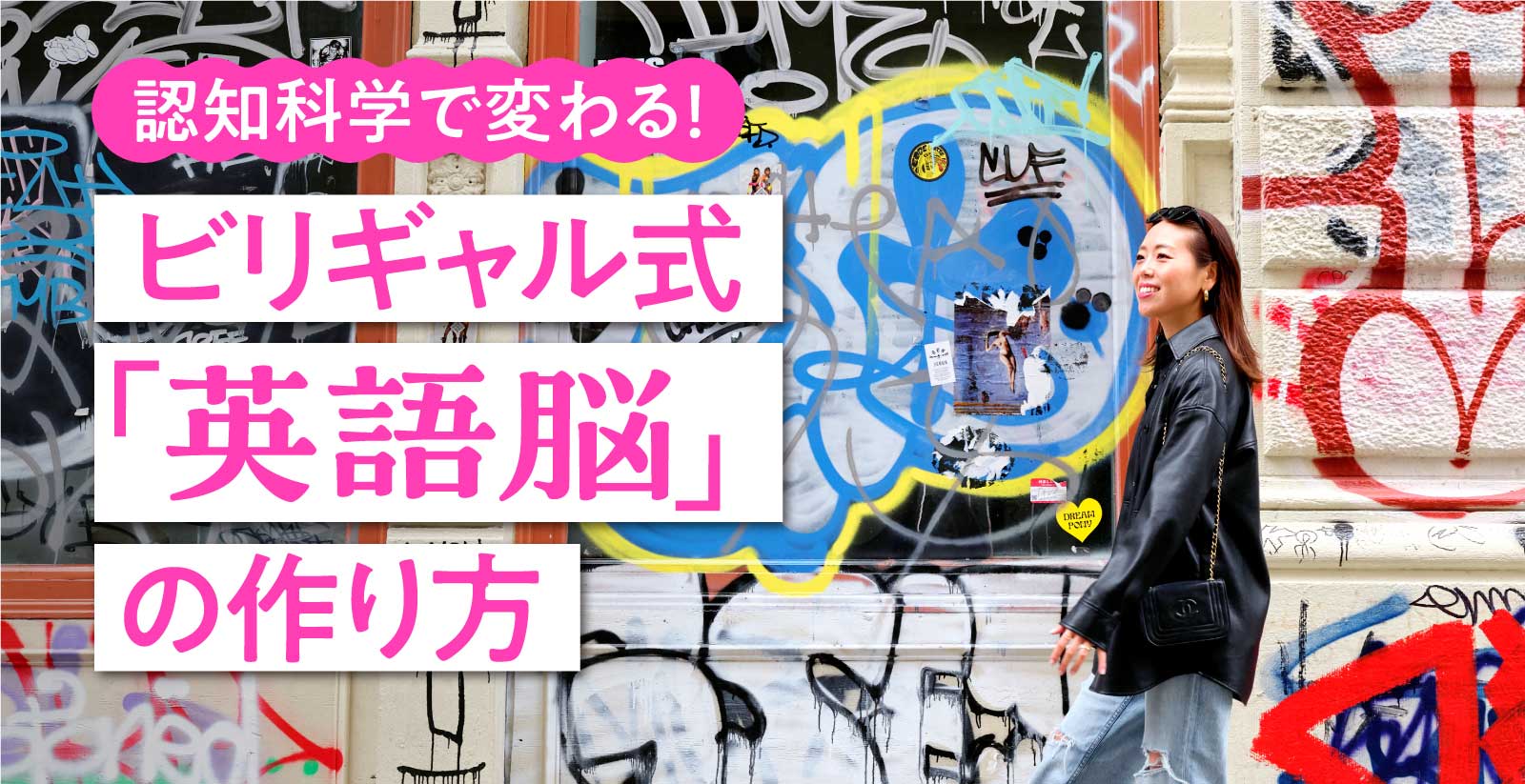目次
日本人と他国の英語教育の違い
前回は「そもそもなぜ、日本人は英語が話せないのか?」についてお伝えしました。
その理由はみっつあると私は考えていて、そのうちのひとつは他国、特にヨーロッパ諸国と比べて、「母国語以外を話さなくてはいけない理由」が著しく欠けているからだと思っています。
そして理由のふたつめは、英語教育の違い、と思っています。
第二言語習得論と呼ばれる分野(簡単にいうと、どうやって母国語以外はマスターできんの? を追求する学問)では、大きく分けてふたつの流派があるそうです。
ひとつは、「インプット仮説」と呼ばれるもので、
「第二言語はとにかく理解できるレベルのその言語の音声をききまくって、読みまくってれば、そんなにアウトプットしなくても自然に聞けるように喋れるようになります!」
と主張するもの。
日本人の中にも、「4歳までアメリカにいたんだよね〜」といういわゆる帰国子女さんは、このインプット仮説のとおり、文法知識とか語彙力とかそんなにないけど、とにかくその言語に触れまくった経験があるので、リスニングとスピーキングのスキルが嫌でも上達してしまう、ということが起こっているようです。
オランダなどの英語がめちゃくちゃできる国では、さっき言った通り、英語がもすごく身近にあるので、まさにこのインプット仮説に当てはまりますね。
学校でもいろんな教科の授業が当たり前のように英語で行われていて、高校生になる頃にはネイティブクラスの英語力が身についちゃうようです。
そしてもうひとつが、「自動化理論」と言われるもので、
これは
「まずはその言語のルール(文法)とボキャブラリーを意識的に学びましょう。
でもそれだけだとスムーズには使えないので、繰り返しの練習や経験を積んで、それらを自動的に使えるように特訓しようね!」
というもの。
日本の英語教育は、こちらの理論に立脚してデザインされているそうです。
日本の英語教育の落とし穴
私達、めちゃくちゃ英文法学びましたよね。
もはやネイティブでも知らないような難しいルールまで、徹底的に学ばされてきました。
ボキャブラリーも、「これ日常会話で絶対使わないよね?」というような難易度の高いものまで暗記しました。
でも、これらを流暢に使いこなせているかというと、ほとんどの人ができてないですよね。
これが、日本の英語教育の落とし穴で
「ルールとボキャブラリー、十分学べたね! オッケー! じゃあ、自動化するところは自分でやっておいてね! グッドラック!!」
ってかんじで、途中までしかやってくれてないんですって。
だから私達、あんなに勉強したのにしゃべれないんだよ!!!
想像してみてください。
教室で、今日はみなさんに、「泳ぎ方」を教えます。身体っていうのは、こういうふうにつくられていて、ここを動かすとこの部分がこう動きます。すると水の中でこのような動作になり、前に進みます……
と、先生が細かく「泳ぎ方」について説明してくれます。それで、生徒たちは、「オッケー理解した!」となったとします。それで先生はこう言うんです。
「じゃあ、今日学んだことをプールに行くことがあれば、ぜひ思い出して泳いでみてね!グッドラック!!」
実践は、しないんですね。
学んだことが自動的に使えるようになるにはたくさんのトレーニングがここから必要なのに、そこはそれぞれに任した!というかんじ。
途中で放り出される感じです。
これでは、英語が話せるようになるわけがありません。