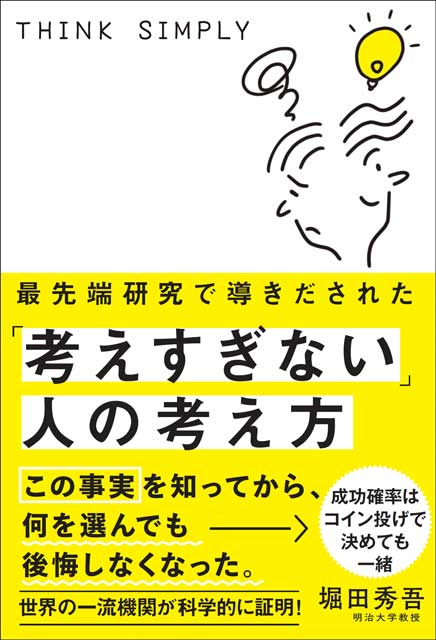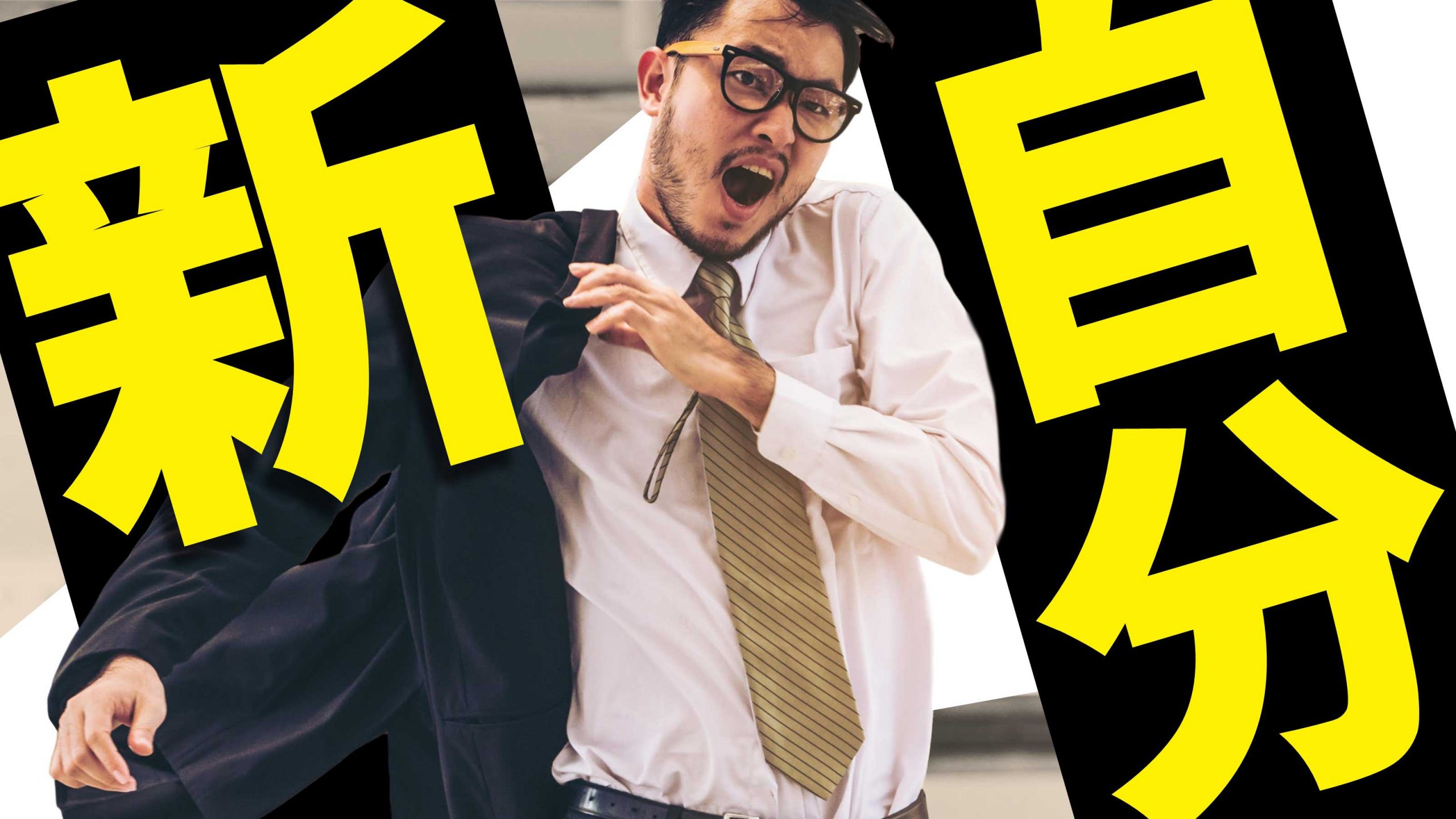人が「考え方を変えたい」と思うとき、不安や悩みがあって怒りや悲しみを感じている状態なのではないでしょうか。嫌なことばかり考えてしまうと、どんどん弱っていってしまい、放っておけば負の感情から抜け出せなくなってしまいます。
この負の連鎖を断ち切るためには、考え方をかえる必要があります。
考え方を変えるためには無意識のうちに繰り返してしまう、偏った考えを修正しなければなりません。ネガティブな感情につながる考え方には、複数のパターンがあります。考え方を変えるには、物事に対して自分が、どのような考え方をしているのかを見つめ直すことが大切です。
この記事では、考え方をポジティブにする4つのステップを紹介しています。自分の考え方を変えたいと思っている人は、ぜひ参考にしてください。
目次
【ステップ1】考え方や思考には10パターンの癖があることを知る

人によって、物事に対する考え方の癖があります。癖には、一定のパターンや傾向があるため、自分の考え方が癖であることに気づかない人もいます。
一見考えているように見えても、無意識に思い浮かぶ考えにひきずられ、癖が出やすくなるようです。
ネガティブな考え方が癖だと気づけると、ストレスの減少につながることでしょう。このような理論は、デビット・バーンズ博士の「認知の歪み」がもとになっています。
デビット・バーンズ博士の理論「認知の歪み」によると、ストレスを感じやすい考え方の癖は、大きく分けて10種類のパターンがあります。以下にて、バーンズ博士による10種類の「認知の歪み」を、わかりやすく解説します。
パターン1:0か100かで考える
「全か無かの思考」とは、物事を両極端な考え方しかできず、中間の結果には不満やストレスを感じる傾向のことです。
認知の歪みの基本といえるでしょう。完璧志向が強く、物事を白黒はっきりさせたいという考え方の癖です。
パターン2:一度のことだけでそれが続くと考える
「行き過ぎた一般化」は、一度でも悪いことが起きると、これから先も同じことが起きると思い込む癖です。
例えば、1人と人間関係が悪くなっただけで、自分は周りの人すべてと仲良くなれないと思い込む傾向です。物の見方に柔軟性がなくなり、余計なストレスを抱えます。
パターン3:良いことを取り除く
「心のフィルター」と、バーンズ博士は紹介しています。すべての出来事を自分の「心のフィルター」を通して見てしまいます。
そのため物事の良い部分は見ずに、失敗やトラブルなど悪い部分だけを取り入れてしまいます。
例えば、過去の失敗だけを思い出して、自分には良いところが1つもないと考えてしまうなどです。
パターン4:すべてを悪い方向に考える
「マイナス化思考」は、良いことも悪いことも、すべて悪いほうに変えてしまう癖です。
「マイナス化思考」の人は、昇進した場合も喜ぶのではなく、「まぐれ」「過大評価」と思い込み、「仕事が務まらなくて失敗してしまうかもしれない」と、逆に落ち込むこともあります。
パターン5:思い込みや先読みをする
「結論の飛躍」は、勘違いや早とちりで、誤った結論を出すことを指します。
「結論の飛躍」には2種類あり、「心の読みすぎ」は、ストレスにつながる悲観的な勘違いです。「先読みの誤り」は、これから起きることがすべて深刻な事態になると信じ込む考え方です。
小声で話している人たちがいると、自分の悪口を言っていると思い込み、否定的な結論を出してしまいます。
パターン6:悪いことは大きく良いことは小さく考える
自分の短所や失敗を重大にとらえ、長所や成功への評価が低いことを、「拡大解釈と過小評価」といいます。
「自分はダメなところばかりで、良い部分がない人間だ」などと、自分に劣等感を抱く傾向にあります。「自分を控えて相手を立てること」が美徳とされる日本人に多いようです。
パターン7:感情だけで判断する
「感情的決めつけ」は、事実に目を向けずに、自分の感情だけで物事を判断することです。
自分の感情を優先するため、「私はこの人が好きになれない」と思うと、「この人は悪い人に違いない」と思い込む傾向があります。また、小さな失敗も、すぐに「取り返しのつかないこと」として考えてしまいます。
パターン8:「しなければならない」と決めつける
「すべき思考」とは、「こうすべきだ」などの厳格なルールを、自分だけでなく他人にも負わせることです。もし、達成されない場合は怒りやストレスをおぼえてしまうのが特徴です。
「挨拶をしなければいけない」という考えが癖になっている人は、自分が挨拶できないと自己嫌悪に陥ります。それに加えて、相手が挨拶をしないと怒りをおぼえる傾向がみられます。
パターン9:1つのことで決めつける
「レッテル貼り」とは、偏った考えや思い込みによって、自分や他人に対して感情的な判断をくだすことです。
たった1つの要素で、その人全体を判断してしまうため、行動や振る舞いが大雑把な人に対しては、「人に対する思いやりがないに違いない」と、極端に視野の狭い考えになってしまいます。
パターン10:自分のせいと思い込む
「個人化」とは、自分の周りで起こる悪い出来事の原因は、すべて自分にあると思い込む考え方です。自分だけではなく、複数の人による仕事が失敗した場合でも、「自分のせいで駄目になった」と、必要以上に自分を責めてしまいます。
抱え込みすぎると、鬱症状を発症することもあります。
【ステップ2】マイナスな考え方の癖がもたらすリスクを知る

ここでは、ネガティブな考え方の癖によるリスクについて、解説します。
リスク1:ネガティブになる
先に述べた「行き過ぎた一般化」「心のフィルター」「マイナス化思考」「拡大解釈と過小評価」「個人化」によって、悲観的な考え方の癖が習慣化してしまいます。
ポジティブに考えることが難しくなり、苦しむ人もいます。悲観的な考え方は、気分が落ち込むだけでなく、不眠症やうつ病などの精神疾患のリスクが高まる恐れがあります。
リスク2:ストレスがたまる
「全か無か」「結論の飛躍」「感情的決めつけ」「すべき思考」「レッテル貼り」によって、柔軟性や融通に欠ける考え方の癖が習慣化します。
何をやっても現実と理想が合わないため、苦しみや怒りを抱き、ストレスが溜まります。結果的に、自律神経が乱れて、心身の不調を引き起こしやすくなることもあります。
【ステップ3】マイナス思考の癖を変えるための6つの方法

マイナス傾向にある考え方の癖について、変える方法を解説します。
1.自分の考え方の癖を認識する
考え方の癖を変えるには、自分の中にある考え方の癖について、特徴を知ることが大切です。
イライラする時や悩む時、その感情の前に浮かんだ考えを把握しましょう。
感情は考えの後に生じます。その考えの癖に気づき、「〇〇の考え方が良いが、それ以外でも良いこともある」と、少しずつ修正していくと、ネガティブな感情が生じづらくなります。
2.物事に対する反応を決めておく
ネガティブな考え方は、物事に対する反応をあらかじめ決めておくことで変えられます。ネガティブな感情を考え直せるように、シミュレーションしてみましょう。
電車で子どもが泣くと、「電車では静かにすべき」「泣かせる母親は失格」と思いイライラしますが、「母親も大変そうだ」「自分も子どものときは同じだったかもしれない」と考えるようにすると、ネガティブな感情が生じづらくなります。
3.他人を変えようとしない
相手の考えや行動が、「自分の思いどおりにできない」「共感できない」「自分と同じにならない」といった状況が、ストレスになることは誰にでもあります。
しかし、強引に相手の気持ちを変えようとすると、嫌われてしまいます。相手の考えや行動を受け入れた上で、ストレスに軽減するために、適度な距離を保つようにしましょう。
4.環境を変える
毎日同じ環境で同じ行動を繰り返していると、考え方もマンネリ化しやすくなります。
いつもと違う環境には、違う価値観があります。
いきなり大きく環境を変えなくても、「新しい習い事を始める」「通勤ルートを変えてみる」など、日常生活における変化からチャレンジしてみましょう。また、自分の理想を実現している人の側にいるのも良いでしょう。
5.深呼吸をする
ネガティブな考え方をしてしまう人には、深呼吸がおすすめです。
深呼吸をすると、気持ちも体も落ち着いて、ネガティブな考えやストレスを遠ざけることができます。
息はゆっくりと鼻から吸って、倍の時間をかけて口から吐きましょう。気持ちが落ち着くまで約10分間、深呼吸を続けてみましょう。
6.過去にこだわらない
多くの人は、過去に何かしら失敗しているでしょう。
しかし、過去の失敗や悪かったことを引きずって悩み続けても、ストレスになるだけで何も改善できません。いつまでも悩まずに割り切り、今できるパフォーマンスを考えましょう。
過去の失敗はマイナスと捉えずに、「失敗から学べた貴重な体験」とプラスに考えると、前向きになれます。
【ステップ4】マイナス思考をプラス思考に変える3つのコツ

不安や悩みなどのネガティブな気持ちを断ち切って、ポジティブになる方法について解説します。
1.考えすぎない
ネガティブな考え方をしてしまう人は、考えすぎて答えが見つからず、パニックになる傾向にあります。
何事も深く考えず、「悩んでも仕方がない」と割り切ることが大切です。
また、悩むだけでは何も始まらないため、行動したほうが早く解決できる場合もあります。フットワークの軽さも、ポジティブな考えにつながるでしょう。
2.成功体験を少しずつ積み重ねる
ネガティブな考え方をしてしまう人は、過去の失敗体験を引きずっている傾向にあります。
「どうせできない」とすぐに諦めず、始めは小さな目標を立てて、少しずつ成功体験を増やしていきましょう。
成功体験の積み重ねは、自信につながります。積極性が高まり、新しい体験へのやる気になるでしょう。
3.短所を長所におきかえる
自分の短所を気にしすぎてネガティブになるよりも、見方を変えて長所と考えられるようにしましょう。ネガティブな印象は、言い換えれば強みになります。
- 気が弱い→謙虚
- 自信がない→慎重
- 人見知り→観察力がある
長所だと思えることで、ポジティブな考え方ができるようになるでしょう。
まとめ
考え方を変えるには、ネガティブに考える癖を改善することが大切です。
改善にはさまざまな方法があるため、自分にあう方法を見つけて、少しずつ挑戦しましょう。成功すると自信に繋がり、ポジティブな考え方ができるようになります。
最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方は、考えすぎてなかなか行動できない人に、おすすめの書籍です。明治大学で、「明治一受けたい授業」に選ばれた教授が、世界中の研究機関で明らかになった「考えすぎない方法」を、全45のアクションで紹介しています。わかりやすく解説していますので、考え方を変えたい人は、ぜひ一読してみてください。
『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方|サンクチュアリ出版』はこちら
この記事は、“最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方” 堀田秀吾(著)の新刊コラムです。
(画像提供:iStock.com/NanoStockk/chachamal/tadamichi/marrio31/chachamal)