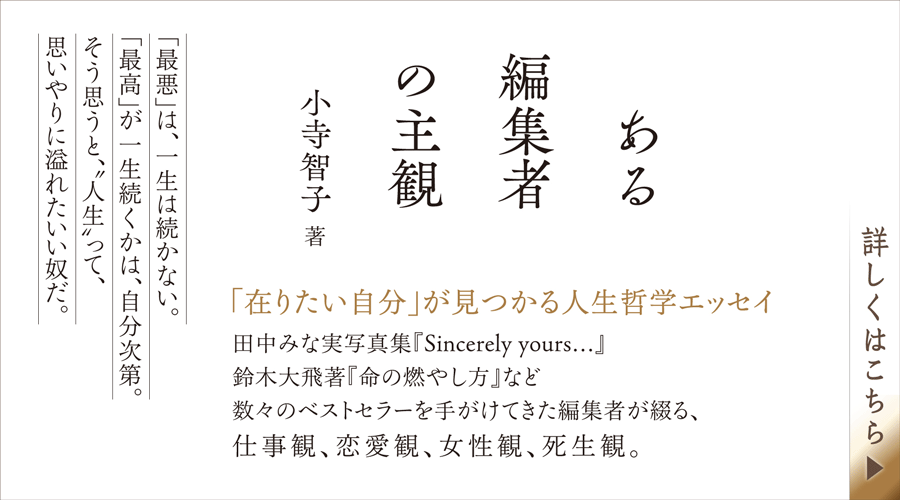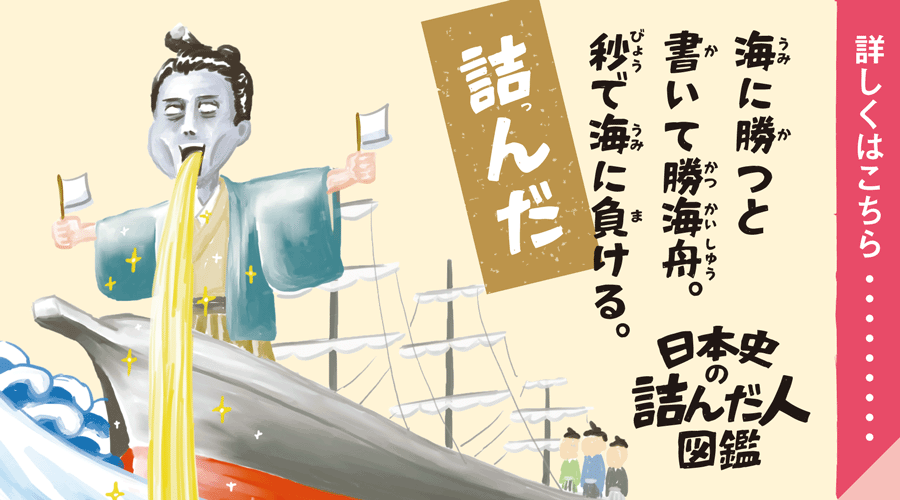旅行記『インドなんて二度と行くかボケ!…でもまた行きたいかも』で作家デビュー。その“ばかばかしくて笑える”文章に中毒者が続出。ネットラジオ「さくら通信」でも笑いを届けながらも、自らを「根暗」「六流作家」と評する、さくら剛氏の実像に迫った。
「小さなころから根暗で、ひとり遊びばっかりしていたんです」 ややはにかんだ表情を浮かべつつ、穏やかに話すさくらさんは、旅行記の文章通りの“飾らない”印象の人である。 自然豊かな静岡県浜松市で生まれ育つも、昔からインドア派であり、友達も少なかったという。 本やマンガ、テレビ、ゲーム……。学校が終わるとまっすぐ家に帰り、ほとんど家で過ごした。 一方で、“お笑い”も好きで、ギャグマンガやバラエティ番組にぞっこんだった。 その他に熱中したのが、プロレス番組と格闘技系のマンガ。こうした傾向の裏には、ひとつの隠された理由があった。 ゲームもまた、異世界への扉となる存在だった。そして中学生で傾倒したのが、『三国志』のシミュレーションゲームである。当時、他のソフトの約3倍もの値段がするにも関わらず、小遣いを溜めて購入し、没頭した。 こうして中学までは変わらぬインドア生活を続けたが、高校に入り、さくらさんは思い切った行動に出た。 高校、大学と格闘技を続け、プロレスラーにこそなれなかったが、身体は丈夫になった。社会で必要な上下関係や礼儀作法も学ぶことができた。 こうして不完全燃焼な青春時代を過ごし、悶々とする中で、胸の内に秘めし別の世界へのあこがれが、徐々に思考を占拠していった。 コミュニケーションが苦手なさくらさんが、お笑いを目指し、しゃべりの世界で勝負するという選択に、違和感を覚える人もいるかもしれない。しかしお笑い芸人の多くは、実は根暗であるという。 養成所では、独自のものの見方が一定の評価を受けた。笑いのセンスにも自分なりに自信があった。 20代前半の青年は、東京のビル群の中でふたたび進むべき道を見失い、四畳半の一室で途方に暮れていた。 さくらさんの一条の光となったのは、芸の幅を広げようと通っていた、シナリオスクールだった。 “お笑い芸人でなくてもいい。人をくすっと笑わせるような、文章の書き手になろう” とはいえ、なにか当てがあるわけではなかった。生活を安定させるため、ひとまず派遣会社に登録。日々仕事をこなしつつ、時間ができればホームページを更新するにとどまっていた。 そんな生活を大きく変えることになったのは、当時付き合っていた彼女との別れだった。 こうしてまた、目の前には別世界が現れた。しかしこれまでと違うのは、そこはあこがれの世界ではなく、試練の世界であるということだった。 人生初の海外旅行を決行するために、仕事を辞めた。 ただ、帰国後にいきなり出版が決まったわけではない。陽の目を見るまでは、そこから4年の月日を要している。 シフトに融通のきくアルバイトなどをこなしつつ、インド旅行の旅行記をいくつかに分けてホームページにアップすることを当面の目標とした。 なお、旅行記を書くにあたり、事前にひとつ決めていたことがあったという。それは、ありのままの「みっともない自分」をさらけ出すこと。 結果的にそれが、表現者としての大きな転機となった。 また、旅行記を書きあげる中で、自分の作家としての軸がはっきりと見えてきた。 こうして旅行記を書き綴っていた間でも、現実とは向き合わねばならなかった。再び派遣社員として登録し、ホテルマンや電話でのカスタマーサポート、肉体労働までさまざまな仕事をこなした。給料は安く、生活は厳しかったが、「自分を変える、彼女を見返す」という思いを強く持ち、なんとか書き続けた。そして、出来上がった部分の原稿を印刷し、出版社に直接売り込みにも行った。 ただ、そんな生活が4年目に入るころには、どうしようもない焦りにとらわれたという。 それでも、さくらさんはあがき続けた。かっこうをつけず、必死になってやれることをやった。 転機となったのは、とある出版社がホームページを対象とした作品募集の企画を行い、藁にも縋る思いでそこにエントリーしたことだった。出版社の選定後、作品に対する読者投票を行い、規定以上の票が集まれば本として出版する、というチャレンジ企画に、さくらさんの旅行記は見事、合格した。 そして、ちょうど30歳になった年、さくらさんはついに、作家という肩書を手に入れ、“何物でもない時期”から脱却できたのだった。 デビュー作が好評だったことで、続編の執筆はすぐに決まった。そこでまたさくらさんは、旅に出ることになった。今度は、南アフリカから中国までの長旅だった。その顛末は著作に譲るとして、さまざまな苦難の末にたどり着いた中国で、さくらさんはふと、大好きな三国志の遺跡巡りを思い立った。 こうして、有名史跡からあやしい史跡まで、これでもかと詰め込んだ珍道中記『三国志男』が誕生したのだった。 そこからは、コンスタントに本を執筆。さくらさん独自の視点と、小気味よい文体、そしてばかばかしくてくすっと笑える比喩や身近なたとえ話には、デビュー作から一定のファンが付いていた。 そして、旅行記の出版が、7冊を数えるまでになったころ。そこでさくらさんは、自らの作家としての枠を広げるため、新たな世界へのチャレンジを行った。 「旅行記を読んでいただけるとわかるのですが、そもそも根暗な人間が、海外旅行が好きなわけはありません(笑い)。そろそろ、新しい何かを見つけたかった。そんなとき、編集者さんとの打ち合わせの中でアイデアが出て、科学の世界を書いてみようと思いました。科学のことをまったく知らない読者でもわかるように、というコンセプトでしたが、そもそも自分が科学についてほとんど知らない。だからひたすら本を読み、3か月かけて勉強してから、執筆にかかりました。勉強してわかったのですが、例えば相対性理論などは非常にSFチックで、星新一の作品とニュアンスが似ています。そうした身近なイメージを思い浮かべつつ、中学生でもわかるような例え話や置き換えをしながら、文章を作っていきました」 光の性質を“美少女アイドルグループのコンサートのワンシーン”で解説したり、一般相対性理論を“パンチラが見えるか見えないか”で説明したり……。『感じる科学』は、そんなばかばかしさに満ち、気楽に読んでいくといつの間にか科学の本質に触れることができるという仕掛けになっている。 新たな分野の開拓にも成功し、仕事にもいよいよ脂がのってきた、2013年。アニメ化を前提として作品を書く、という大きなプロジェクトが舞い込んだ。 母親が、うつ病を発症した。 高齢でうつ病を発症すると、その進行はとても早く、認知症に近い症状が出ることが多い。あっという間に理性を失っていく母、そしてその後を追う父を間近で見た衝撃は、計り知れなかった。 そして、さくらさんもまた、うつ病にかかった。 「一人っ子で、僕しか面倒をみる人はいませんから、選択の余地はありませんでした。仕事と両親の介護をなんとか両立させるべく、必死にやっていたのですが、そこで自分もまた次第に生きる気力を失ってしまいました。そうして僕も動けなくなり、介護ができる人間がいなくなって、両親は精神病棟に入院することになりました。病院に任せることで一息ついて、そこで初めて自分も心を病んでいることに気づいたんです」 動けない、何もできない日々から、病院に通って少しずつ回復し、ようやく仕事ができそうなコンディションまで来た時点で、いくつもの仕事を放り投げており、多くの人に迷惑をかけてしまっていた。 幸い、両親はその後、病状が回復し、再び二人で生活を営めるようにまでなった。しかしその頃には、さくらさんの人間関係はずいぶん損なわれてしまっていた。 「自分としてはまた一からのスタートでした。一度失った信頼はそう簡単には戻りません。作家廃業も覚悟しました」 そんなさくらさんを精神的に支えたのは、やはり笑いだったという。 また、もうひとつ、さくらさんの救いとなったものがあった。それは、読者からの手紙や、インターネットラジオのリスナーからの投稿だった。 自身の経験と、ファンの声。 「僕は思うんです。笑いというのは、精神的な救いであると。だからこれからも、やはり笑いを自分の軸として、ばかばかしい、おもしろいものを人に届けていきたい。それで一人でも、二人でも、気持ちが楽になる人がいるなら、なによりです。それが自分が作家になった、ひとつの意味だと考えています」 (取材/文 國天俊治)
ペンネームの「さくら」は、尊敬する同郷のエッセイスト、さくらももこさんから拝借。旅行作家として世に出て以来、偏愛する「三国志」の史跡100か所以上を巡って記した『三国志男』など旅行記の執筆を続ける一方で、物理や科学の世界を誰もがわかるように解説した『感じる科学』を始め学術系の本も執筆している。
その他に、インターネットラジオで7年続く長寿番組「さくら通信」などの人気コンテンツも抱え、現在もマルチに活躍を続ける。そんな人気作家の、これまでの歩みを追った。
「ひとりっ子だったせいか、小さなころからとにかくひとりで行動することが多かったですね。母によると、幼少期には、庭の小さな砂場で朝から晩までもくもくと何かやっていたそうです。そんな暮らしをしていたので、幼稚園や小学校でも友達の作り方がわからなかった。元来ひとりが苦にならないので、よけいに自分の世界に籠る、という感じでした」
「読書をするときには、家にあった小さな机の下に潜り込んでいました。狭いところで読むほうが、その世界に没頭できたから」
お気に入りの作家は、星新一。現実から異世界に飛ぶような感覚がたまらなかった。
「特にハマった記憶があるのは、『ついでにとんちんかん』というマンガです。小学生むけでわかりやすくも下品すぎず、ボケとツッコミが高度に成立していて、今見ると構成もすごく緻密であることがわかります。この時期に吸収したお笑いの要素が、現在の僕のギャグの原点になっていると感じます」
「当時、現実世界の僕は、友達も少なく、身体も貧弱。だからこそ、ウケて人気者になった自分、強くなった自分、という“違う世界の自分”へのあこがれを、いろいろなものに投影していたのかもしれません」
「ゲームが入り口となって武将の名前を覚え、詳しいストーリーが知りたくなってマンガを読み、最後は本です。吉川英治の『三国志演義』を熟読しました」
「少林寺拳法部に入りました。プロレスラーにあこがれていたけれど、プロレス部がなかったので、とりあえず格闘技を始めたんです。今まで抱え込んできた“あこがれ”のひとつに対し、初めて行動を起こしたんですね。どうにか自分を変えたかったのだと思います」
しかしそれでも、元来の“根暗”は変わらなかったという。
「例えば大学の飲み会があっても、みんなの輪の中には入っていけません。張り付いたような笑みを浮かべながら部屋の隅でひとり座って過ごすことになります。最初こそ気を使ってくれる人がいるけれど、中盤以降は話し相手がいなくなるわけです。それでも場をしらけさせるのが怖くて、帰るに帰れない……。そこで行っていたのが、人間観察です。あの人はどういう心情なのか、背景にはどんな人間関係があるのか。表から見えているものだけではなく、その裏にある物事を考えながら時間をつぶしていました。その経験や思考法というのが、作家としての素養となったように思います。まあ、ポジティブに言えば、ですが(笑い)」
さくらさんは、4年次で大学を中退。次なる世界へと邁進することにした。
「お笑い芸人を目指すことに決めました。そのタイミングで、大学のあった名古屋から東京へと引っ越しました。東京に行けば新たな世界が待っていそうな気がしたんですよね。そこから、アルバイトをしながらお笑いの養成所に通い実力を磨く、という生活をしていました」
「明石家さんまさんなど、本当に明るくてかつおもしろい天才はいるにはいますが、ほんの一握りです。お笑いでおもしろいことを言うには、まず他と違った独自の視点がいる。それを発想するためには、ひとりでうじうじと物事の裏を考え、自分の世界に籠ることが必要ですから、やはり根暗である人のほうが向いているんです」
しかし、そう簡単に芽が出るほどお笑い界は甘くない。
くわえて、自らをがんがん売り込みに行くような度胸も根性もなかった。成功するまで続けるという覚悟も根気強さも、持ち合わせていなかった。だから早々に、挫折した。引きこもった。
「学校の宿題として文章を書くわけですが、それが自分としてはなかなかおもしろく仕上がることがありました。提出するだけではもったいない、多くの人に読んでもらって感想を聞きたい。そう考えて、自分のホームページを開設しました」
そのホームページに対する読者の反応が存外によかったことで、さくらさんは人生の新たな方向性を見出した。
「海外旅行が好きな人で、別れの原因も、海外で暮らしてみたいから、というもの。当時の僕には海外など別世界でしかなく、一緒に行くなどありえませんでした。そうして、怖くて日本から出られない僕が、ちっぽけに、頼りなく見えたんだと思います。こっぴどく振られて、傷つきましたね」
ショック状態から回復するにつれ湧き上がってきたのが、悔しさと怒り、そして焦りだった。
「自分だって海外くらい行ける、それをどうにか彼女に見せつけてやりたいという思いがまずありました。一方で、このままではいけない、自らを追い込み、根本的に変える必要があるという焦りも感じていました。逃げ場のないところに飛び込んでいけば、ダメな自分を変えられる気がしたんです」
「どうせやるなら、観光ではなくハードな旅行にしよう。そう考えたときに、バックパッカーの総本山というイメージのあるインドが思い浮かんだんです。失恋により自暴自棄になっていたこともあり、いきなり“ラスボス”と戦ってやろうという気持ちでした」
そして1か月間にわたり、バックパッカーとしてインドを放浪した。その顛末を書いたのが、デビュー作となった『インドなんて二度と行くかボケ!…でもまた行きたいかも』である。
「“海外旅行をやり遂げた自分”を引っ提げて、意気揚々と帰国したわけですが、当然、彼女がやり直そうと言ってくることもなく、語学ができるようになったわけでもなく、置かれている状況に何の変化もありませんでした。ただ、自分の中に、ある種の覚悟ができたような感覚はありました」
「これまでいくつか文章を発表してきた中で、かっこうをつけて書いたものよりも、自虐ネタのほうがウケがいいことはわかっていました。ただ、プライドもあって、どうしてもしゃれた文章を書こうとしてしまっていた。思えば私生活でもそうで、おしゃれに見える服で身を包み、歌がうまいと褒められるためにひとりカラオケで練習を重ねるようなこともしていました。自分に自信がないから、少しでも大きく見せたかったんですね。ただ、本当の自分は根暗でちっぽけ。海外でも当然それは変わらず、旅行ブログなどにありがちな、『今日は現地の子どもと交流しました!』、『地元の有名カフェでスイーツを補給』などといったきらきらしたことは一切できなかった。今でいう、インスタ映えするような場所にも行ってないし、おしゃれな写真だって撮っていない。だったらいっそ、真逆に振って、情けない、四苦八苦している自分を見て笑ってもらったほうがいいんじゃないかと考えたんです」
旅行記は口コミで次第に話題となり、有名タレントが自分のブログで紹介してくれるほどにまで広まっていった。
「小細工をするより、ありのままのほうが受け入れてもらえる。その体験が、自分を変えました。まず、私生活で見栄を張るのを一切やめましたね。それまで着ていた、周囲を威嚇するような派手な服やアクセサリーも全部捨てました(笑い)」
「やはり自分のベースはお笑いなのだと改めて気づきました。まずは、ばかばかしい文章で笑って欲しい。それが下地で、そこにその時々の題材をつけていくというやり方が、一番いいのではないかと。お笑い+旅行、お笑い+三国志、お笑い+科学、といった感じです。今でもお笑いプラスアルファの組み合わせを探し続けています」
お笑い芸人の時とは違い、諦めようとは思わなかった。もうこれでダメなら人生それまでだ、という覚悟があった。
「膨大な数の本が出版され、ずらりと本屋に並んでいるけれど、自分はたった一冊の著作すらない。30歳が近づくにつれ、同世代の人々はひとつの会社に腰を落ち着け、安定した生活をしているのに、自分はいったい何をやっているのかという焦りはありました。この“何者でもない時期”が、精神的にもっともきつかったですね」
「もともとホームページに読者がそれなりについていたのが大きかったです。これまで積み上げてきたことは無駄ではなかったな、と心底思いました」
「三国志の本は、旅のお供に持ってきていました。本に登場する戦場や、墓、城などの史跡に実際に行き、そこでその場所が出てくるシーンを読んだら、臨場感があるのではないかと思いました。最初は軽い気持ちだったのですが、せっかくだから、もう一生来ないかもしれないからと思うと、バスで1日かかるような場所にまで足を伸ばし、ずいぶん時間がかかりました。そして気づけば、100か所以上の史跡を巡っていたんですね」
そんなファンの後押しを受け、二作目の発売以降は、専業作家として活動することができるようになった。
それが、旅行記以外の初の著作となった『感じる科学』だった。
「ギャグを書くときは、下品にならないように、人が不快にならないように、人を傷つけないように、ということをいつも慎重に見極めるようにしています」
「これを成功させれば、作家として新たな境地に行ける」
そう意気込んで、全力を挙げて取り組んでいた矢先のことだった。
そして、それを介護していた父もまた、うつ病となり、床に臥せってしまった。
こつこつと山を登り、ようやくひとつの頂が見えた。そこに手を伸ばした瞬間、足場が一気に崩れ、闇深い谷底へと落下……。そんな経験だった。
「仕事を再開してすぐ、両親にうつ病再発の気配が見えたことがありました。その時には、またあの地獄が始まるのか、と僕も精神的に追い詰められました。そこで、気分転換にお笑いのライブに出かけたんです。本当にばかばかしく、中身のない内容で、声をあげて笑いました。そして終わってみると、心にかかりつつあった霧が晴れ、ずいぶん気分が楽になったんです。そこで精神的に持ち直したことで、再び自分がうつ病になるのを避けられたと思います」
「自殺しようと思っていたけれど、さくらさんの本を読んで、ばかばかしくなって止めました。死にたくなった夜、『さくら通信』を聞いて何も考えず笑ったら、気持ちが落ち着きました……。こうした声は、今でもけっこう届くんです」
それは、さくらさんがこれまでやってきたことが、決して無意味ではなかったという証明でもあった。







困ったココロ
さくら剛(著)
1,300円+税
![]()
![]()
![]()
![]()
20代男女の約7割が“非リア充民”?
バカバカしすぎて笑いが止まらない!
“非リア充”の作家さくら剛による
“非リア充”の人たちのための心理学の本。
数々の心理学から“人の心の本質”を学び、
友だち、恋人、仕事などに恵まれた「充実人生」をめざします。