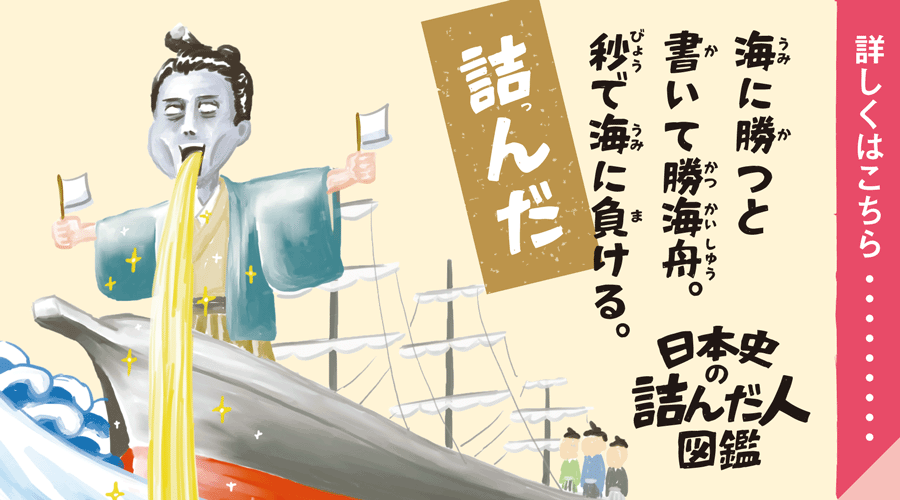2017年に日本で翻訳出版されると同時に話題となり、35万部を超えるベストセラーとなった絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』。子どもたちの心をとらえて離さないオモシロ絵本はどのように誕生したのか。著者であるビル・コッターさんに「絵本作家になるまで」の半生を聞いた。
目次
とにかく「絵を描くこと」が大好きだった少年時代

アメリカ中西部、オハイオ州のクリーブランドで生まれ、個性豊かな3人きょうだいの真ん中で伸び伸びと育った絵本作家のビル・コッターさん。幼少期について尋ねると「とにかく絵を描くことがすべてだった!」という言葉がすぐに飛び出した。小さなころから絵を描いたり、ピアノを演奏したりすることが大好きで、主にアートや音楽方面でその才能を発揮していたという。
「わが家は両親の教育方針で、1日30分までしかテレビが観られなかったんです。テレビ見放題の友人がホント、うらやましかったな。テレビを観ない分、毎日時間はたっぷりあったので暇さえあれば大好きな絵を描くことに没頭していましたね」と子ども時代を振り返る。
息子の特別な「才能」に最初に気づいたのは、コッターさんの母親だった。ビル少年が楽しみにしている学校の美術の時間は週1回、短時間のみ。授業だけでは物足りない息子が学校外のアートスクールに通えるよう、取り計らってくれた。毎週土曜日になると母親にスクールまで送ってもらい、絵画やモノ作り、ギターやピアノなど、朝から晩まで様々な芸術的レッスンを受ける日々だったという。
「もともと母も絵画が趣味で、アーティスティックなタイプ。僕の好きなことや得意分野をすごく理解してくれていて、芸術方面に進めるように背中を押してくれた。母の物理的・精神的なサポートがあったからこそ、今があると思っています」
美大を卒業し、いざニューヨークへ

アートに対する情熱を持ち続けたコッターさんは、メリーランド州・ボルティモアにある全米最古のビジュアル・アート系専門大学、メリーランド・インスティテュート・カレッジ・オブ・アート(MICA)に進学。彫刻家のジェフ・クーンズをはじめ、数々の著名アーティストを輩出する名門美術大学でアートを学んだ。
「1826年に創立された歴史のある美大なんですが、そこで基本的な絵画のスキルを磨きました。技術だけでなく、“自分の絵に魂を注ぎ込む”ことも学びましたね。大学時代はとにかく課題をこなすことに必死で、絵本作家になりたいという思いはまだ芽生えていませんでした。卒業後の進路についてもまるっきりノープラン。友人2人と一緒に『とりあえず、大都会に出てみるか!』みたいな、そんな軽いノリで大学卒業後にふらっとニューヨークへ引っ越したんです」
子どもたちとのコミュニケーションが絵本のアイデアに

http://cotterillustration.squarespace.com/ より引用
実はコッターさんの「絵本作家への第一歩」はすべて、このニューヨーク時代に詰まっている。
一つ目の転機は、アートを子どもたちに教える職に就いたこと。トライベッカにある「チャーチストリート・スクール・フォー・ミュージック・アンド・アート」というアートと音楽の専門スクールでの経験が、初めての絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』(原題『Don’t Push The Button!』)誕生のきっかけとなった。
「午前中は幼児向けのデイケアプログラム、午後は小学生向けのアフタースクールでアートと音楽を5年間、教えていました。子どもたちと接していてすぐに理解したのは、彼らは一つのことになかなか集中できないってこと。絵本を読み聞かせていてもつまらないとすぐに騒ぎ出すし、長い間じっと座っていられない」
子どもたちに絵本を読み聞かせるうち、「キャラクターが登場して、聞き手に直接語りかけるスタイルの絵本」に、人気が集中していることに気付いた。「ほかにも絵本にタッチしたり、シェイクしたり。何かしらインタラクティブな要素がある絵本だと、飽きずに楽しんでくれることが分かったんです」
紫色の愉快なモンスター「ラリー」の誕生

(http://cotterillustration.squarespace.com/ より引用)
コッターさんの初めての絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』は、こんな宣言から始まる。
「このえほんには 1つだけルールがあるよ/それは、このボタンをおしちゃダメということ」。しかし、ダメと言われるとどうしても押したくなるのが人間の性。いたずら好きのモンスターがあの手この手でボタンを押すよう誘惑し、読者である子どもたちは思わず押してしまうーー。絵本を介して大人と子どもの間に楽しいコミュニケーションが生まれる、まさに「インタラクティブ」な絵本だといえるだろう。
物語の主役である紫色のモンスター「ラリー」は、アートスクールの教師時代に考えついたものだ。「何か子どもたちに喜ばれるような親しみやすいキャラクターを作りたい」と模索するなか、影響を受けたのは『セサミ・ストリート』の放送作家・アニメーターとしても有名なアメリカの絵本作家、モー・ウィレムズ。彼が手がけた『ぞうさん ぶたさん』シリーズに登場する象のジェラルドや豚のピギーのような、カジュアルな口調で読者に語りかけるようなキャラクターを作り出したかったという。
「ほかにも、1985年から1995年まで全米の新聞に連載されていた漫画『カルビンとホッブス』にもインスパイアされています。主人公のカルビン少年は空想好きで、学校嫌い。すぐに森へフラフラと遊びに行ってしまう落ち着きのないトラブルメーカーです。そんなキャラクターの造形は、決して“いい子”ではないラリーにも重なる部分があるかもしれません」
実はラリーは当初、現在のようなポップな姿ではなく、もっと写実的な絵で描かれていた。しかし、スクールで3〜4歳の子どもたちに試しに見せてみたところ、すこぶる不評だったそう。「その場ですぐに描き直したら、『これすごいよ!』と小さな子たちから大反響で。それから現在のようなスタイルになりました」
「隣人が出版エージェント」という幸運も

こうして、処女作『ぜったいに おしちゃダメ?』は、子どもたちの意見を取り入れて磨かれていったわけだが、作家デビューの第二のハードルである「出版社との契約」は、どのようにクリアしたのだろうか。
「この話をするとみんな驚くんですけど、住んでいたアパートメントの階下に、たまたま出版エージェントが住んでいたんです。なんだか、すごくニューヨークっぽい話でしょう(笑)」。一般的にアメリカでは、作家は出版エージェントと契約し、エージェントが作家の代理人として出版社と交渉する。コッターさんが大学卒業後に友人2人と引っ越したアパートメントの隣人が、偶然にも出版エージェンシーで働く女性だったのだ。
「引っ越した夜に、ヒッピーみたいなロングスカートを履いた女性がワインを持って訪ねてきたんです。『私、出版エージェンシーで働いていて、イラストレーターのエージェントなんかをしているの。あなたは?』って聞かれたから、『まさに……それが僕がこれからやりたい仕事だよ!』って答えて。美大時代に作ったポートフォリオを見てもらって、そこから絵本の制作についても色々とアドバイスをもらうようになりました」
そして、ニューヨークでの教師生活も3年目に突入したある日。彼女に『ぜったいに おしちゃダメ?』の原型を見せたところ、「これだよ! これならイケる!」と、ようやく太鼓判を押してくれたという。「彼女がモノクロで作ったダミーの絵本を8社ほどに送ってくれて、オファーが来たのがシカゴの出版社、ソースブックス (Sourcebooks Jabberwocky)でした」
コッターさんが絵本を出版したいきさつを知るほどに、絵本作家になるべくしてなったような不思議さを感じてしまう。彼自身も「運命の幸運な巡り合わせ、“セレンディピティー”を感じる」と強くうなずく。「作家としてブレイクするには、努力だけでなくクレイジー・ラックーー強運も必要かも。たとえば、階下に住む隣人が偶然出版エージェントだった、みたいなね」と笑う。
故郷に戻り、次々と絵本の新作手がける

(http://cotterillustration.squarespace.com/ より引用)
『ぜったいに おしちゃダメ?』がヒットし、念願の絵本作家としてデビューを果たした今は、両親や兄の家族などが暮らす故郷のオハイオ州・クリーブランドで執筆活動を続けている。
2016年には『ぜったいに さわっちゃダメ?』(原題『Don’t Touch This Book!』、2019年1月にサンクチュアリ出版から日本版を出版)、2017年には『Don’t Push The Button! A Chiristmas Adventure』など、「ラリー」が登場する絵本の続編を中心に、これまで7冊の絵本を手がけてきた。アートスクールの子どもたちの代わりに、彼の「最初の読者」として意見をくれるのは、近所に住む小さな甥っ子や姪っ子たちだ。
「絵本作家は天職?」との問いには、「小さなころから大好きだった絵を描くことが仕事になり、フリーランスの絵本作家として生活できている今が最高に幸せ。この生活をできる限りキープして、作品を作り続けていきたい」と穏やかに答える。ニューヨークでの暮らしとは一変し、クリーブランドでの日常は至極のんびりとしたものだ。「一日の始まりには、まずコーヒーをゆっくり飲んで……。その後は美術館に行ったり、音楽や異文化、様々なアーティストたちから、絵本のインスピレーションを得ています」
子どもたちの興味と親の好み、自らの作家性ーーすべてをかなえる絵本

(https://twitter.com/CotterBooks/status/908023874457145345 より引用)
自らの感性のおもむくまま、自由に絵本を作っているようなイメージもあるコッターさんだが、実はとてもマーケティング的な思考を持った作家でもある。
たとえば、モンスターのラリーの体はピンクでもブルーでもなく紫色。「アートスクールでは男の子、女の子のどちらも紫色が好きだったから」と、ジェンダーに関係なく人気がある色を選んだ。
そして、最も大切にしているのは「子どもたちが何をつまらないと感じ、何を面白いと思うのか。どんなスタイルの絵本が興味を惹き付けるのか」ということだ。「とはいえ、実際に絵本を買ったり、読み聞かせするのは大人ですよね。彼らが子どもたちとコミュニーションを取りやすい絵本であるという視点も大事。大人も楽しめる絵本であることを意識しています」
「子どもや親が絵本に求めることと、アーティストとしての表現がぶつかることはない?」と聞くと、にっこり笑ってさらさらと「ベン図」を書き出した。サークルを3つ描きながら、「まず子どもの興味、次に親の好み、最後に自分のやりたいことを考える。そして、この3つが重なる部分を探せばいいんです」と説明。「新しい本を作るときは、何か必ず新しい要素を入れなければいけない大変さがある。でも、この基本的な軸だけは常にブレないように注意しています」
絵本作家になりたいなら「1つのアイデアに固執しない」こと

絵本作家として有名になってからは、「“私も絵本を出版したいのだけど、どうしたらいいか”と、作家志望の人たちから聞かれることが多くなった」というコッターさん。作品を実際に見せてもらうと、「子どもが読んでも楽しめないんじゃないかな」と思うことが多々あるそうだ。
「自分が描きたいものを描くことも大事ですが、子どもの年齢に合わせて作られていないものが多いと感じます。ターゲットとする子どもたちの年齢はいくつくらいなのか、どんな内容なら興味を持ってもらえるかをまずは考えてみてほしい」
また、いいアイデアを一度思いつくとそれに固執してしまいがちだが、「アイデアは多ければ多いほどいい」とアドバイスする。「たとえば釣りをするときは、エサを1つ付けたからといって必ず魚が釣れるわけではないですよね。釣れた!と思っても、長靴とかビンが釣れてしまうこともある。何年もかけて1つのアイデアを大事に温め続けるよりも、思い浮かぶ限りのアイデアをどんどん出して、実際に子どもたちが気に入ってくれるのかどうか、試してみるほうがいいと思います」
絵本の次のステップ「児童書」にも挑戦したい

「新作の予定は?」と聞くと、「サンクチュアリ出版さんと日本の読者に向けてスペシャルな絵本を企画しています。内容はまだ……シークレットです(笑)」と答えてくれた。
「個人的には、子どもたちが絵本を卒業した後に読むチャプターブック(章立てのある児童書。7〜10歳くらいが対象)に挑戦してみたい」と語る。甥っ子や姪っ子たちが小学生になったときに、絵がなくても楽しめる少し長めの児童書を作ってみたいそう。「実は先日、兄の奥さんに『子どもたちが成長したら、これおじさんが書いたんだよ!って学校で自慢できるような本を作ってほしい』って注文を受けたばかりなんですよ」
「本は一生を通して付き合うものだから、読書嫌いになってしまうのはもったいない。そのためには人生のステージに合った本選びが重要です。『ハリー・ポッター』シリーズほどストーリーが長くなく、本を読む習慣のない子でも楽しめる……ロアルド・ダールが書いた『チョコレート工場の秘密』や『おばけ桃が行く』のようなイメージかな。将来的には絵本と『ハリー・ポッター』の間に位置するような読みやすい本を作ってみたいですね」
「人は誰でもそれぞれの特技を生かせば、小さなことでも世の中に貢献できるはず。僕の場合、それは絵本を作ること」と語るコッターさん。「絵本の読み聞かせは子どもたちの心に影響を与える大切な時間。僕の本を読むとき、大人は思い切って“silly”(おバカさん)になってみてください。子どもたちはきっと大笑いしてくれるはず。絵本を介した親子のコミュニケーションを楽しんでほしいですね」
取材・文/澤田 聡子
取材撮影/榊 智朗
ビル・コッター 絵本作家。 アメリカ・オハイオ州クリーブランド生まれ。 幼少期からアートスクールに通い、アートと音楽にあふれた環境で成長する。 ボルティモアの美術大学、メリーランド・インスティテュート・カレッジ・オブ・アート(MICA)卒業後、ニューヨークのアートスクール「チャーチストリート・スクール・フォー・ミュージック・アンド・アート」に教師として就職。 子どもたちにアートと音楽を教えながら作った初めての絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』がベストセラーに。 現在は故郷のクリーブランド在住。 著書に続編『ぜったいに さわっちゃダメ?』(サンクチュアリ出版)、『Don't Push The Button! A Chiristmas Adventure』『Don't Push The Button! A Halloween Treat』(Sourcebooks Jabberwocky)など


ぜったいに おしちゃダメ?
ビル・コッター(著)
定価:1,050円(税込1,155円)
この絵本にはたった1つだけルールがあります。
それは「このボタンを押しちゃダメ」ということ。



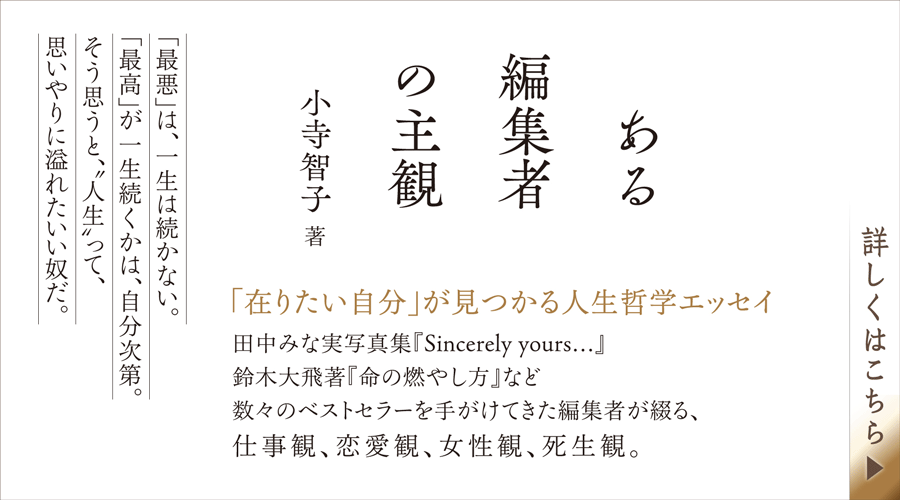
 ビル・コッター
絵本作家。
アメリカ・オハイオ州クリーブランド生まれ。
幼少期からアートスクールに通い、アートと音楽にあふれた環境で成長する。
ボルティモアの美術大学、メリーランド・インスティテュート・カレッジ・オブ・アート(MICA)卒業後、ニューヨークのアートスクール「チャーチストリート・スクール・フォー・ミュージック・アンド・アート」に教師として就職。
子どもたちにアートと音楽を教えながら作った初めての絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』がベストセラーに。
現在は故郷のクリーブランド在住。
著書に続編『ぜったいに さわっちゃダメ?』(サンクチュアリ出版)、『Don't Push The Button! A Chiristmas Adventure』『Don't Push The Button! A Halloween Treat』(Sourcebooks Jabberwocky)など
ビル・コッター
絵本作家。
アメリカ・オハイオ州クリーブランド生まれ。
幼少期からアートスクールに通い、アートと音楽にあふれた環境で成長する。
ボルティモアの美術大学、メリーランド・インスティテュート・カレッジ・オブ・アート(MICA)卒業後、ニューヨークのアートスクール「チャーチストリート・スクール・フォー・ミュージック・アンド・アート」に教師として就職。
子どもたちにアートと音楽を教えながら作った初めての絵本『ぜったいに おしちゃダメ?』がベストセラーに。
現在は故郷のクリーブランド在住。
著書に続編『ぜったいに さわっちゃダメ?』(サンクチュアリ出版)、『Don't Push The Button! A Chiristmas Adventure』『Don't Push The Button! A Halloween Treat』(Sourcebooks Jabberwocky)など