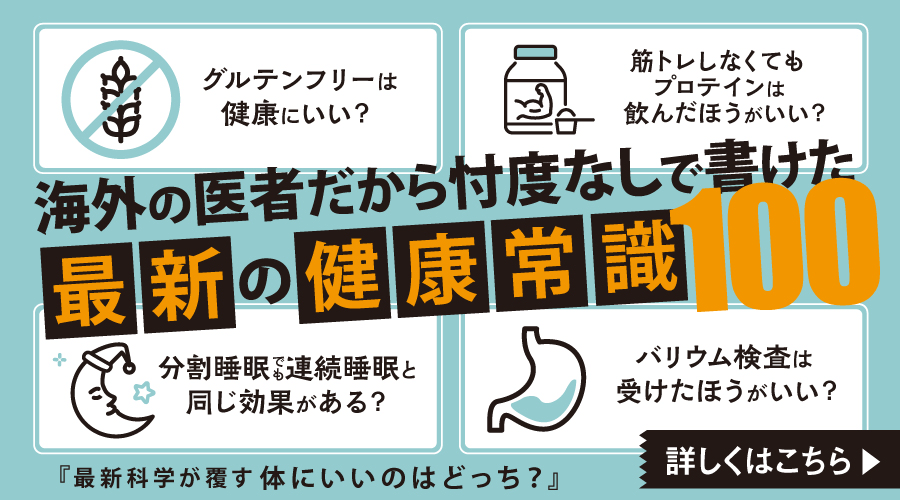「僕はね、自分を占い師と名乗ったことはないんですよ」。では彼はいったい、何者なんだろう。 「占星術は僕のもっとも大きなフィールドのひとつではありますが、いわゆる“占い”だけではなく、古代から連綿と続く占星術という存在をアカデミックな観点から研究し、大学で教鞭を取ってもいます。その他に、大学時代からユング心理学の研究を続けてきていて、今でも研究者としてユングに関する論文を発表したり、シンポジウムに出たりしています。また、著書に関しては、占いの本と同じくらいの数、翻訳を手掛けて出版しているんですよ」 学者、研究家、翻訳家、そしてメディアに登場する際のエンターテイナーとしての顔……。 出身は、京都。母は、1964年に日本で初めてとなる「着付け教室」を開校した才女で、父も和装小物を扱う事業をしていた。そんな“生粋の京都人”たちの間に生まれた鏡さんは、古の都を遊び場として幼少期を過ごした。小さいころはとても内気で、友達と遊ぶより本ばかり読んで空想の世界に浸っていたそう。 当時はまだまだ少ない女性経営者であった母は、華やかな雰囲気と負けん気の強さを併せ持った女傑で、鏡さんに多大な影響を与えた。 占いの世界に通じる“魔法の扉”は、小さいころから目にしていたよう。 古の都・京都もまた、その不可思議な“魔力”で鏡さんの心を捉えた。 ただ、魔法の世界の住人でいられたのは、小学校低学年までだった。 8歳のころ、父がとある借金の保証人になったことがきっかけで、その商いが徐々に低迷。子ども心にもわかるほど、家計が悪化していった。一方、幸いにも母の活躍はめざましいものがあった。 離婚後、母と妹との3人の暮らしが始まった。 「占いそのものというよりも、魔女が描かれたイラストに惹かれて購入したのですが、その内容がとてもおもしろかった。それで、タロットの絵柄にも登場する魔術師や占星術にも関心が広がり、それらの本を読み始めたんです。これが、占いに興味を持った最初のきっかけでしたね」 こうして、さまざまな占いやオカルトの雑誌に目を通すようになった。 「インターネットのない時代、占星術の専門書はほとんど日本に入ってきてはいませんでしたから、貴重な機会でした。英語はまだ読めませんでしたが、星の運行表なら理解できるかもしれないと思い、通訳を介して書店の店主にお勧めの本を紹介してくれるよう頼みました。絵本などを出してきてくれたのですが、そこで母がむっとした様子で『子ども向けではなく、本当にいい本を持ってきてほしい』と店主に言いました。それで出されたのが、ユング派の心理学者で占星術をやっているリズ・グリーンという人の『サターン』という本だったんです。結局それを買ってもらいましたが、当然、まったく読めなかった(笑)。でも、実は後にその本を、自分が翻訳することになるんですね。振り返れば、不思議な縁を感じます」 鏡さんにひとつの転機が訪れたのは、15歳のころだった。とある女子向けの占い雑誌で連載されていた、占星術の入門特集。その最後には、毎回占星術の問題が出されており、読者はその解答を編集部に送って、採点を受けるという企画になっていた。 「君、すごい知識を持っているね。どうだろう。東京に出てきて占いをやってみないか」 こうして鏡さんは、16歳にして占星術の入門コーナーを任された。夏休みを利用して東京に通う鏡さんの姿を見て、母は最初「占いなんて怪しい」と反対したが、実際に連載が始まったのを見て応援し始めたのでしょう。 少女向け占い雑誌は、現在の鏡リュウジの女性誌での活躍の基盤を作る。一方、高校時代には、魔術を研究するサークルに入っていた。そして、すでに出版界で筆を振るっていた 高校時代から、売れっ子の占いライター。鏡さんはいつしかそんな稀有な存在となっていた。 「このころからすでに、占いは近代の目から見れば迷信であり、科学ではないということには気づいていました。それなのになぜ、理性的であるはずの自分がこれほど深く傾倒してしまったのか。その自らの心の動きを知りたいと強く思うようになりました」 魔術の世界への憧れと、科学を正しいとする理性……。その思想的な葛藤を、鏡さんは常に抱え、悩み続けていた。 「ユングは、学者という立場で深層心理について研究する一方で、占いやオカルティズムに共感する心を持っており、本人もそのギャップに悩んできました。近代の知識人で、占いやオカルティズムを否定せずに学者であり続けたのは、ユングくらいでしょう。著作を読んだ時に、『ああ、僕と同じような葛藤を抱えた人がここにいた』と思い、彼についてもっと知りたいと考えるようになりました」 これが、鏡さんが大学でユングを研究するにいたるきっかけである。 「現代の科学世界を生きる自分と、古代の宗教世界を生きる自分……いずれも自分には違いありませんが、その折り合いは、きっと永久につかないのかもしれません」 ユング研究と並行して、いくつもの雑誌に記事を書き続けていた。そのペンネームのひとつとして誕生したのが「鏡リュウジ」という名前である。 「西洋のドラゴンが好きだったので、龍という文字を入れたかったのですが、漢字だとちょっと強面っぽくなってしまうので、仮名にしました。ひらがなよりは、見た目のインパクトが大きいカタカナに。そして鏡という苗字は、自分の見たい姿を投影する存在ということで占いにマッチすると考えて、つけました」 逆さまの自分を映し出す、鏡……。それを自らの名に関したのは、葛藤する心の無意識の表れでもあったのかもしれない。 大学時代にはもうひとつ、大きな転機があった。 「あくまで学生が本業なので、翻訳では、一時的に売れるけれど興味がないようなものはほぼやりませんでした。純粋に自分が面白いと思えるものを受けるようにしていましたね」 はやったら、あかん。 そうして自らの歩む道を見極める一方で、魔法の国への憧れも、持ち続けていた。 メディアの仕事も、順調にこなして、フィールドを広げていた。 「メディアの仕事は楽しかったですが、当時は一生占いで食べていく気はありませんでした。占いを生業にするのは、カッコ悪いと思っていたからです」 「大学側からは、『どちらを本気でやるのか決めてほしい』と迫られました。研究者としてのコースに未練はあったのですが、やはりメディアでの仕事は楽しかったですし……マジメさが足りなかったのでしょう」 そして鏡さんは、27歳で独り立ちすることになった。 それから17年が経った今でも、仕事の内容はほとんど変わらず、忙しい日々を送っている。本人は「ドラマチックでなくてすみません」と笑う。 「人は占いをする動物であり、占いは人間の基本である、というのが僕の持論です。人間の思考法の中には占いがセットされていているから、時に合理性ではなく直感を重視するような行動をとるわけです。近代になって合理主義が登場し、理性を動員すれば直感を抑えて合理的に動くことができるようにはなってきました。それでもまだまだ、占いの感覚は生きています。フィクションとわかっていても物語に運命を感じ、人生に起きる邂逅を運命と呼ぶ。そうした人類の歩みにおいて、その時代の人々がそれぞれ、過去、現在、そして未来を紡ごうとしてきた。それが蓄積されたのが、現代の占いだと思っています」 占いを学術的にとらえている鏡さんに対し、例えば血液型占いのような形で「統計学の立場から分析している」と指摘する人がよくいるそうだが、それは大きな間違いであるという。 2013年にサンクチュアリ出版から発刊し、累計60万部のヒットとなった『12星座の君へシリーズ』も、読者がそれぞれの心と向き合い、今の自分を角度を変えて見つめられる「鏡」のような本になるよう、願いを込めた。 「占いの本を書くうえで、おどさない、決めつけない、というのはずっと大切にしてきましたが、このシリーズでも、あおったりせず、願えば叶うという書き方もしていません。そしてただ『当たってる!』だけで終わらずに、その後の人生について考えられるような構成になっています。自分がいちばん輝ける場所、本当に愛すべき人、自分らしく生きるために必要なこと……占いを入り口として自分を見つめ直すことで、きっとよりよい未来が訪れるはずです」 さて、冒頭の問いに戻ろう。 (取材/文 國天俊治)
2002年に刊行した『魔法の杖』シリーズは100万部突破のベストセラーになり、30年以上も占星術の世界を歩んできた鏡さん。その原点と、人生を追った。
心理占星術研究家・翻訳家。
鏡さんの公式ホームページでは、自身の肩書がそう紹介されている。
鏡さんはいくつもの顔を持ち、ゆえに多忙な日常を送っている。そのエネルギーはどこから来るのか、と尋ねると、「好きなことばかりなので、なんとかこなせてるんじゃないかな」と、涼やかに笑った。
「没頭すると一日中、本を読んでいました。着替えるときまでも本を手放さないので、母によく怒られました」
「母が常々、僕に言って聞かせていたのは、『はやったら、あかん』という言葉でした。“はやる”には、流行、気が急く、調子にのる、といった複数の意味があります。つまり、売れすぎはあかん、目立ちすぎもあかん、といういかにも京都的な感覚の言葉だったと思います。あとは小さなころから『何かをするなら日本で最初のことをやりなさい』とも言われてきました。そうした母の“語録”は、今でも僕の頭の中に刻まれているようです(笑)」
「物心ついたころから、魔法の世界の虜でした。今でいうと、ハリー・ポッターに憧れるような感じでしょうか。魔法学校があって、そこには大きな図書館があって……というような世界が大好きでした。中でも、子ども向け創作童話として人気の『小さい魔女』や、魔女伝説を基にした『ガラス山の魔女たち』などの話が印象に残っているのですが、思い返せば、そうして“魔女もの”に特に心惹かれたことが、後のタロットへの興味関心につながっていったのでしょう」
「特にお気に入りの場所だったのが、鞍馬山。天狗伝説などが有名である一方で、ヨーロッパのオカルティズムの影響を受けた信仰の地であったことなどから、どこかヨーロッパ的な空気も漂っていました。他にはなかなかない、とても不思議で心惹かれる場所でしたね」
現実はいやおうなしに、少年を大人へと変えようと迫った。
こうして突き付けられた理不尽に対し、鏡少年は思いがけない行動に出る。
「僕から母に、『父と離婚してほしい』と頼みました。母の気持ちがもう限界に来ているのに、それでも子どものために我慢しているというのが伝わってきたからです。とにかく母に楽になってほしかった」
当時の社会通念としても、保守的な京都の町の常識としても、離婚は“してはならない、恥ずべきこと”であり、多くの女性はなかなか離婚に踏み切れなかった。
しかし鏡さんの母は、それを跳ね返して離婚という選択をする。その大きな決断を支えたのが我が子からの訴えであったことは、想像に難くない。
そして、離婚により「母が父の負債を背負って共倒れ」という最悪の事態は避けられた。すなわち鏡少年は、そうしてひとつの運命を変えたのだった。
ちょうど当時、世間はオカルトブーム真っ盛り。小学生にもその波が来ていて、占い専門雑誌や本もたくさん出ていた。そんな中、鏡さんが本屋で出会ったのが、1冊のタロット占いの入門書だった。
中学にあがっても、魔術や占星術といった超自然的な領域に対する“熱”が冷めることはなかった。家族でハワイ旅行に行った際、鏡さんが一心不乱に目指したのは、青く透き通る海でも、砂の美しいビーチでもなく、占星術の専門書店だった。
鏡さんはそれを楽しみにしており、雑誌の発売から数日とおかずに投稿した。小学校からこつこつと積み重ねてきた知識のおかげで、解答はいつもパーフェクト。最終的にその雑誌の優秀賞までもらった。
そしてある日、鏡さんのもとに編集部から1本の電話がかかってきた。
思いがけぬ誘いだったが、当時はまだ中学生である。それを伝えると、編集部の担当者は「そんなに若かったのか!」と、たいそう驚いたという。
「占い雑誌の世界は狭いですから、おそらくその編集部から話が広まったのでしょう。高校に入学したころには、『15歳の占い師がいる』と話題になっていたようで、別の出版社からも問い合わせがくるようになりました。最初に連絡をくださった編集プロダクションの紹介で、とある占い雑誌で連載を持つことになったんです。今でいうと、読者モデルのようなものでしょうか」
「16歳で占いをやる人は当時いませんでしたから、母の教えにある『日本で最初のことをやりなさい』を実践したともいえます。それを母は、怒れませんよね。ただし、『はやったら、あかん』は鉄則 (笑)」
サークルの先輩たちが「かわいい後輩」として鏡さんを「ユリイカ」など硬派な雑誌の編集部にも紹介してくれた。
そのつながりで、鏡さんもまた大学時代有名雑誌で記事を書くようになっていった。これが専門的な書籍、翻訳、論考の仕事への道を開いてくれた。
ただし、それだけ占いの世界に浸かりながらも、鏡さん自身は一般的な占いを文字どおりには信じていなかったという。
それを何とか解決しようと、さまざまな本を読んでいくうちに出会ったのが、スイスの精神科医であり心理学者であった、カール・グスタフ・ユングだった。
国際基督教大学に進学し、当時の人文科学学科で宗教学を専攻。卒業論文も、修士論文もユングについてまとめた。現在でもその研究は続き、ユング学会のシンポジウムで登壇するほどの専門家となった。しかし未だに心の葛藤が続いているという。
当時、アルバイトで翻訳会社からの仕事を引き受けていた。その内容は、洋書を渡されて編集者のためにそれを要約するというものだったが、それを続けていたところ「せっかくだから本格的に翻訳をやってみないか」と編集部から声がかかった。
そうしてトライした占いの翻訳本が、なんと10万部のヒット。そこから学業と並行して翻訳を手掛け始め、年間数冊のペースで出版していき、それだけで学生としては十分すぎる収入を得ることができるようになった。
しかし鏡さんは、そこで自分を見失わなかった。
母の教えは、鏡さんの心にしっかりと根を下ろしていた。
実は高校時代から、占星術や魔術の分野で名の知れたイギリスの著者に手紙を書いており、そのうち数人からは返事をもらって親睦を深めていた。そして大学では、イギリスに足を運んで彼らと実際に会い、そこから家族ぐるみで付き合うようになった。
また、イギリスの「魔術学校」で通信教育を受けるなどもして、今でいう「ハリー・ポッター的」世界に存分に浸っていたのだった。
当時、開局直後だったラジオ局「J-WAVE」でアルバイトをしていた友人のつながりで、ラジオの占いコーナーに携わり、レギュラー番組を手掛けた。コーナーは長く続き、人気を博した。
こうして、大学にいながら社会人なみの収入を得ていたが、鏡さんは独立などは考えず、学問の道を究めようと大学院に進学した。
大学院で修士課程を終えた際に、大学から「非常勤講師として働かないか」と誘われ、鏡さんはそれを受諾。講師となった矢先に、大学側にメディアで仕事をやっていることがばれてしまった。
メディアの仕事には相変わらず恵まれてはいたが、将来に対する不安は大きかったという。
「最初は怖かったですよ。相変わらず、占いに対する葛藤も抱え続けていましたし、日々もやもやしながらも、目の前の仕事を必死にやっていた感じです」
自営業者となったからには、これまでのような受けの姿勢ではなく、自ら積極的に仕事を取りに行かねばならない。編集者に企画を持ち込み、アメリカの「天使ブーム」を日本に紹介するなど、精力的に活動を続けた。
そんな努力に、時世も微笑んだ。2000年にスタートした携帯電話の占い配信サービス。そこで星占いを担当し、爆発的なヒットとなった。さらに翌年には、翻訳本『魔法の杖』を刊行。欧米では人気の占術であった「ビブリオマンシー」を日本で初めて紹介し、これがシリーズ100万部突破のベストセラーにつながった。
こうして「鏡リュウジ」という名は、占いの世界では欠かせない存在となっていった。
占いに対するスタンスもまったく変化していないという。
「統計は不特定多数を相手にした科学ですが、占いが応答するのは個人の領域です。例えば医療統計学では『日本人の○○割ががんになる』と分析します。しかし占いでは『なぜ私はがんになったのか』という心と向き合います。真逆の存在なんですね」
『12星座の君へシリーズ』は累計60万部のヒットに(2013年、サンクチュアリ出版刊)。今までなかった“もっと自由に、もっと自分らしく生きる”ための星座の本。
学者、研究家、翻訳家、そしてメディアに登場する際のエンターテイナー。
いずれも本人には違いないが、いったいその実像は、どこにあるのだろう。「未来」についての質問の答えに、その一端が表れているかもしれない。
「今後は、占星術の学問的な部分をもっと広めていければと思っています。学者と一般の方々とをつなぐ意味での、“翻訳者”になりたいですね」 プロフィール
鏡リュウジ
1968年、京都生まれ。心理占星術研究家・翻訳家。国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了(比較文化)。
高校時代より、星占い記事を執筆するなど活躍。心理学的アプローチをまじえた占星術を日本で紹介することによって、占いマニア以外の人にも幅広くアピールすることに成功。
占星術の第一人者として地位を確たるものとし、一般女性誌の占い特集では欠くことのできない存在となる。また、大学で教鞭をとるなど、アカデミックな世界での占星術の紹介にも積極的。英国占星術協会会員、日本トランスパーソナル学会理事、京都文教大学、平安女学院大学客員教授などを務める。
プロフィール
鏡リュウジ
1968年、京都生まれ。心理占星術研究家・翻訳家。国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了(比較文化)。
高校時代より、星占い記事を執筆するなど活躍。心理学的アプローチをまじえた占星術を日本で紹介することによって、占いマニア以外の人にも幅広くアピールすることに成功。
占星術の第一人者として地位を確たるものとし、一般女性誌の占い特集では欠くことのできない存在となる。また、大学で教鞭をとるなど、アカデミックな世界での占星術の紹介にも積極的。英国占星術協会会員、日本トランスパーソナル学会理事、京都文教大学、平安女学院大学客員教授などを務める。

12星座の君へシリーズ
鏡リュウジ(著)
952円+税
![]()
もっと自由に、もっと自分らしく生きるための星座の本